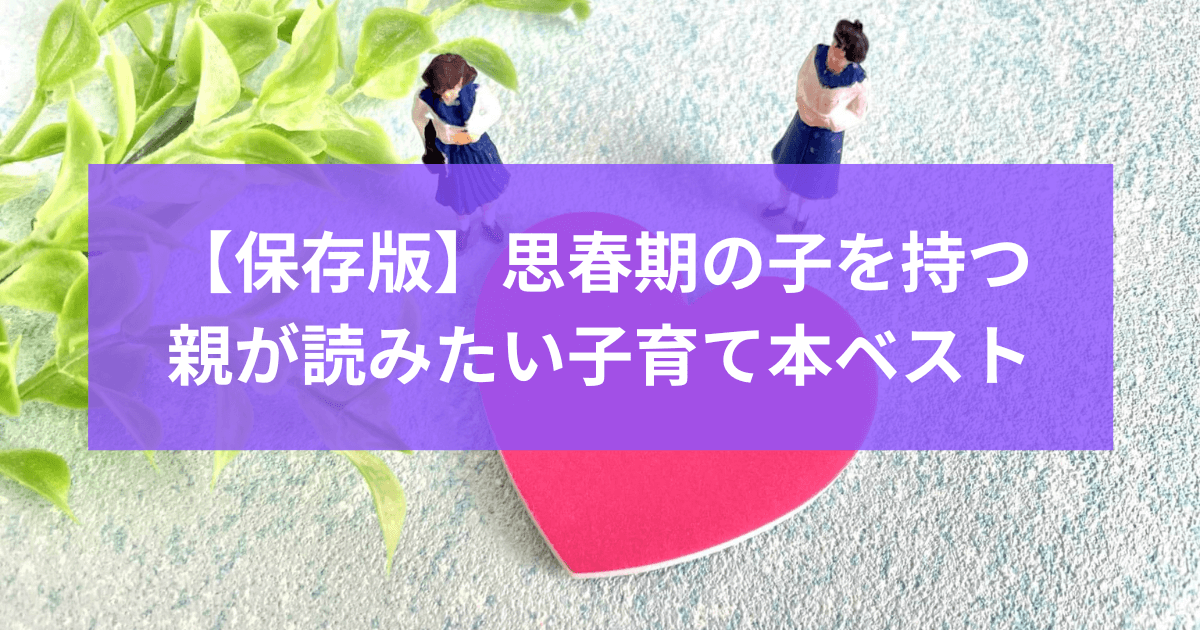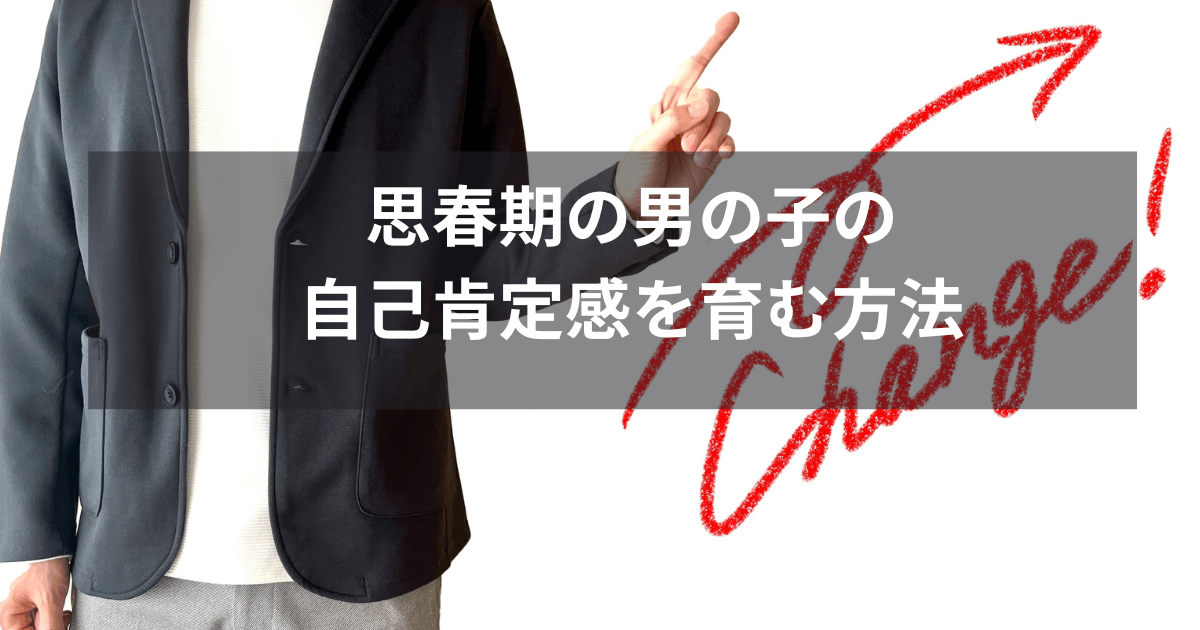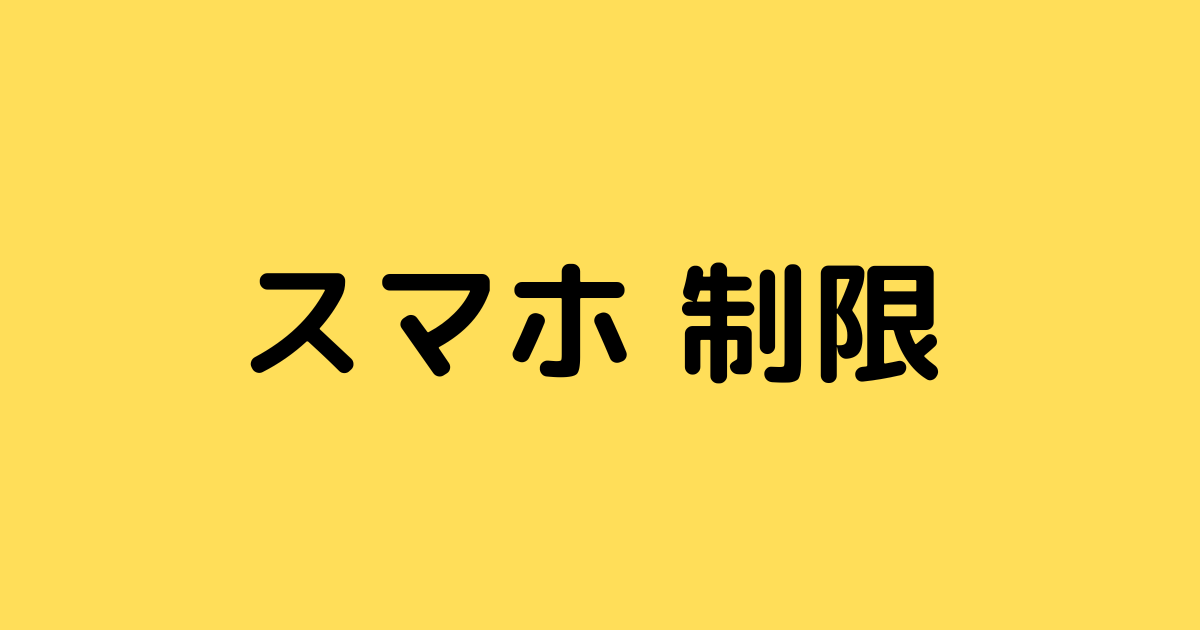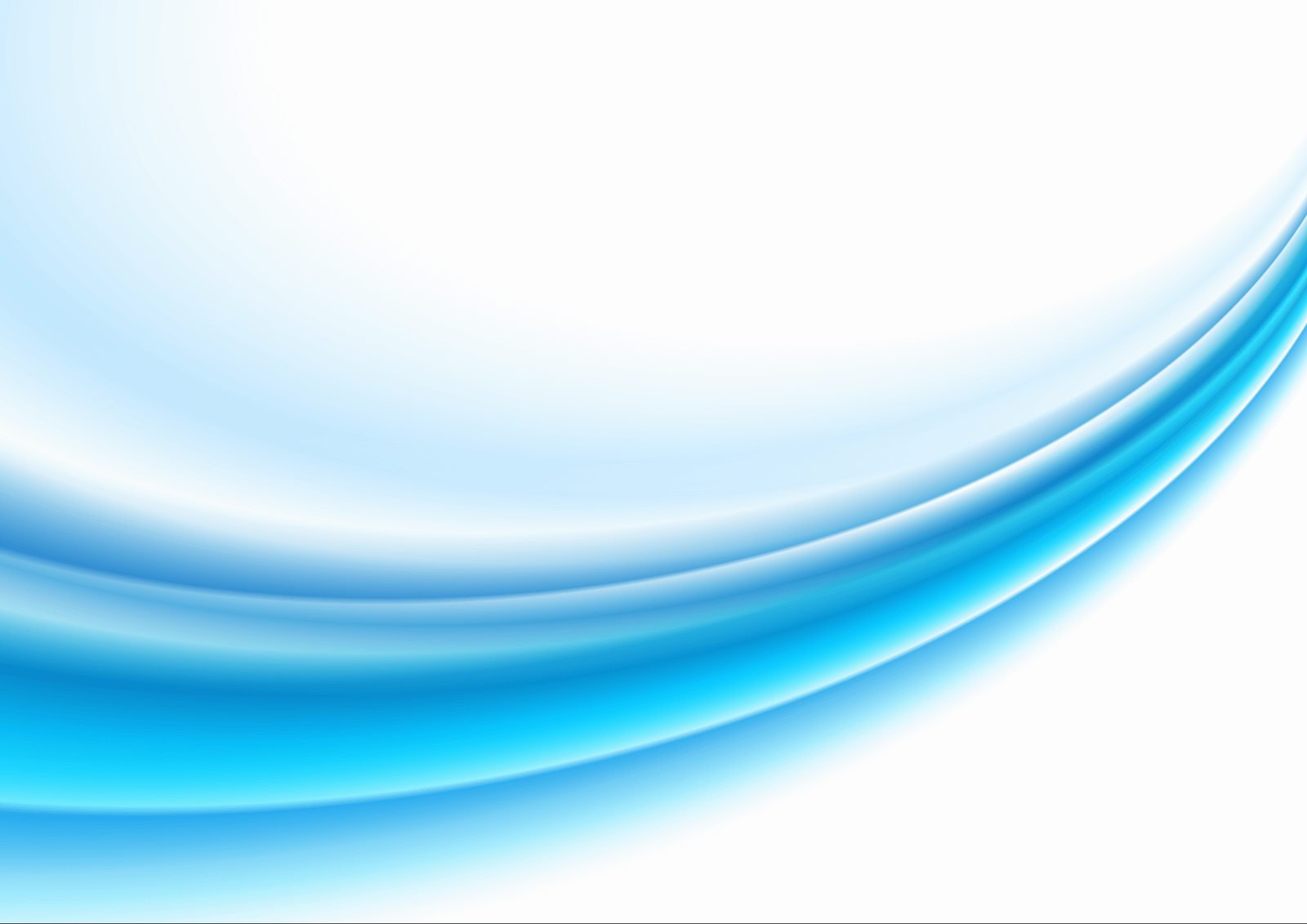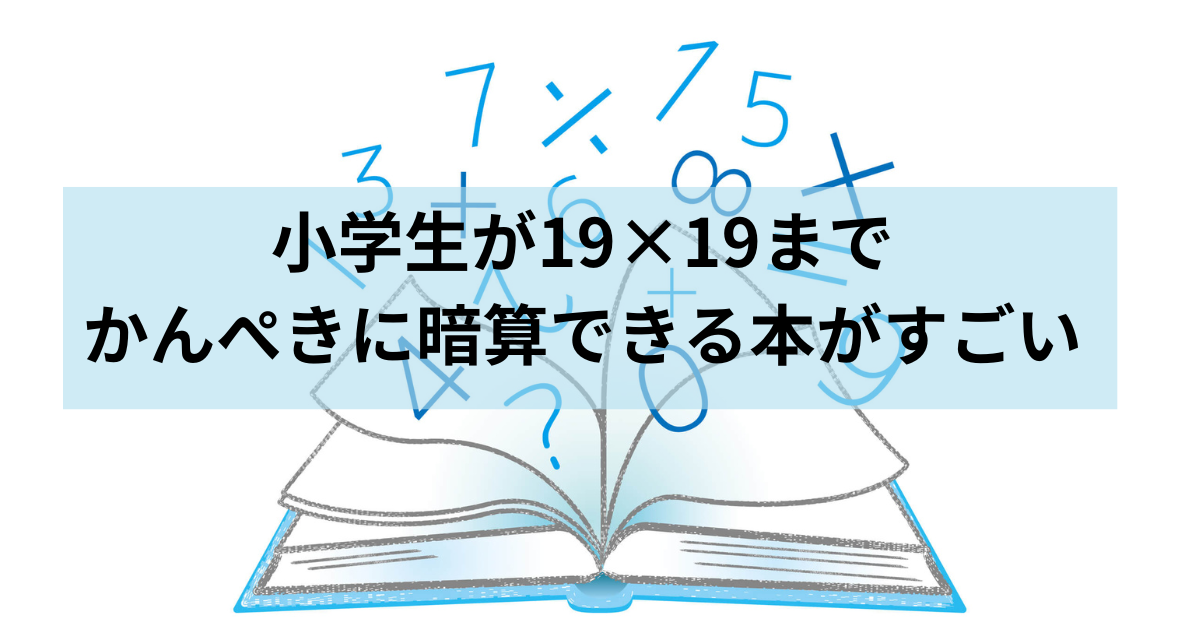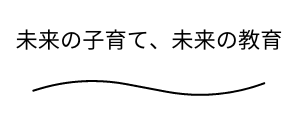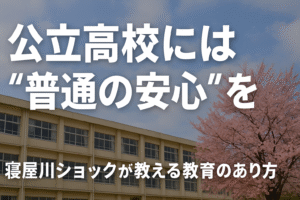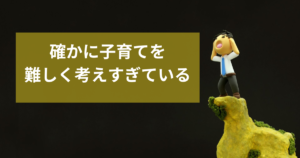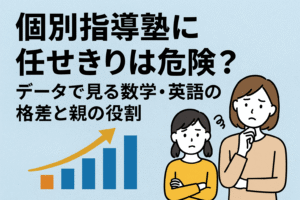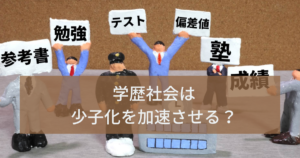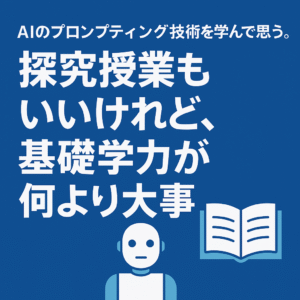久しぶりに学校関連の記事を投稿してみたいと思います。
長女は今私立中学に通っています。毎日元気に登校しています!とお伝えしたいところですが、長女は身体が強くない事もあって、少々休みながら学校に通っています。
これについて親の僕はどう思っているか?
「休み休みでも学校へ通えてたらいいやん!」と思っています。もちろん、健康で毎日学校に通えるに越した事はないですけど、今の時代、毎日学校へ通えないと健全ではない、不登校と騒ぎ立てるのは違うなと思っています。
小中学校で不登校が過去最多になったというニュースがありましたけど、今回は不登校をテーマに僕の思うことを書いてみたいと思います。
不登校の定義とは?
令和3年度の問題行動・不登校調査では、小中学校の不登校児童数は、約24万5千人だったそうです。前年度よりも5万人近く増えたと社会問題になっています。
しかしです。
まず、何をもって不登校というのでしょうか?不登校の定義って何?ということで調べてみました。
国立教育政策研究所*1の資料から不登校の説明を抜粋するとこうです。
不登校については、学校基本調査において、年度内に30日以上欠席した児童生徒を長期欠席者として、その欠席理由を「病気」「経済的理由」「学校ぎらい」「その他」に区分して調査していたが、その後「不登校」という用語が一般的に使用されるようになり、平成10年度から、上記区分のうち「学校ぎらい」を「不登校」に名称変更した。
簡単にいうと、風邪とかじゃなくて、「学校に行きたくない」で年間30日以上休むと不登校。ということです。年間の授業数は約200日、35週と想定すると、およそですが週に1日程度休めば不登校になる。
僕はそもそもこの「不登校」の基準が今の時代にあっていないなって思うんです。
親も自分の中高時代を振り返って、子どもは毎日学校へ通うものと思っている人は多いかもしれません。ですが、今の子の学校は、僕ら親世代とはまるで違うものだということを理解しておいたほうがいい。
〇ちなみにマレーシアには不登校の概念がないそうです。
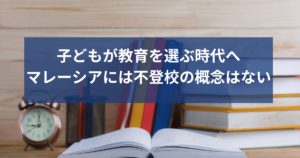
不登校の基準が今の時代にあっていないと思う理由
人間関係がより複雑化している
まず学校での人間関係です。LINE等のSNSの登場で友だち関係は複雑化し、特に女の子を持つ親は頭が痛いと思います。
思春期の女の子は「みんな仲良く」ではいられないことを親は知っておくべきというのは、「思春期の女の子が親に求めていること」*2の著者・中野 日出美氏。
僕らの子ども時代は、「友達100人できるかな~♪」という歌がありましたが、いやいや、みんながみんな仲良くしなさい!なんて今の時代、時代遅れです。
子ども達の価値観も多様化し、モンスターペアレントなんかも登場し、先生の生徒をまとめる力、求心力も残念ながらずいぶん落ちてきたように思います。
クラスメートの事を「たまたま近所の同い年を集めただけ」といい、
友達でもないし仲良しでもない、好きでもない連中と喧嘩しないで平穏に暮らす練習をするのが学校じゃないか。
というのは、僕が大好きで何度も紹介させていただいているブルーハーツ甲本ヒロト氏*3です。
学校は社会の縮図です。会社にだって合う人、合わない人がいるのですから、学校だけ、みんな仲良くしなさいって子どもを追い詰めてはいけないと思います。
子どもは子どもなりに学校で戦っているんです。身体も心も休めながらでも学校へ通えてたらよくないですか?
今の子はやらなければいけない事が多すぎて疲れている
また、今の子は、やることが多すぎて本当に疲れています。子どもたちは成功することを親から求められて疲弊しているというのは、「やりすぎ教育 商品化する子どもたち」*4の著者・武田信子氏
今の子ども達は、勉強はもちろんの事、これからは勉強だけではやっていけない時代だといわれ、習い事もたくさんしている。塾にも通い、何か熱中するものを見つけなさいと言われて、家でマンガを読んでいる暇もないのではないでしょうか?
これでは忙しすぎて身体も心も休めるときがありません。それでも僕らの時代と比較して、「学校は毎日行くべきもんだ」なんて言えるでしょうか?
↓子どもにプレッシャーをかけすぎていたと思った時に読みたい本
僕らの時代は毎日通うのが当たり前だったかもしれないけど、時間的にはずいぶん余裕がありました。そう考えると今の子は、休みながらでも完走できたらよいんなんじゃないかな?って僕は思うんです。
長女は私立中学に通っているのですが、その点ものすごく柔軟で助かっています。娘だけじゃなくて、クラス全体で、毎日通っていない子も割といる。長期で学校に通えない子は、オンライン授業だってしてくれる。
他の学校はわかりませんが、少なくとも我が子が通う私立中学の魅力はこの柔軟さで、子どもに寄り添ってくれるというか、事情を汲んでくれる。長女はこの中学へ通わせてよかったなと思っています。
一方の次女は、公立中学へ進学する予定です。今のところ本当にたくましく学校に通ってくれていますが、選択肢が公立中学一択であることに不安がないといえばウソになります。
学校が通いづらくなる公教育の仕組みはやめる
高校入学に必要?な曖昧な内申点のつけかたはやめる
公立中学は、高校進学時に内申点が必要で、それは学校の先生の裁量が大きいって聞きますけど、まずそれが不安です。
↓僕には小学校の通信簿さえ評価の基準がわからない
例えば、週に1回休みながらでも学校へ通えたとしても、今の文科省の基準では不登校。これで内申点が下がると考えると、子どもが悩んでいるのに、
「無理してでも学校に行きなさい!」
なんてなりそうで、めちゃくちゃ窮屈です。
2040 教育のミライ*5の著者・磯津 政明氏によると、義務教育を行う機関が文科省管轄の小中学校しかない先進国は日本だけ。アメリカではホームスクールが10%を超える約5000万人が学んでいるそうですね。オンラインも当たり前になった今、公立学校に通えたか通えなかったかだけで評価されるのは今の時代にあっているのだろうか?
ゆぽたん*6という学校に通っていないYOUTUBERが話題ですけど、よくネットで叩かれていますよね。僕は特別ゆぽたんを応援しているわけではないですけど、学校へ通っている、通っていないという話だけで叩くのは違うかなと思う。
学区制もやめる
僕は学区制もいい加減、時代に合っていないと思うのでやめてほしいと思っています。
学校が合わないなら変える!子どもに選択肢をたくさん用意してあげてほしいんですよね。それを学校の都合でずっと学区制を残しているから、転校するのも大変です。いじめまでいかなくても、学校に通いづらいという子はたくさんいます。もっと楽に学校を選べるようにしてほしい。
不登校は公教育だけがなんとかしようと思っても限界がある
文科省の考える不登校対策*7は
・30万人の不登校の児童・生徒全ての学びの場の確保する
・心の小さなSOSを見逃さず、「チーム学校」で支援する
・学校を「みんなが安心して学べる」場所にする
・不登校を科学的に把握する
なんだそうです。理想といえば理想ですけど、ただでさえ、学校の先生の仕事が増えているのに、これ以上学校に負担を求めるのは酷というものです。
多様な学びの場を提供するという方向性はいいと思うけど、公教育だけでなんとかしようと思わないことが大事だと思います。
例えば、ドワンゴのN中、N高いいですね。ネットでも学べるフリースクール。
そして、こうした多様な選択肢を支援する東京都のフリースクールの補助倍増っていうニュースはものすごく素敵だなって思いました。
文科省による不登校特例校*8の設置も進んでいますけど、何でもかんでも公教育で解決しようとせず、民間にも頼りながら子どもに多様な選択肢を用意してあげることが、一番の不登校対策というか、不登校という概念がなくなるんじゃないかと思います。
国だけで、文科省だけで、何でも解決なんてできないですよ。お金は出すけど、口は出さないが代名詞のソフトバンクの孫オーナー*9じゃないですけど、国は経済面で不登校の家庭を支援、バックアップしてくれたらいいんじゃないかな?僕はそう思います。
誰も不登校児になりたくてなっているわけではない。出来ればですが、学校を完走できたらいいですね。
最後に。僕は出来れば。。。出来ればですが、学校は休みながらでも、フリースクールでもネットスクールでもいいから完走できたらいいなって思っている人です。
上述したとおり、学校は社会の縮図でもありますから、可能であれば何かしらの形で学校に通えると将来役に立つこともあるのかなと思います。
働き方も多様化しています。会社にだって毎日出勤しなくてもいいかもしれないし、週休3日制に当たり前のようになるかもしれない。だから毎日学校へ通わないといけないという押し付けはもう不要です。けれでも、合わない人とでも、なんとかやっていく。その術を学べるのが学校だとしたら、完走できれば、それはひとつ自信にはなるかなって思っています。
誰も好きで不登校になっているわけじゃありません。誰もが自分のあう居場所を探しているはずです。だから、多様な選択肢を用意してあげる事が大事で、公教育だけに子どもを縛らない事も大事だと思うんですね。
*2:
【書評】「思春期の女の子が親に求めていること」を読んだ。思春期は、それまでの子育てをやり直す最後のチャンス! – 子育て本をたくさん読むパパの子育てブログ
*3:学校に馴染めない子を救うブルーハーツ 甲本ヒロトの伝説の言葉 – 子育て本をたくさん読むパパの子育てブログ
*4:
【書評】やりすぎ教育 商品化する子どもたちを読んだ – 子育て本をたくさん読むパパの子育てブログ
*5:
日本の教育の未来を「ど真剣」に考えさせられた【書評】2040教育のミライ – 子育て本をたくさん読むパパの子育てブログ
*6:
*7:
多様な学びの場を 不登校対策で文科相が協力者会議に検討方針 – 日本教育新聞電子版 NIKKYOWEB
*8:
大阪府内で初めて「不登校特例校」来春開校へ|NHK 関西のニュース
*9: