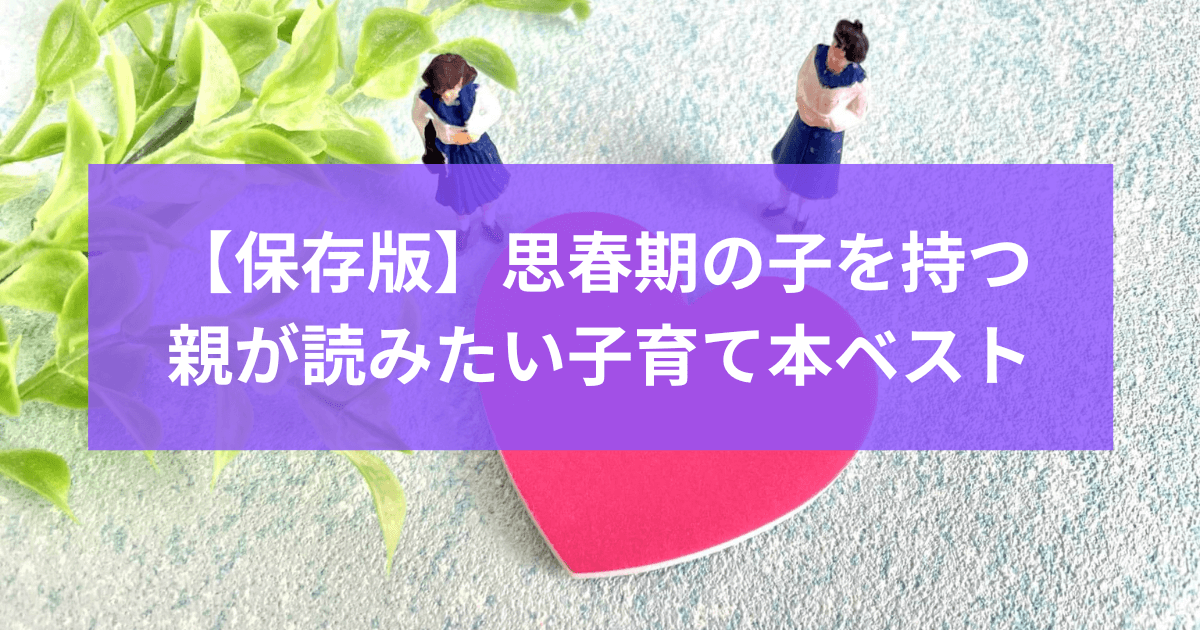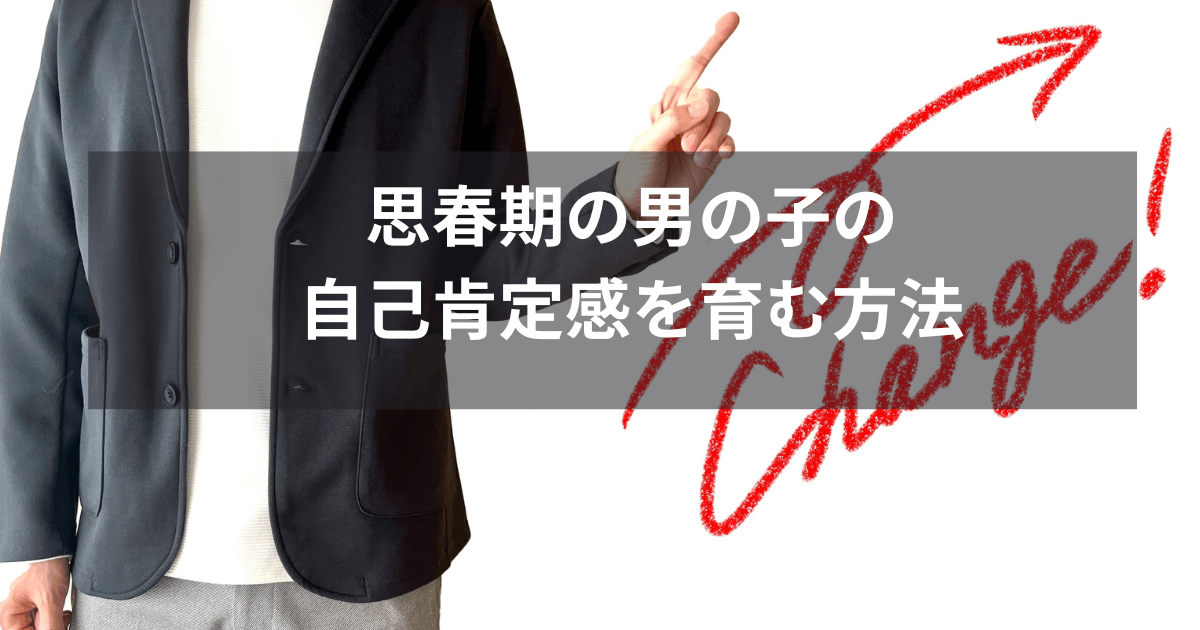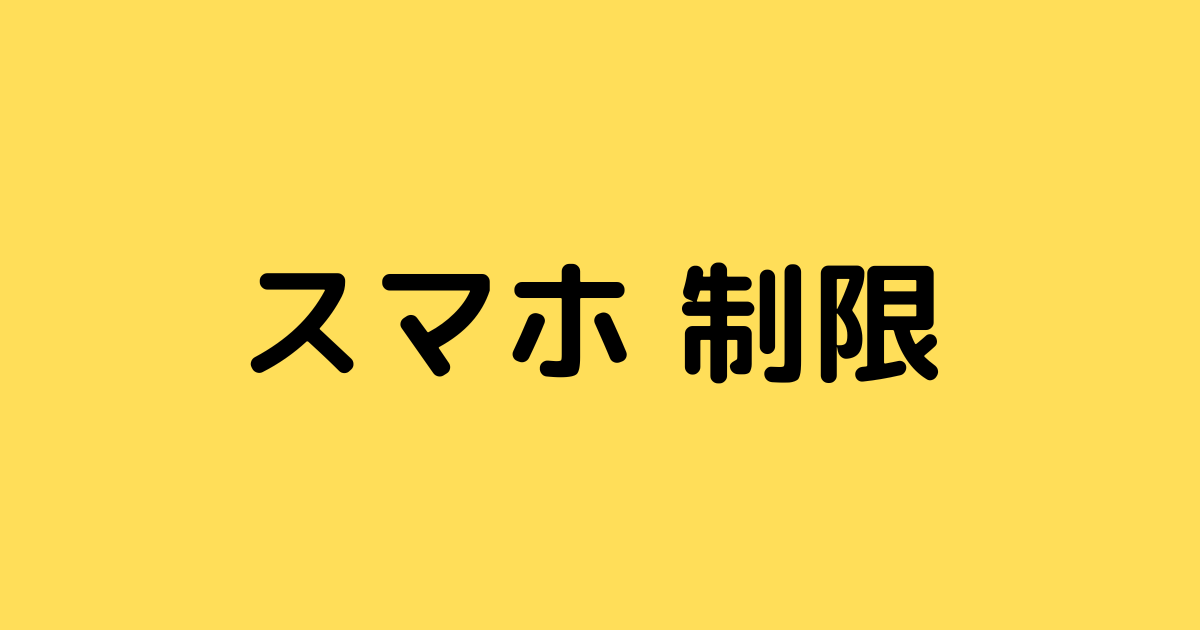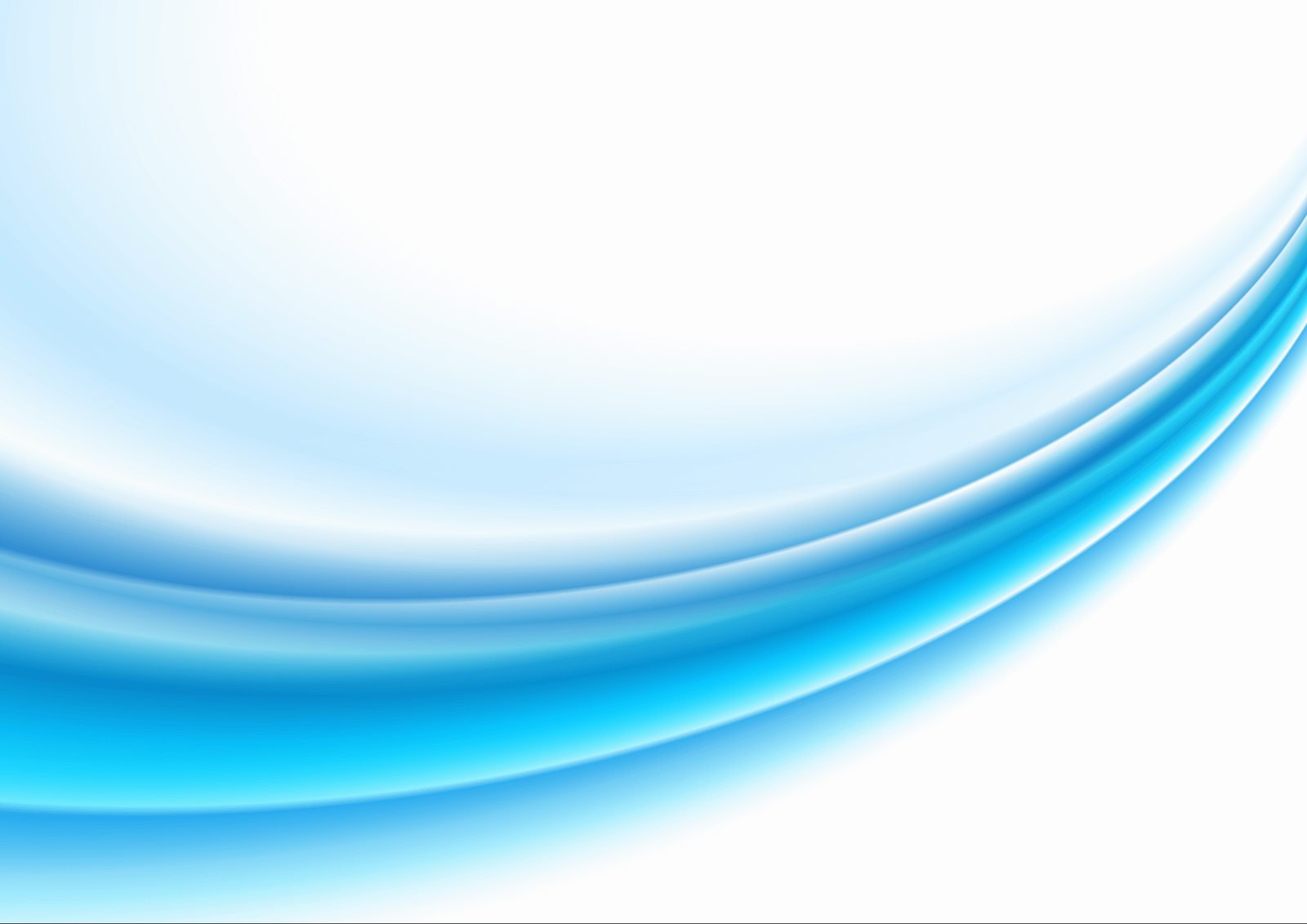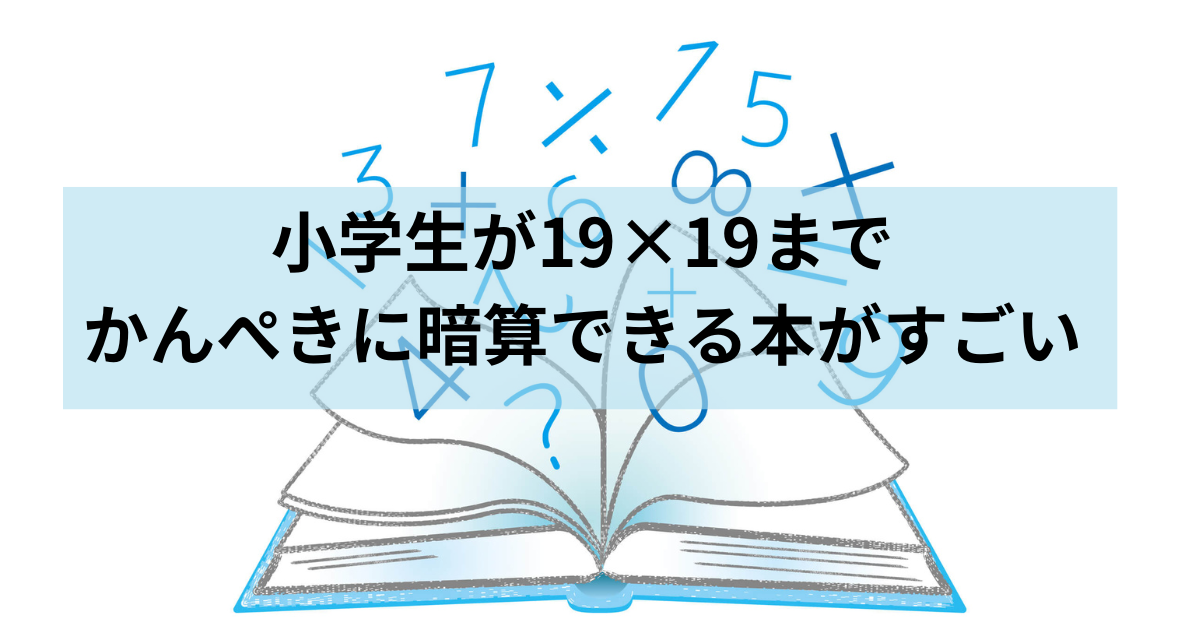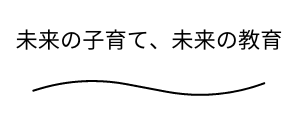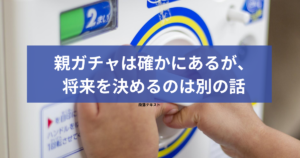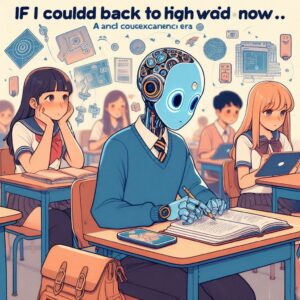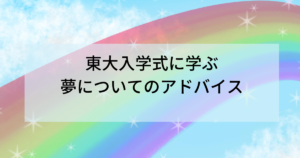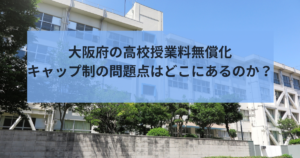中学生の娘を持つ僕が、娘のために選んだ塾のお話を先般させていただきました。

次女は現在個別指導塾に通っていて、実は最初の通知表は非常によい成績でした。とはいえ、中学1年生はまだ小学生の延長のようなもので、これから学習内容がグッと難しくなるのは間違いありません。とくに数学や英語などは、できる子とそうでない子の差が広がっていくのがこれからの傾向でしょう。
名古屋大学附属高校生による統計センターの学生作品では、以下のような分析が示されています。
- 英語の平均正答率:
- 大都市:48.6%
- へき地:39.9%
→ その差は8.7ポイント 国家安全保障局
- 同じ年・同じ調査における他の教科との比較:
- 国語:大都市とへき地で 1.7ポイントの差
- 数学:同じく 5.1ポイントの差
→ 英語の地域格差が最も大きく出ている 国家安全保障局
これは地域間格差の統計ですが、他にもSESによる格差も拡大しているという指摘もあります。これは塾に通っている、通っていないの差もあるように思えますが、塾に通っているからといって必ずしも成績が伸びるとは限らないというのも、親として心に留めておきたい事実です。
塾に入っているから安心、というわけではなく、塾を上手く「利用する」視点が親には欠かせないと思っています。僕は長女の中学受験のとき、ずっと勉強を見ていたので、今回は多少余裕をもって次女の塾の様子を見守れているように感じています。
そこで今回は、個別指導塾に限らず、塾をうまく活用するための具体的な考え方を、親としての立場からまとめてみました。
1.塾を信頼して基本はお任せすること
まず第一に大事だと考えているのは、「塾を信頼し、基本的にはお任せする姿勢を示すこと」です。もちろん、成績が思わしくないときに親が過剰に介入してしまうのは避けたいところですが、かといって信頼できないという態度を取るのも禁物です。塾側からすると、信頼されていないと感じる親とは、指導しにくい関係になってしまうものです。
ですから、日々の様子をこまめに観察しつつ、基本線として「塾の指導を信頼しています」という意志を伝えておくことが重要です。もちろん成績が上がったときには、「塾のおかげで成績が上がりました。ありがとうございます」と感謝の気持ちを伝えることも忘れずに。誰だって、感謝されるともっと頑張ろうと思うものです。
加えて、個別指導塾には親が知らない情報やノウハウが豊富に蓄積されています。それらを惜しみなく子どもに提供してもらうためにも、親としては塾との信頼関係を丁寧に築くことが重要です。
2.しかし信用しきらず、観察も怠らない
一方で、完全に塾にお任せで良いわけではない、という境地にも気づきました。実際、今回の娘の成績は良かったのですが、塾の宿題には少し気になる点がありました。娘が理解していない「応用問題」を解かされていたのです。
基礎が身についていない状態で応用問題に取り組んでも、いつまでたっても理解できないし、当然解けません。そこで僕はまず、塾の宿題に取りかかる前に、娘に簡単な基礎問題を出して、ちゃんと理解できているかどうか確認するようにしました。理解できているとわかったら、ようやく塾の応用問題に取り組ませる、という流れです。
これは、長女の中学受験時代に学んだ方法に通じます。集団塾では、難関中学向けの問題とそうでない問題が混ざっており、塾の先生が「あなたにこの問題は解かせなくてもいいです」と取捨選択してくださっていました。つまり、今やるべき問題とそうでない問題とを見極めて、効率的に取り組む姿勢が本当に理にかなっている、と思ったのです。
個別塾の先生は、現役大学生で難関大学に通う方も多く、自分が解ける問題だからこそ子どもにも出してしまうケースがあるかもしれません。しかし、我が子の理解がそこまで追いついていない可能性を見落としがちなのは、親でも要注意ですね。
ただし重要なのは、問題の解き方が塾の先生と違う(僕自身がやり方を変えてしまう)のは絶対にNGです。僕が上述したように「塾を信頼しています」と伝えることが大切だと書きましたが、この点でも塾のやり方に沿って子どもを導く姿勢を保つことが大切です。
3.信頼と観察のバランスを取ることが肝心
結局のところ、僕が考える「個別指導塾の上手な使い方」は、この信頼と観察のバランスに尽きます。高いお金を払っているからといって、自動的に成績が上がるわけではありません。塾と親の連携と信頼関係があって初めて、子どもは最大限伸びていきます。
ですから、塾を基本的には任せつつ、必要なときには親としてサポートする。この連携が、未来の教育のあり方にも通じる重要な礎になると思っています。
まとめ:親としての塾との付き合い方
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 1.塾を信頼し基本はお任せ | 「信頼しています」と伝え、成果があれば感謝を伝える |
| 2.信用しきらず、観察を怠らない | 基礎が理解できているかを確認し、必要なサポートをする |
| 3.信頼と観察のバランスを取る | 親も塾も連携できる関係を築くことが大切 |
最後に、これは塾に限らず、これからますます「個別化・AI化」が進行する近未来の教育においても同じだと感じています。つまり、親が子どもを信じ、外部リソースに任せつつ、必要なときには的確なサポートを入れる――これは確実に求められる力です。
僕としては、娘がこれからの学習で伸びていく姿を見守りながら、塾と連携しつつ、僕も少しずつ一歩ずつ学び続けたいと思います。
以上が、僕の親視点からの「個別指導塾に任せきりにならない使い方」の考察です。偉そうなことを書きましたが、うちの娘もこれからが本番です。いい時も悪い時もあると思いますが、試行錯誤しながら、よい環境で高校受験を迎えられるようにサポートしていきたいなと思っています。
※この文章は引用文献と私の意見をChatGPTに与え出力した記事を修正加筆して完成させたものです。私が考えることをいとも簡単に表現してくれるChatGPTすごいです!