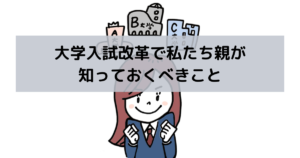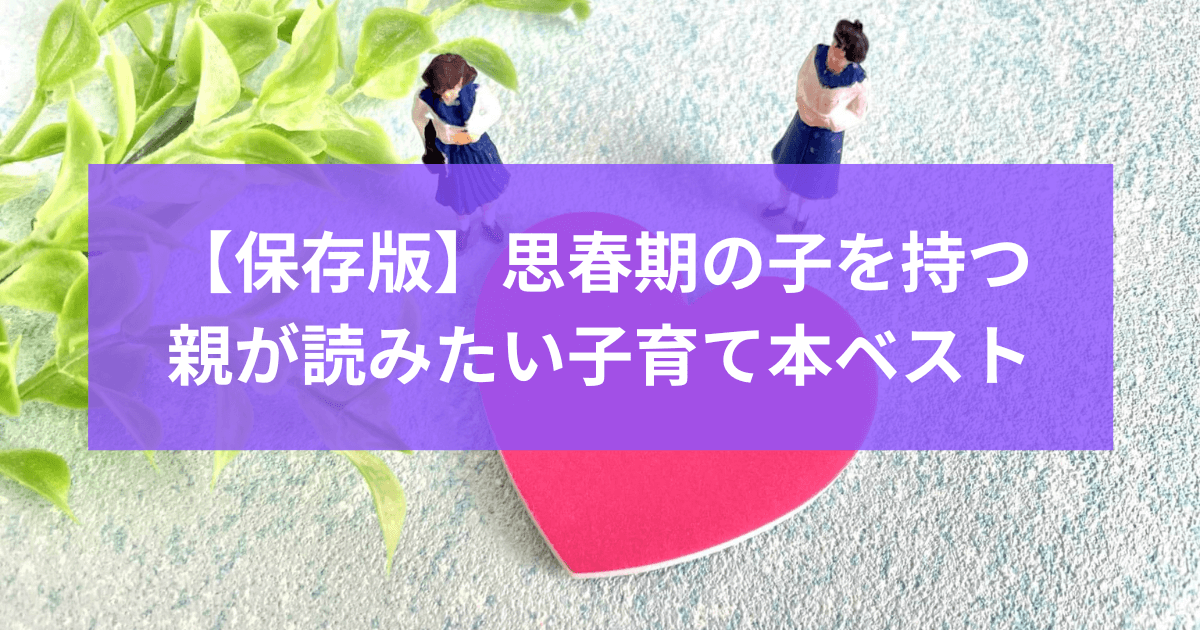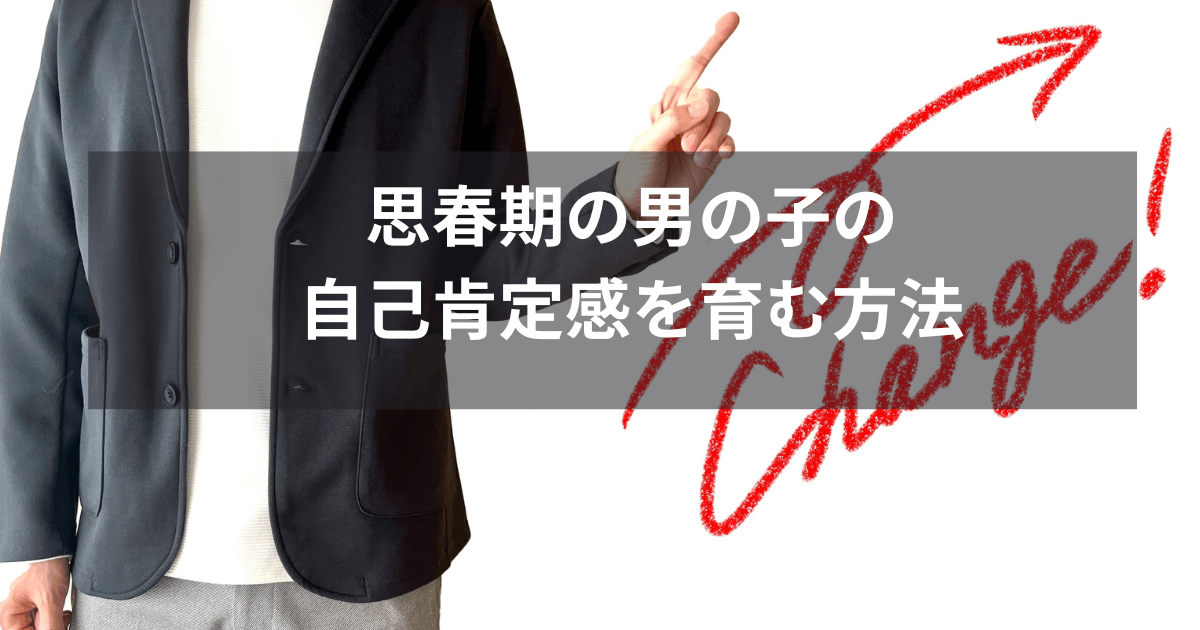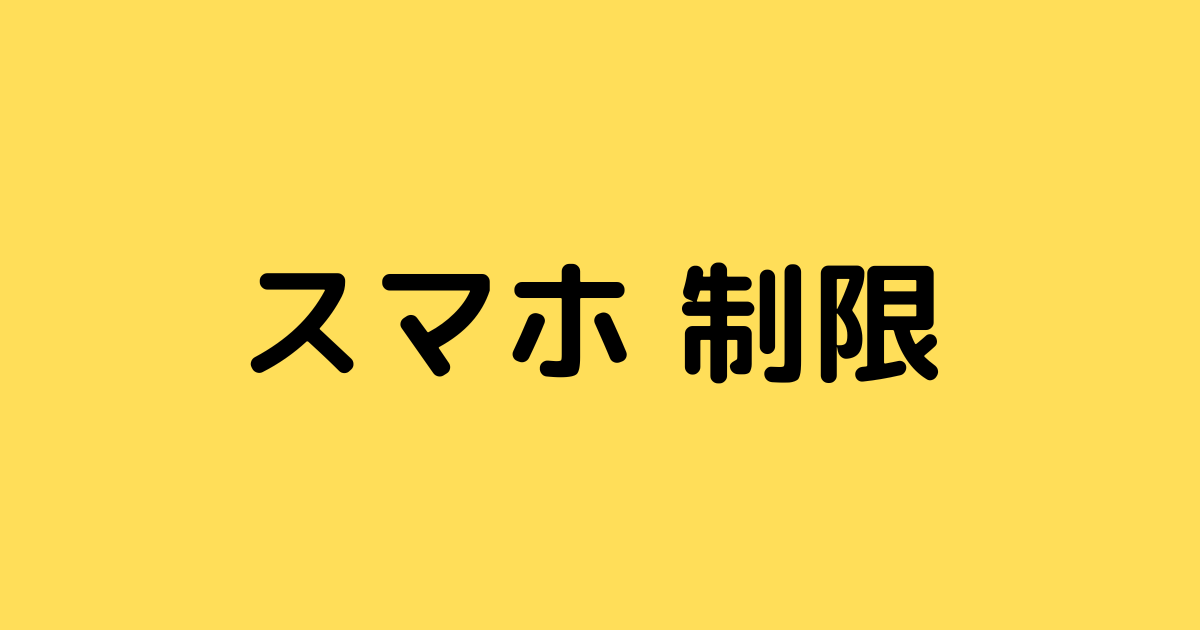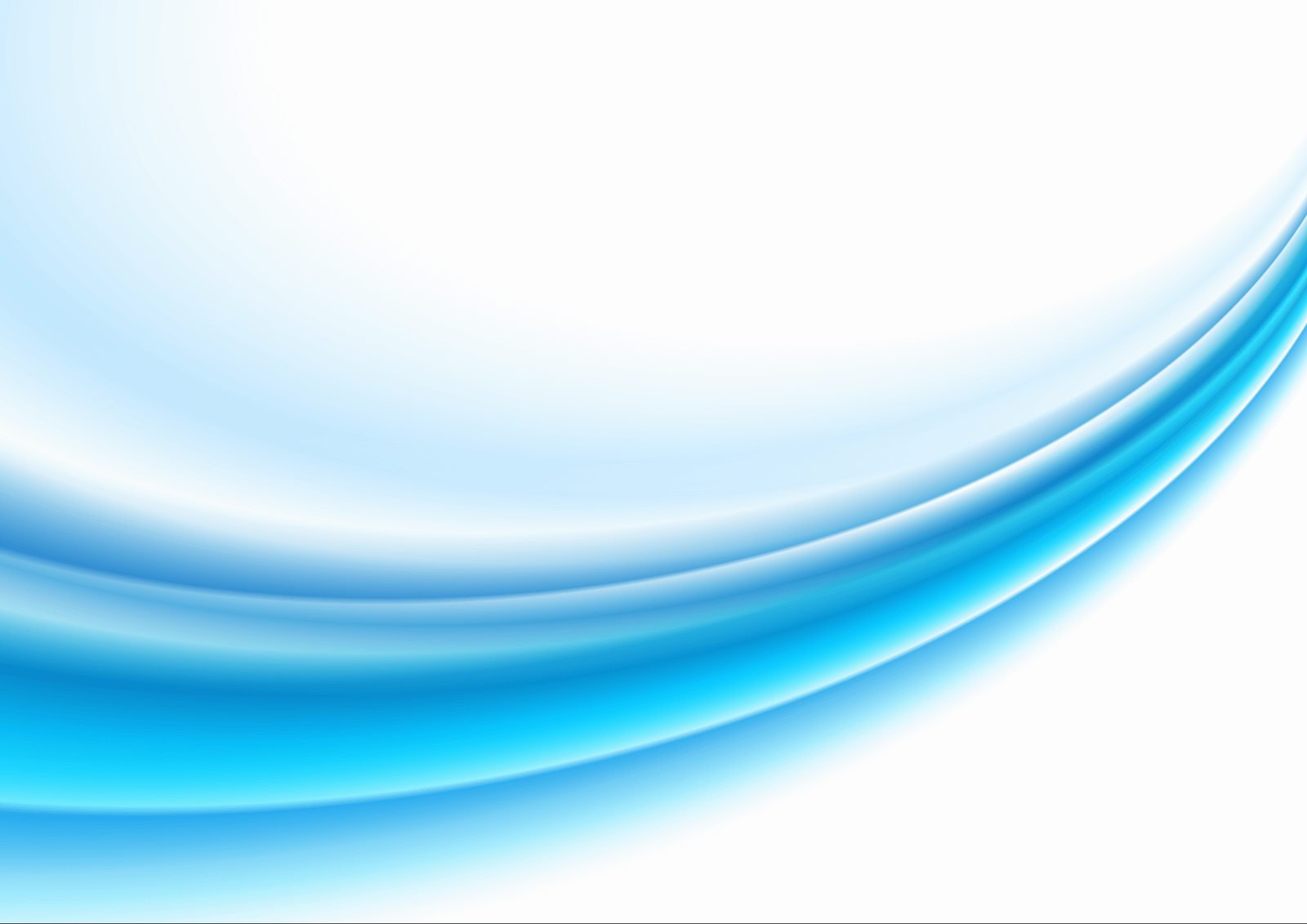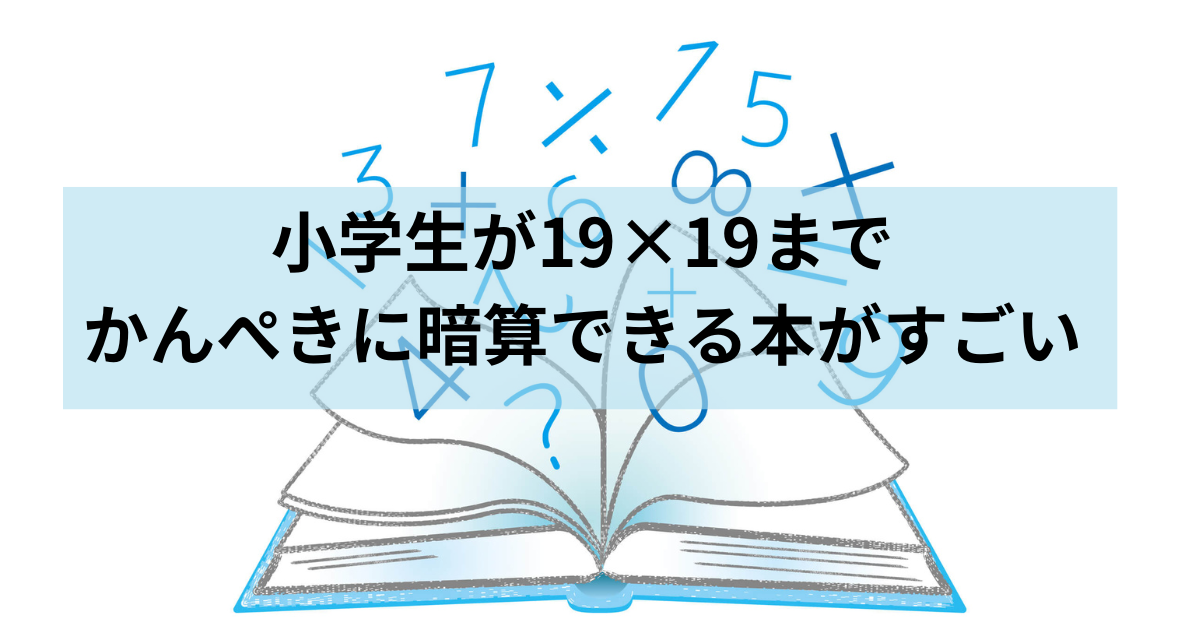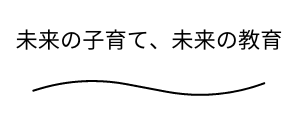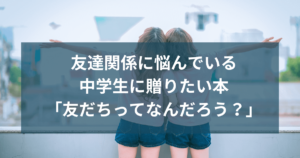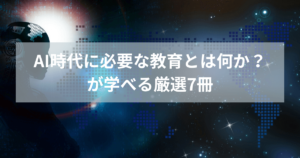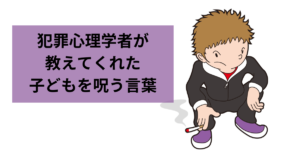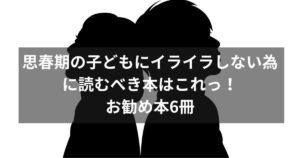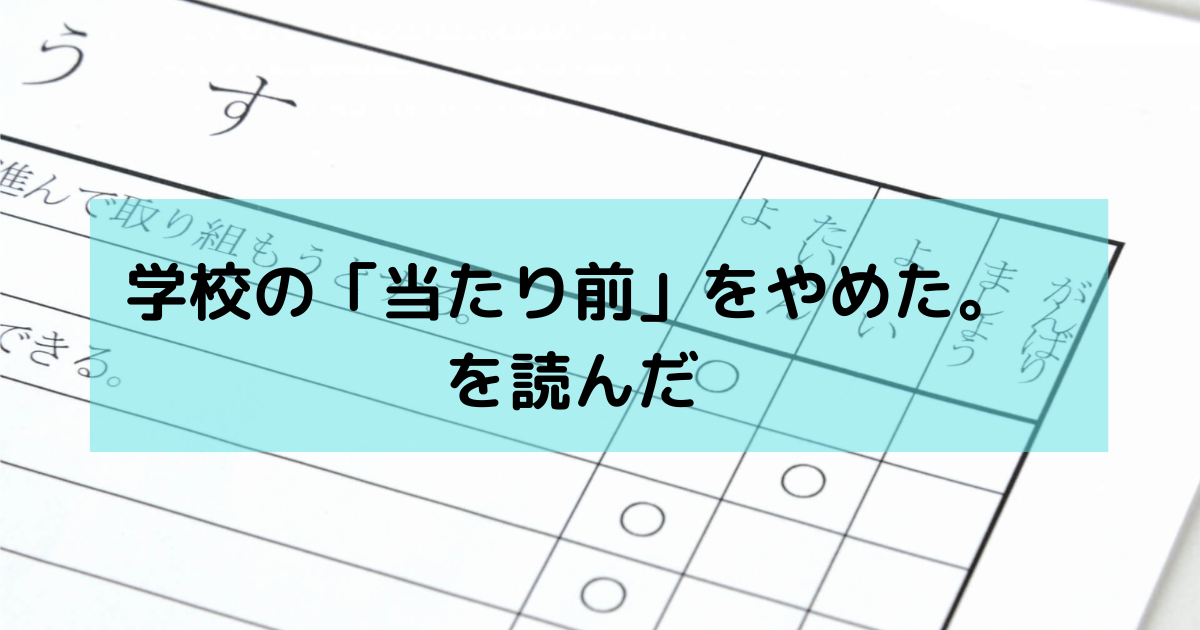
1学期が終わり、次女が通知簿をもらって帰ってきました。4年生の1学期、次女は本当に勉強を頑張ったと思います。僕の中では、次女の通知簿はオール「よく出来る」です。
次女の学校の通知簿は3段階評価です。「頑張ろう」「できる」「よく出来る」。「できる」は普通という感じがします。次女の通知簿は、「よく出来る」ではなく、「できる」が多かった。先生に惜しいと言われる。
僕は娘を決して通知簿で評価していませんが、この通知簿に納得はいかなかった。ほとんどのテストで、100点や100点に近い点数をとってきている次女。テストが全てではないのはわかるけど、惜しいって何?もっと透明性が欲しい。
- 今の小学校は相対評価ではなく、絶対評価になっているのではないのか?
- 絶対評価なら、「よく出来る」をつけてやってもいいんじゃないのか?
- 100点じゃないと「よく出来る」にならないのか?
僕はもやもやしていました。
そんな時、学校の「当たり前」をやめた。を読みたくなりました。宿題や、定期テストを廃止!革命的な公立中学校としてテレビでも話題になった麹町中学の校長先生・工藤勇一氏の著書です。今回はその書評です。
- 今の学校教育に疑問を持っている人
- 未来の学校教育について関心がある人
- 工藤勇一氏の革新的な学校改革を知りたい人
本書と著者のプロフィール
工藤勇一氏
1960年山形県鶴岡市生まれ。東京理科大学理学部応用数学科卒。山形県公立中学校教員、東京都公立中学校教員、東京都教育委員会、目黒区教育委員会、新宿区教育委員会教育指導課長などを経て、2014年から千代田区立麹町中学校長。教育再生実行会議委員、経済産業省「未来の教室」とEd Tech研究会委員等、公職を歴任(著書発行時)
本書の要点ポイント(書評)
宿題は必要ない。クラス担任は廃止。中間・期末テストも廃止。公立の名門中学・麹町中学に赴任した校長先生である工藤勇一氏がやってのけた大改革。
本書は、工藤氏が学校の当たり前、宿題や中間期末テストをなぜ廃止したのか、その理由や意味、そして工藤氏が目指す教育とは何か、麹町中学で取り組んでいる事を書いた同氏の初の著書になります。(工藤氏は現在、横浜創英中学・高等学校校長)
↓麹町中学のホームページ
↓横浜創英中学・高等学校校のホームページ
学校の本来の目的とは何か?
学校の本来の目的とは何か?工藤氏は、人が「社会の中でよりよく生きていけるようにすること」だとおっしゃっています。
しかし今の学校は、手段が目的化してしまっている。本来、子ども達に必要な力を身につけさせるための「手段」であるはずの学習指導要領や教科書が「目的」となり、ただ消化しているだけになっている。
工藤氏は著書の中で、目的と手段をとり違えないことを何度も強調されていて、学校で当たり前とされてきた事を疑い、改革をされています。
僕からも言わしてもらえば、多くの学校は「大学受験」を目的にしてしまっている。
子どもは、大学に受かった途端、目的を失って、勉強をしなくなる。親も、子どもの「学歴」に一喜一憂してしまう。学歴だけでは社会の中でよりよく生きていけないのに、です。
こういった学校の当たり前、常識が本当に子どものためになっているのか?それを真剣に考えさせてくれたのが本書です。
宿題が、子どもの評価のためのものになっている。だから廃止
宿題の本来の目的って何だろう?宿題は、わからない問題を解るようにするのが目的で出ているもの。
しかし工藤氏は、
「宿題」を出すのは子どもたちの関心・意欲・態度を測り、評価(通知表)の資料とするためではないですか?もっと私たちは専門性を発揮しないといけない
といい、宿題をただ子ども達の評価の基準にしているだけだと全廃に踏み切りました。
僕自身は宿題は必要だと思うのですが、今まではただ意味もなく「宿題をしなさい」と子ども達に強要していたように思います。
それでは当然、子どもの勉強に対する興味関心を惹きつけることはできないな、なぜ宿題って出ているのか?、なぜ勉強しないといけないのか?、その意味、目的を考えて親も子どもに語りかけないといけないなと思いました。
定期考査時点での評価に意味はない
次に定期考査の廃止について。
テストの目的は、学力の定着を図ること。学力をある時点(中間や期末)できりとって評価して何の意味があるのか?と工藤氏はいいます。定期考査こそ、学校が子ども達を評価(通知簿)する為のものになっている。だから全廃に踏み切った。
工藤氏は中間テストや期末テストは廃止する代わりに小テストを増やしている。単元毎に細かく定着度を図るようにしたという事ですね。
↓ 定期テスト廃止の動き。麹町中学の取り組みが広がっている
僕はこの考え方は素晴らしいと思います。
僕なりにイメージしてみたのですが、水泳教室の級のような考え方なのかな?と思いました。
水泳はそれぞれ泳げるための課題毎に級がわかれていて、それを完璧にクリアして初めて上の級に上がれる。もちろんこれだと生徒によって進度が異なるので、実際には一斉授業の学校では難しいのだけれど、工藤氏が考えていることってこういう事なんじゃないかな。
全員「通知簿5」で何がいけないのか?
生徒によって進度は違えど、単元テストに何度も再チャレンジし確実に習得すれば、全員に通知簿5をあげてもいい。それでも学校の通知簿で全員が5になることはまずないと工藤氏はいいます。
ここで僕が疑問に思っていたことが出てきます。「なぜ全員通知簿5ではいけないのか?」
学校の通知簿は、2000年頃から、「相対評価」から「絶対評価」に変わっているはずです。なのに全員が5にならない。教育委員会からNGが出るのだといいます。
↓学校の絶対評価については下記記事を参考にさせていただきました
内申点や、高校の推薦入試が影響しているのではないかと工藤氏はおっしゃっていますが、それが理由なら本当に学校の推薦入試制度は止めた方がいい。
いつまでたっても、テストや受験が目的ゴールになって、ゴールしたら勉強しない子どもたちばかりになる。そう思えてなりません。
麹中アフタースクールがすごい
本書には工藤氏がやり遂げた改革が他にもたくさん書いてあります。その中でも僕が印象に残ったのが麹中アフタースクールです。
放課後に「麹中塾」を開講。大学生が勉強を教えにきてくれるというもので、他の部活も含めて、放課後、外部指導にきてもらっているといいます。
単純に公立中学で放課後、塾まで開講してくれる事自体を羨ましいと思うかもしれないけど、それ以上に大学生が子どもたちのロールモデルになってくれることが、この麹中アフタースクールの最大の魅力であると思いましたし、それこそが工藤氏の狙いであることは本書を読んでわかりました。
ロールモデルとは、子ども達よりやや年齢が高い身近な尊敬できる存在であり、子ども達が、「この人みたいになりたい」と思える存在のことです。
これは深谷圭助氏の著書「子どもが自ら考え、動き出す。学ぶ環境のつくり方」でおっしゃっていたメンター制度の考え方と同じであり、僕自身が子ども達の人生において、親ではない尊敬できる存在との出会いが大事だと考えているのとも同じです。
対立があって当たり前という考え方
本書で僕がもうひとつ印象に残っているのが、「意見の対立はあって当たり前だ」という話です。
工藤氏は、学校の目的は、人が「社会の中でよりよく生きていけるようにすること」だとおっしゃいました。
社会に出れば人それぞれ意見が違うのは当たり前で、ましてやグローバル社会、諸外国の考え方や習慣は日本人とは違う。それをどうまとめて解決していくのか?その能力が今問われている。
ブルーハーツの甲本ヒロト氏の言葉がここで思い出されます。
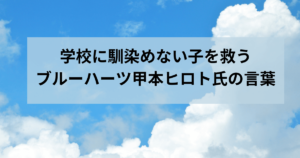
甲本氏は、学校のクラスメートの事を、電車に例え、同級生といっても、偶然同じ車両にのっているだけだといいます。その上で
喧嘩せず自分が降りる駅まで平和に乗ってられなきゃダメじゃない?その訓練じゃないか、学校は。
とおっしゃっている。
社会に出れば当たり前のように、意見が違って当たり前な状況に出会うけど、自分と意見が違うからといって、いじめや喧嘩ばかりしていても問題は解決できない。
それを自分たちで解決していく力を養う場所が学校なんだなというのも本書で学ばせていただいた気がします。
まとめ。やっぱり小学生は褒めて伸ばしてやりたい
僕が本書を読みたくなったのは、次女の通知簿に納得がいかなかった。その想いは、ただ親のわがままなのかを確かめたかったからです。
でも本書を読んで本当に救われた気持ちになりました。
僕は本当に小学生の通知簿はテストの結果プラスαの絶対評価でお願いしたいと思っています。思考力やら判断力やら、主体性やら難しいことはいわず、多少、甘めでも子どもの頑張りを褒めて、褒めて、褒めてやって欲しい。
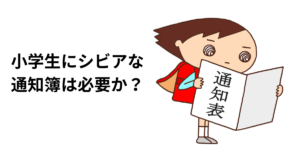
細かいことは言わず、小学生の頃は、「たくさん単元をクリアしたね!」「よく頑張ったね!」と褒めてやってほしい。そしたらまた頑張ろう!って思うのが小学生じゃないでしょうか?先生に褒められたら、勉強がもっと好きになるかもしれない。小学生こそ、通知簿は全員5(よく出来た)であってもいいと僕は思うのです。
今回の通知表を見て僕は次女に
パパの中ではオール「よく出来た」だと伝えました。3年の時より勉強を頑張った。パパはそれを見ていたし、努力の結果もちゃんと出ている。
子どもが頑張った事を親が純粋に評価してやらないでどうする?僕のそんな想いを感じ取ってくれたのか次女には笑顔が。僕の胸は熱くなりました。
学校教育改革について学びたい方は

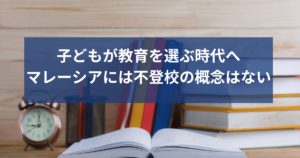

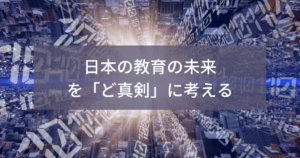

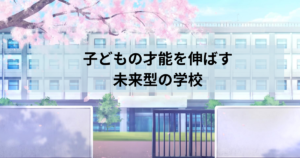
大学入試改革について学びたい方におすすめ本