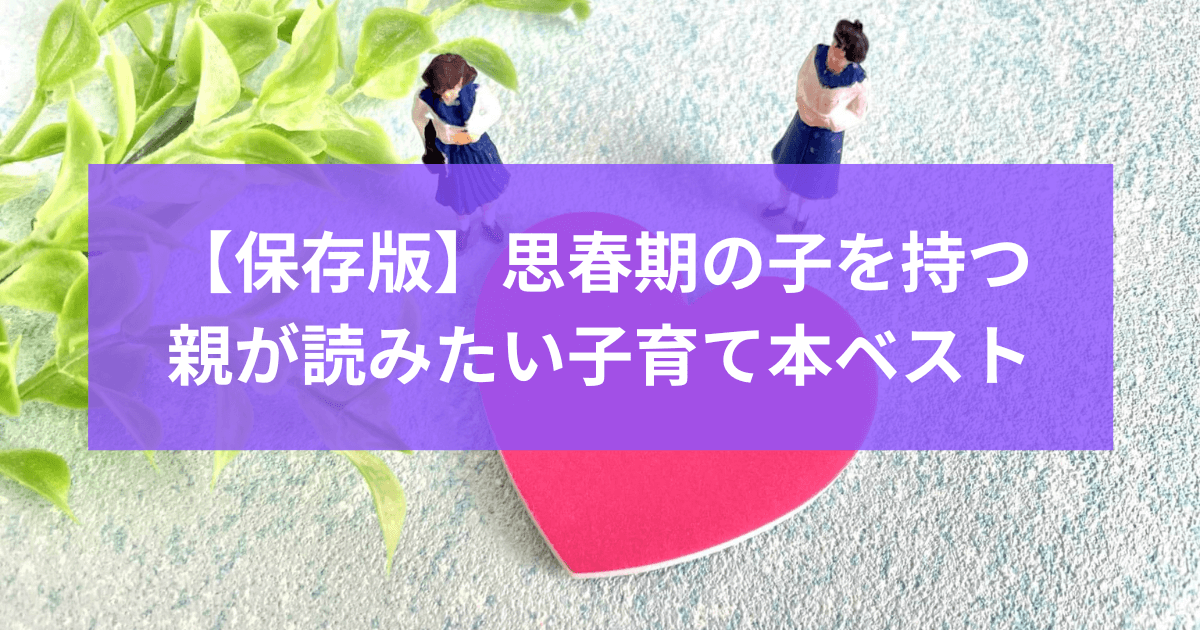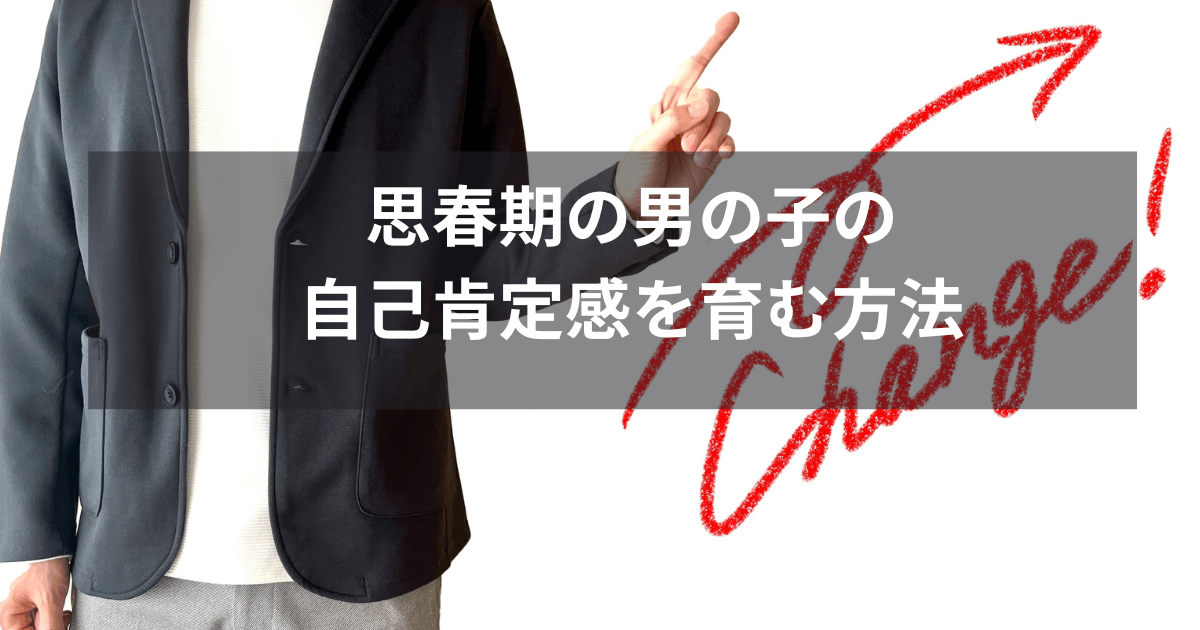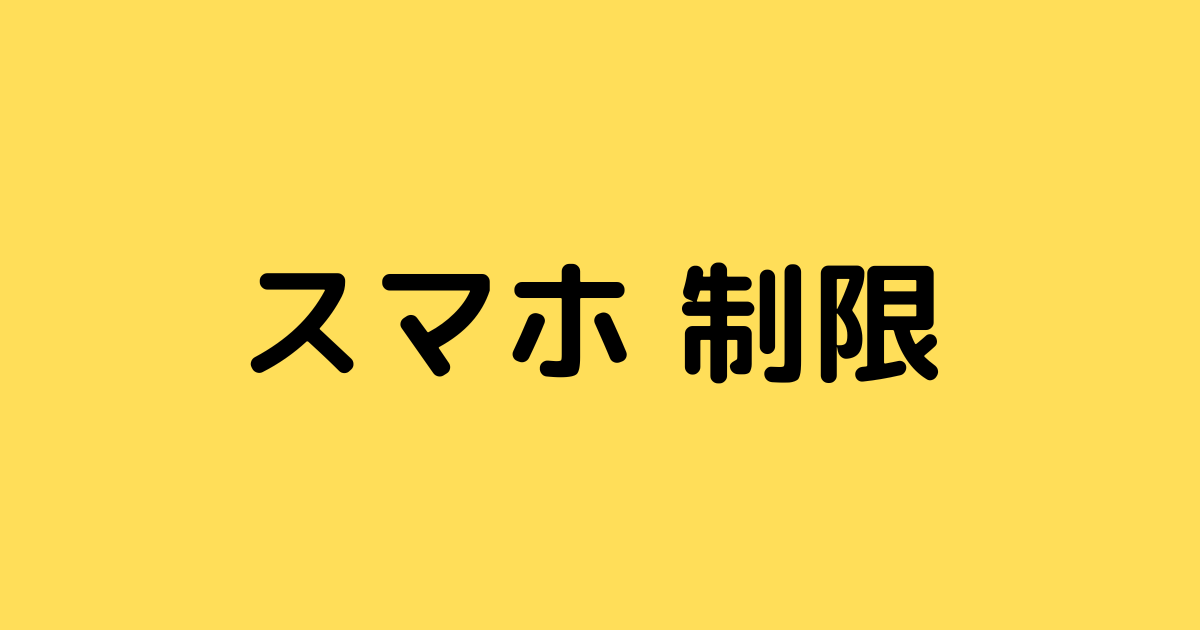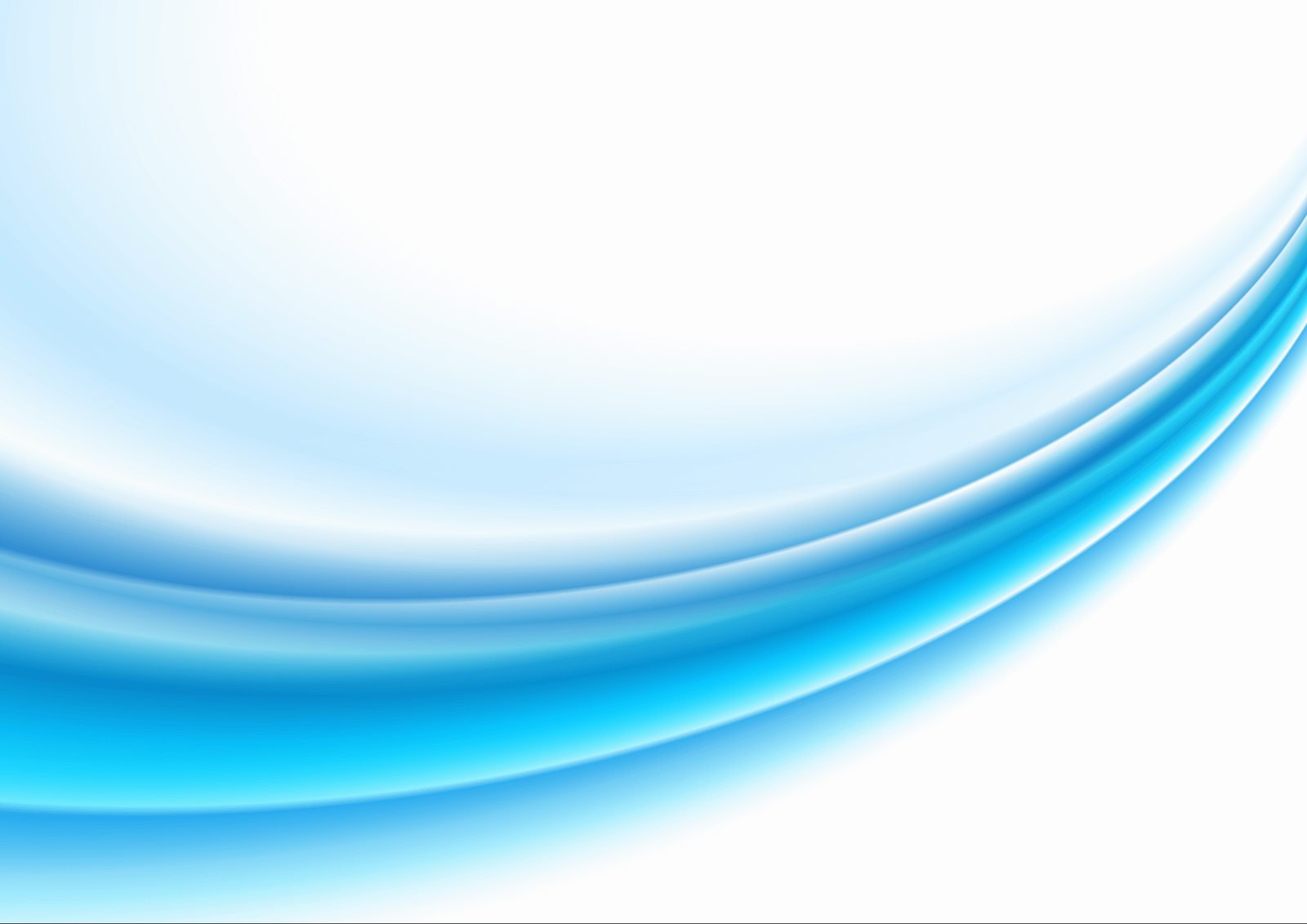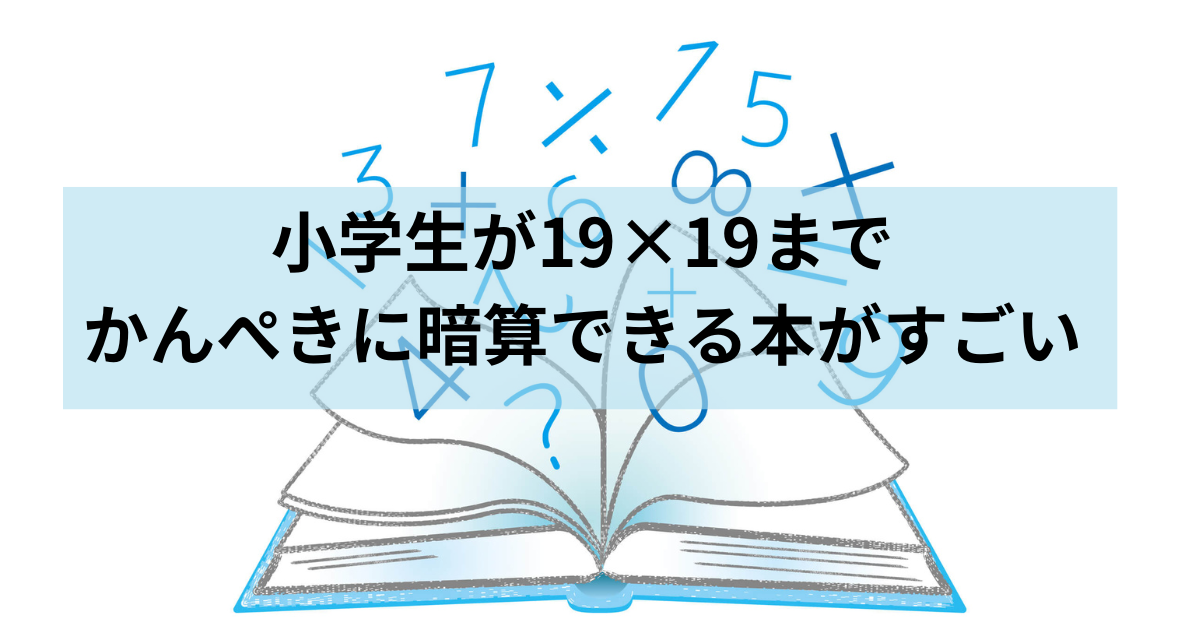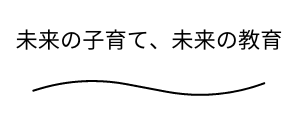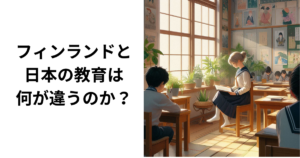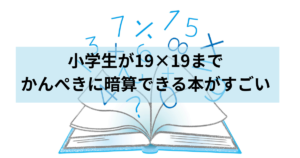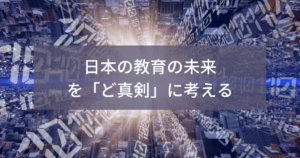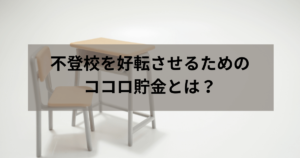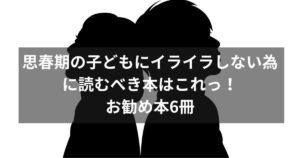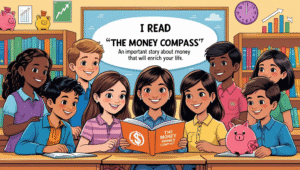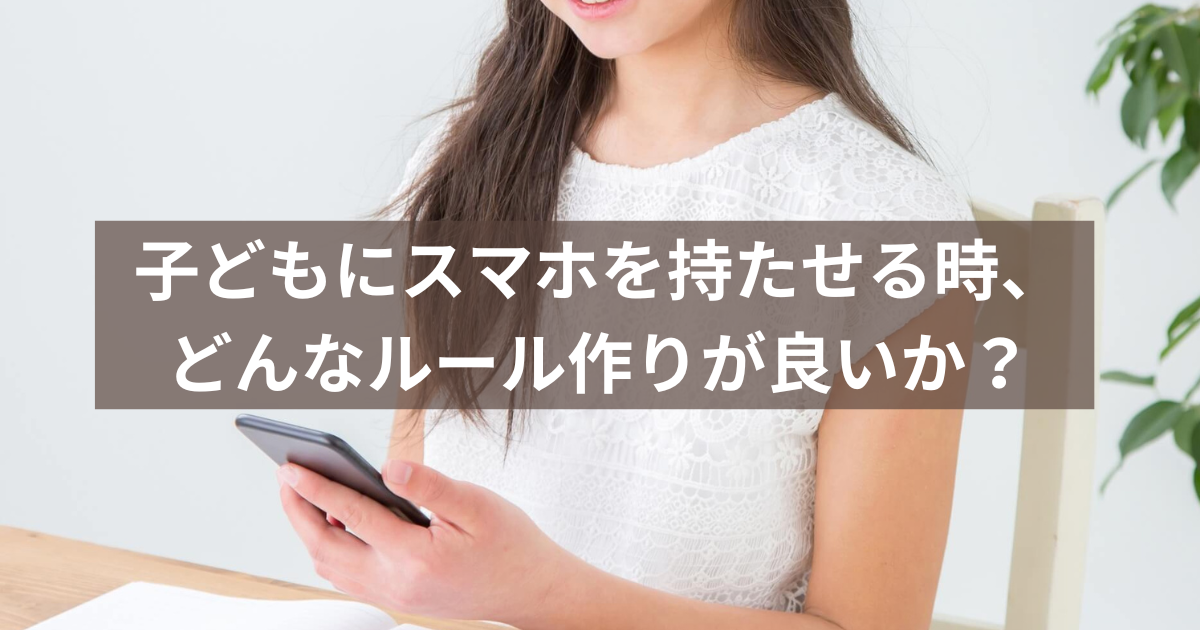
子どものスマホ中毒に悩んでいる親御さんは多いのではないでしょうか?
小学生のうちは、子どもも素直で親の言う事をよく聞きます。親がダメといえば、それで済んでいたことが、中学生になって、そうもいかないことに戸惑う親は多いと思いますし、準備もしていない親も多いと思います。
「学校の皆がスマホを持っている。スマホが欲しい。」
そう言われて、何も準備もないまま、子どもにスマホを持たせたはいいけれど、一日中スマホばかり。そればかりか学校の成績も落ちる。
なんてケースは結構あるあるだと思います。
実は僕も子どものスマホ問題に悩んだ一人ですが、今は悟りを開いたというか、段々、子どものスマホやゲームについて理解ができてきたと思っています。
↓ 我が家のスマホ制限の最終回答

子どものスマホルールは、ご家庭によって違うのは当たり前だと思うのですが、スマホを持たせる前に読んでおいて損はないなと思う本があったので、紹介しておきたいなと思います。
その上で、僕の経験も交えてどんなスマホのルール決めがよいかを述べてみたいと思います。
今回の教材と著者のプロフィール
石田 勝紀氏
一般社団法人 教育デザインラボ代表理事。1968年横浜生まれ。20歳で学習塾を創業。これまで4000人以上の生徒を直接指導。講演会、セミナーを含めると5万人以上にのぼる。「日本から勉強嫌いな子をひとり残らずなくしたい」という志のもと、Mama Cafe
の運営、執筆、講演活動を精力的に行っている。
学びポイント(書評)
スマホを持たせる前のルール決めは大事!
本書のタイトルにもなっていますが、著者は、スマホを持たせる前のルール作りが大切だと指摘したうえで、厳しいルールを作るのではなくて、細かいルールを作ることが大事だと説いておられます。
我が家もスマホを持たせる時のルールは決めてありました。1日何時間までとか、夜何時までとか簡単なものでした。ですが、子どもの行動によってルールを変えたり追加したりして、子どもがイライラすることがありました。
親の都合でルールを追加したり変更したりする。それでは、子どもが不満を持つのも無理はありませんね。
なので、スマホを持たせる前にルールは大雑把ではなくて、細かく綿密に作る。これっ、経験上、本当に大事な事だと思います。
スマホを持ったから勉強しなくなるわけではない。子どもを信頼したルール作りを
スマホを持つと勉強しなくなる。本書では、これには全く相関性がないことを、文科省の全国学力・学習状況調査*1を引用、平成19年と令和元年を比べて平日の家庭学習の時間に差がない事を用いて説明されています。
スマホを持った途端、スマホにハマり、ゲームにハマり、LINEにハマり、結果、勉強しなくなる。みんなそう思うかもしれないんですけど、決してそうとはいいきれないです。
僕も経験上、子どもがスマホをもったから勉強しないといういう相関は今のところ、認められないといえます。
確かにスマホ時間は多くなり、一時期は、子どものスマホ時間を厳しく制限しようと動きました。ですが、最近は子どもを信頼し、スマホについては何も言わなくなりました。
例えば、1日1時間制限しているとして、友だちともう少しLINEで話す必要性があって、もう30分利用時間増やしてといわれたとします。そんな場合
「〇〇(子どもの名前)を信用しているから、いいよ」
といって、言われた時間だけ、利用時間を増やしています。ですが、それで子どもがずるずるスマホにはまって、勉強をしなくなったということは今のところありません。
むしろ、スマホを厳しく制限していた時よりも、子どもが自分で制限し、むしろ勉強するようになったんじゃないかなと思うくらいです。
ただですね、環境が大事かもしれないとは思います。
長女は私立中学にいっていて、周りがみんなやっぱり勉強しているんですね。だからスマホばかりしている子って、あまりいないんです。
僕は、外部環境が子どもに大きく影響を与えると思っている人なので、まわりがスマホばかりしている子ばかりの環境なら、やっぱり著者のいうとおり、スマホルールはより明確にしておく必要はあるかなと思います。
スマホルールを子どもに決めさせる意味
スマホを買ってやるときが、親が唯一有利になれるときだ。と著者はいうのですが、これは名言ではないかなと思いました(笑)確かにスマホを買ってやるときは、子も素直で「勉強頑張ります!」って感じになる(笑)
で、親が有利なのだから、親がルールを決めたらいいんだと思いがちなんですが、
子どもがまずルールを考える。子どもの意見を聞いたうえで、親が意見をいう。この順番でルールを構築していうというのが著者の考え方でした。
難しいことかもしれないですけど、これは本当に効果があると思います。
親が一方的に決めたルールを守れなかった場合、
- 「親が決めたからうまくいかなかった。」
- 「こんなルール守れない。」
と人(親)のせいにする。そうならない為にも、子どもが自分で決めて納得したルールであることが大事なんですね。
子育てにおいて、自己決定権を育むことは、スマホだけでなく大事なことですし、ルールに自分の意見を採り入れてもらえる、親に信頼されている気持ちは、自己肯定感にも繋がります。
ただし、ルールは必ず破られるとも著者はいいます(苦笑)
その時のために、ルールを破ったペナルティーはきちんと決めておくのだそうです。自分が納得して決めたルールですから、破ったらペナルティー。納得せざるを得ないですね。
社会に出ればルールの中で子どもも生きていくわけですから、きっといい練習にはなると思います。
スマホゲームも悪ばかりではない。デジタルリテラシーがあがる利点もある。
スマホ脳*2というベストセラー本があり、スマホは脳を中毒にするという話があります。スマホ脳はぜひ読んでおいた方がいいと思うのですが、著者は、それでも多くの子は、ゲームで脳はやられないと思っている。とおっしゃいます。
子どもが1日中ゲームばかりしている。
実はこの悩みも僕は経験したことがあります。当初はイライラしましたし、スマホ中毒を心配しました。
ですが、小言をいうのを我慢して、思い切って、スマホの使い方を子どもに任せてみたら、長女はゲームの時間が減ったんですね。
それどころか、分からない事があったら、それを放っておかず、ネットで調べる癖がついているのがいいなって思っていて、デジタルリテラシーもあがっていると思うんですよね。
次女はまだスマホを持たせてませんが、ゲームは持っていて結構やりますが、ゲームを一緒に楽しむようにして、ゲームの楽しさを理解してやるようにしてみたんです。
次女が遊んでいるゲームは、「マイクラ」*3、今は「あつ森」ですが、一緒に遊んでみると、いずれも勉強にも繋がる良質のゲームコンテンツだということがわかりました。
↓この2つのゲームソフトは、僕は良質のコンテンツだと思う
「あつ森」では、魚を集めることができるですが、どんな季節にどんな魚が採れるのか、その魚にはどんな特徴があるのかがわかったり、本当に勉強になる。
学校の授業が、「あつ森」のようなコンテンツなら、きっとみんな勉強するだろうなって思ったし、もう少し「あつ森」のように、学校の授業も工夫できないのかなって思いました。
だから、必ずしもスマホやゲーム=悪ではない。これは子どもと一緒にゲームをしたから分かったことです。
「ゲームって勉強になるな」と声をかけるととても嬉しそうに、色々教えてくれますし、YOUTUBEを使って、「あつ森」の事をとことん調べている姿をみて、
「1つの事を一生懸命、探究するのはいいね。」
というと、すごく誇らしげな顔をします。
先入観を捨てて、子どもを理解する努力をしたら、我が家はいい方向に向かったと思っています。デジタルも、コンテンツの質と使い方なんだと思います。そのことも考慮しながら、ルール作りができればいいなと思う。
僕が唯一、厳しめにルール決めしたいなと思う事
今まで説明してきたとおり、僕は割りとスマホに寛容であり、ルールも厳しくはないです。ですが1点だけルールを厳しめに課していることがあります。
それは、子どもの体の事を考えての使用制限です。長くスマホを使い続けると目が悪くなる。深夜までやると、体を壊す。
だから
「ゲームを長時間したら目が悪くなるから、30分毎に一度休憩やで。」
とか、
「深夜まで起きていると体調を壊すから、夜は11時までに制限しておくよ。」
とか。
本当に子どもの体の事が心配なので、そのことは伝えて、使用制限しています。それなら子どもも納得してくれて、制限を守ってくれています。「30分毎」とか、「11時まで」とか、具体的な数字を入れるとより効果的かなと思います。*4
スマホを厳しく制限したところで、子どものやる気に親の影響はなし。それよりも子どもを信頼したルール作りを
「やる気」の半分は遺伝で決まり、後は外部環境。親の影響はほとんどないと、最近僕が勉強している、行動遺伝学*5の双子研究の話が本書でも紹介されています。
つまり、スマホばかりしてるからといって、親がガミガミ言っても、それによって子どもが勉強をやる気になったり、成績があがったりはしないという事。
僕は本当、行動遺伝学を知ってから、子育てが楽に感じるようになりました。ガミガミ言うよりも、子どもを信頼してやること、それから子どもに決定権を持たせてやることで、自己肯定感や、自己決定感を育むことを大切にしていきたい。そういう意識で、スマホのルール決めもしています。
今のところですが、こちらの方がずっと子どもにいい影響を与えていると思っています。