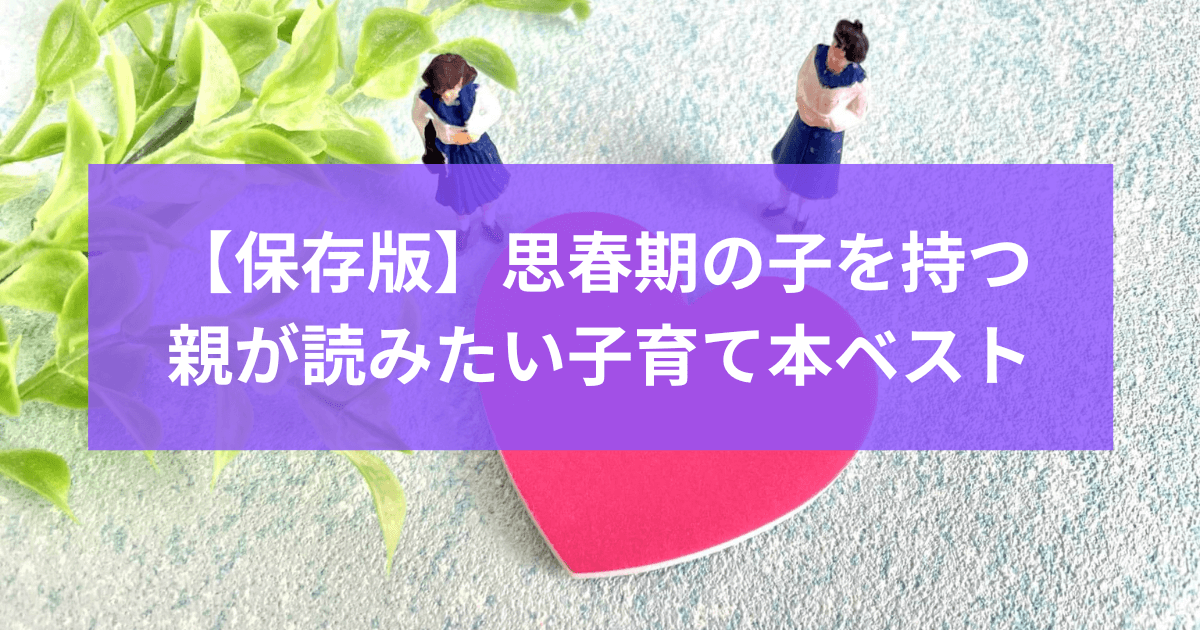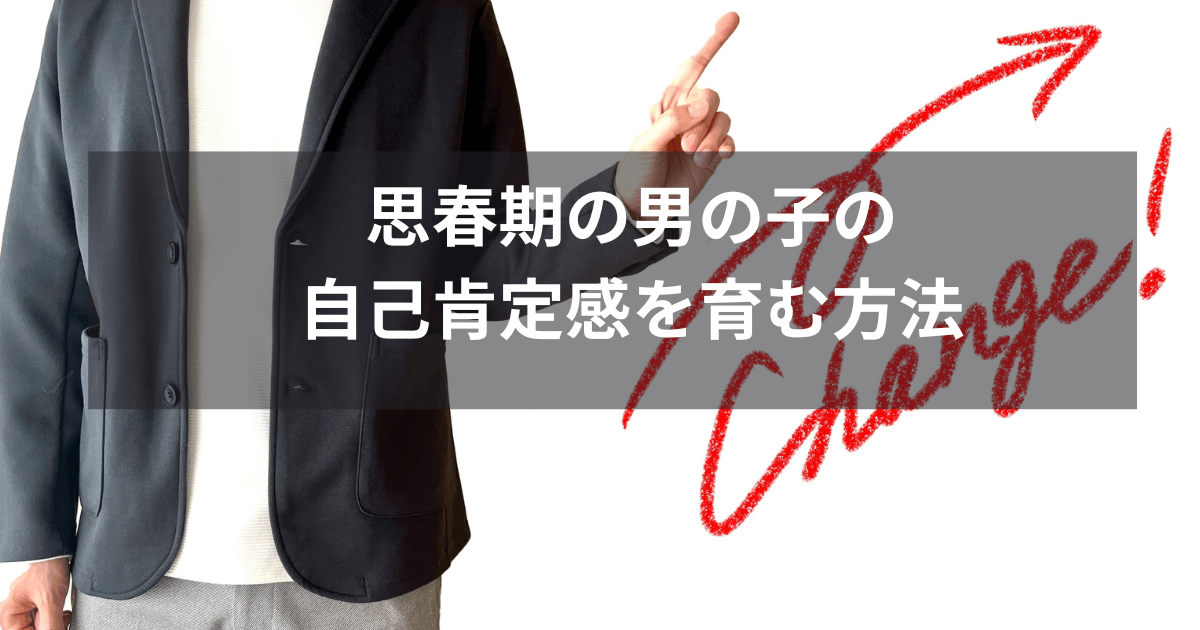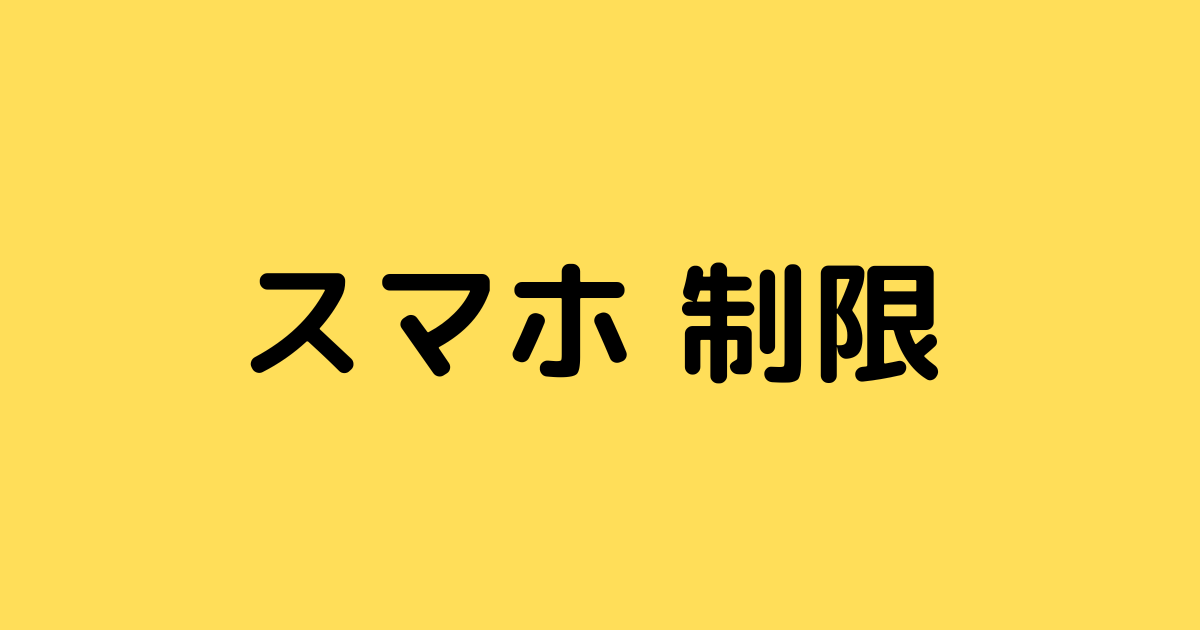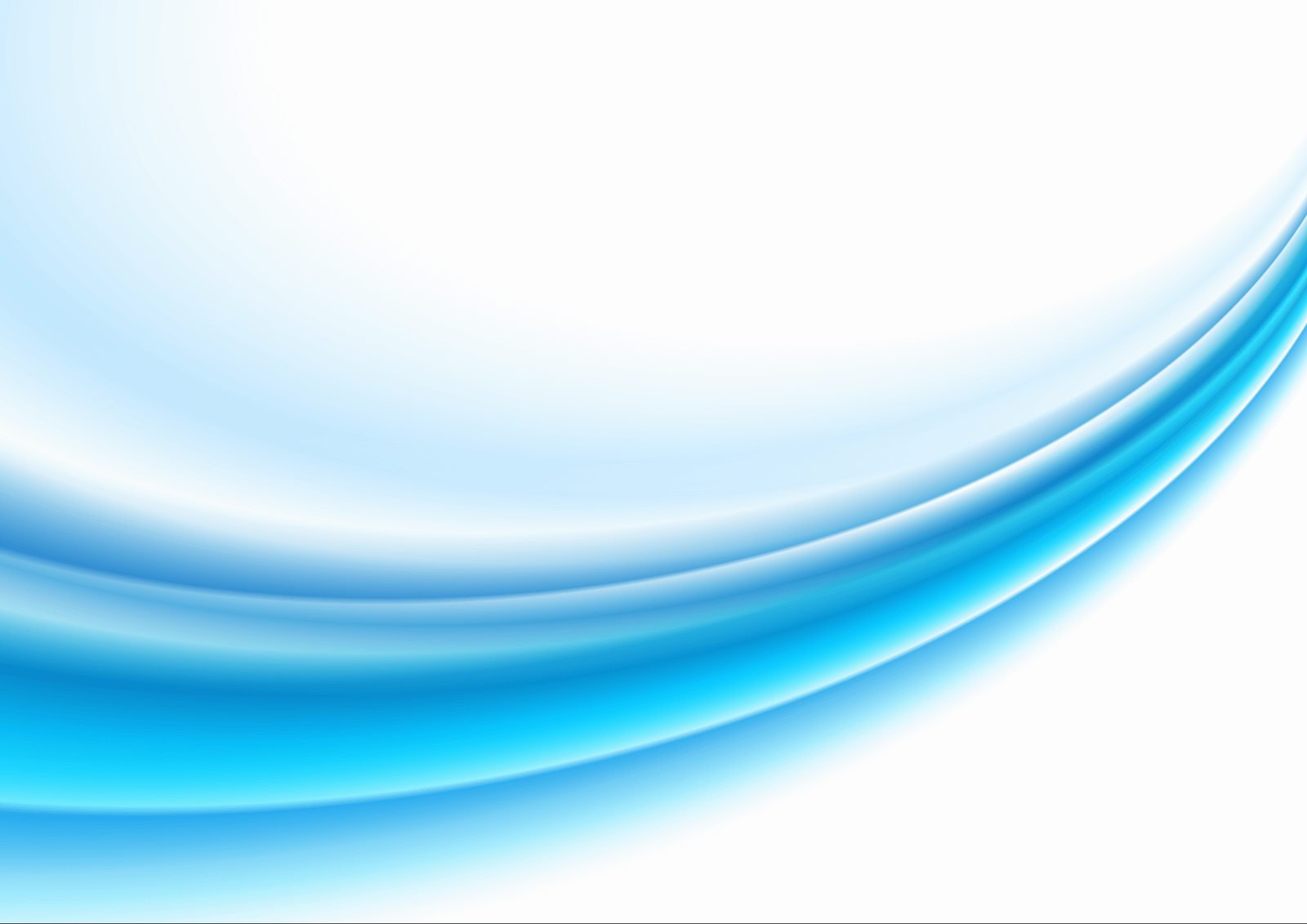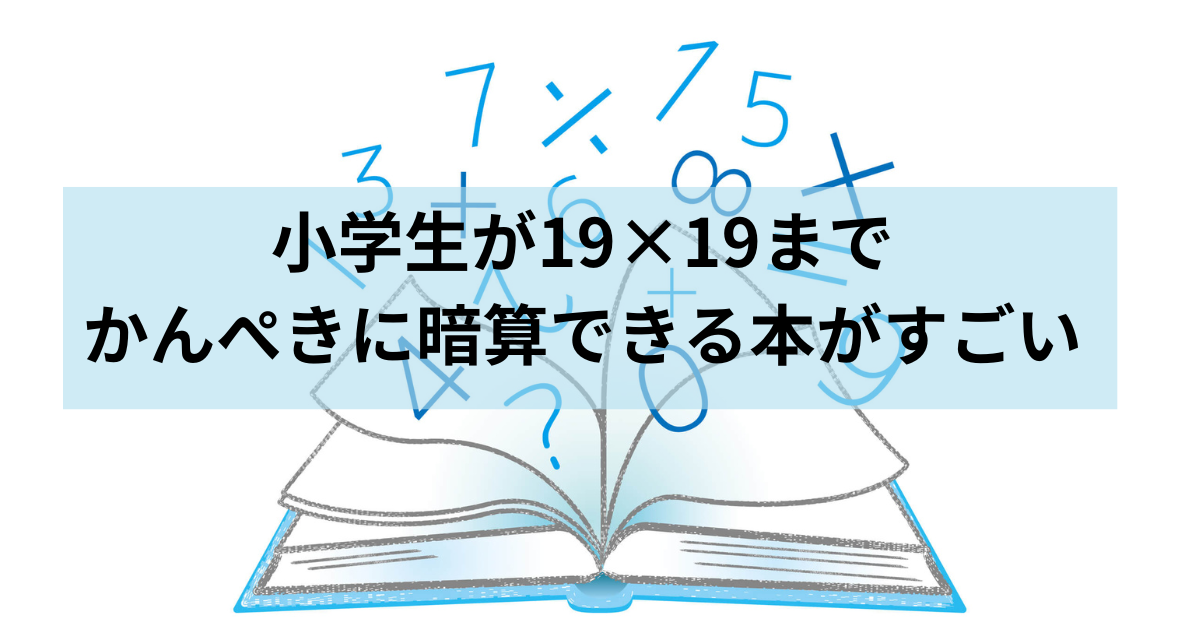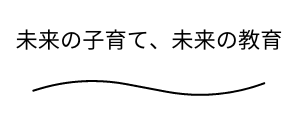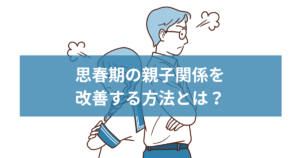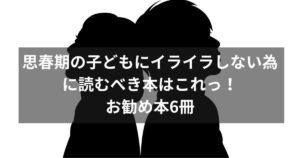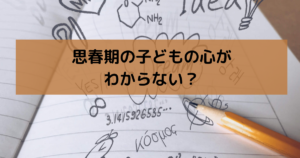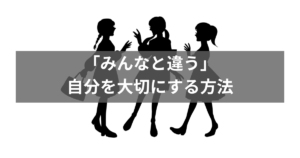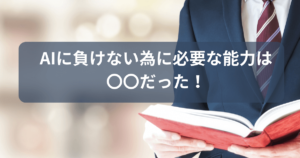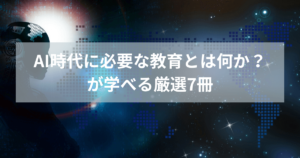お金の話を今のうちに子どもにしておきたいなとずっと思っていました。
- お金を貯金ばかりする子ではなくて、自分に投資できる子になってほしい
- でも、無駄遣いをする子には育ってほしくない
- 簡単に借金をする子に育ってほしくない
これが僕のお金に関する価値観であり、子どもに教育したい内容です。ですが、これを論理的に伝えることは結構、難しいなと思っていました。
そこで、子どもにお金のことをわかりやすく説明できる本を探していたのですが、今までなかなか良書に巡り合うことができませんでした。
ですが、やっと見つけましたよ!「いま君に伝えたいお金の話」という本です。
2024/2/11追記
もう一冊、お金の良書を見つけました。きみのお金は誰のため。お金と経済が学べる小説です。
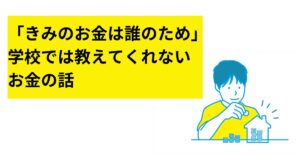


くろちゃんパパ
- 思春期の娘二人(小学生、中学生)のパパ。
- 子育て本、教育本を100冊以上読む。
- 娘が生まれた時からずっと子育てに関わり、娘たちと今も良好な関係を築く。
- 長女の中学受験の勉強に毎日付き合い、中高一貫校の合格を親子で勝ち取る。
- 勉強だけで優劣が決まる今の教育に疑問をもち、未来型の教育に関心を持ち勉強中。
本書と著者のプロフィール
村上 世彰氏
投資家。1959年大阪府生まれ。1983年通産省(現・経産省)に入省。国家公務員としてコーポレートガバナンスの普及に従事する。独立後、1999年から2006年まで投資ファンドを運営。現在、シンガポール在住。
村上 世彰氏が教えてくれる。お金の本質
村上 世彰氏のことを皆さんは覚えていらっしゃいますか?村上ファンド。いわゆる「もの言う株主」として世間で注目を浴びていた方ですね。その歯に衣着せぬ言動から、村上氏のイメージは、「お金第一主義」そんなイメージや誤解を世間ではもたれていたかもしれません。
それが最近は中学校や高校でお金の授業をされているという話を聞いて、僕がイメージしている村上氏とはずいぶんイメージが違うなと少し気になっていました。N高等学校の投資部の顧問になられているのは有名な話ですね。
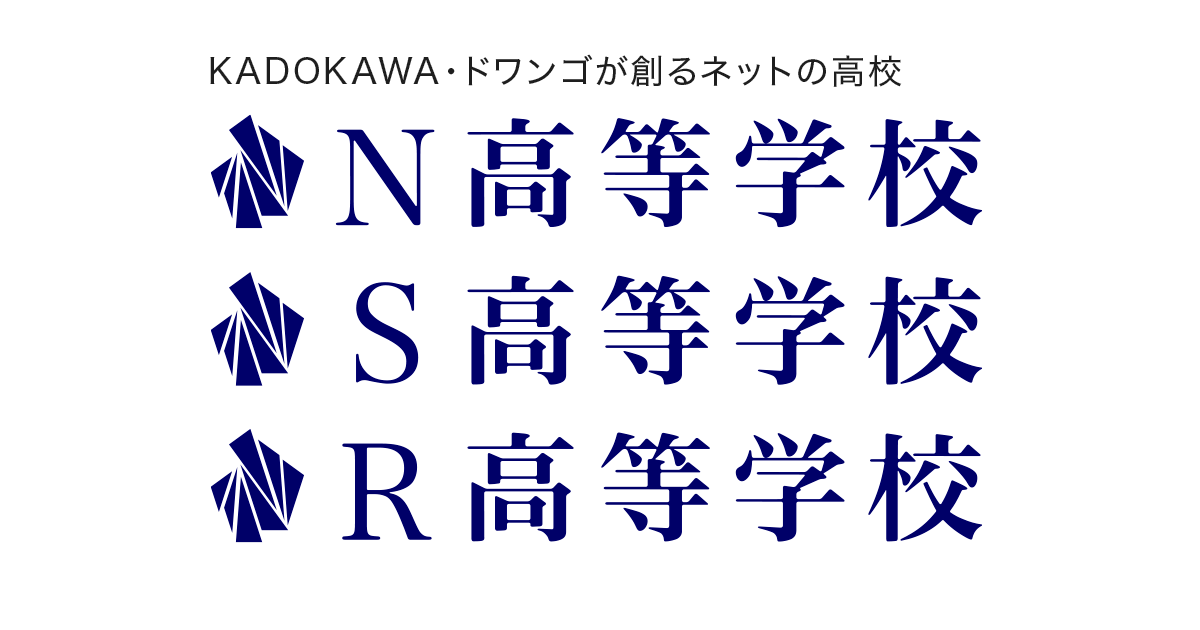
そんな折、見つけたのが、村上氏の著書「いま君に伝えたいお金の話」という本です。本書は、中学生、高校生に向けて書かれた本ですが、お金のプロである村上氏の教え方は、さすが最高にうまいと思いました。そして子どもに向けて、とっても優しく語りかけていらっしゃるのが印象的です。
欲しいものが何でも手に入る時代のお金
今の子ども達にとってお金ってどんなイメージがあるでしょう?飽食の時代、自分がそんなにお金に執着しなくても、欲しいものが簡単に手に入るかな。だとしたら、お金に貪欲ではない子のほうが多いのではないでしょうか?
「お金より大切なものがある」「お金、お金って汚い」そんな風に思う子もいるかもしれません。恥ずかしながら僕の子ども時代がそうでした。ですが、大人になればお金が大事なんだと痛感する時がくるんですね。だから僕はなおさら今のうちに子どもにお金とどう付き合っていくべきかを子どもに教えておきたかったのです。
お金ってなんだろう?
お金はもともとは物々交換の道具であったといいます。お金がない時代、魚と肉を交換するようなことをしていて、これを物々交換といいますが、交換できるものがない時の代わりとして、お金は生まれたといわれています。(諸説あります)こういう時にお金があると便利です。
つまり、お金というものは本来、自分が欲しいものと交換するための「便利な道具」なんだということです。
僕たちは、「将来が不安」、「老後が不安」などの理由でお金を貯めるのだけれど、ただ貯めるだけでは、お金の価値ってないんだなと気付きます。
お金は悪いものではない。扱い方が問題
お金、お金というと、お金に汚い人だな~と言われることもあります。ですが、お金を扱う人や扱い方に問題があるのであって、お金が決して悪いわけではない。お金の事をよく知らないで大人になると「お金の魔力に支配される」と著者はいいますが、本当にお金に汚い人間になってしまいます。
自分たちの子どもをそうは育てたくない。
- お金持ちのほうが偉い
- 何でも値段が高いものの方がよい
など、値段だけで価値を判断してしまうとお金に縛られた生き方になる。お金に縛られない生き方をするためには、お金とは違う基準を自分の中で作ることが大事だと著者はいいます。
お金は物々交換の道具であるといいました。自分が本当に価値があると思うものに、自分の幸せの基準に沿って、お金は使うもの。
その感覚を子どもたちに磨いてほしいなと思いました。
値段が高いからサンマが美味しいとは限らない
モノの値段は、季節、作られる場所、使う素材、人々の関心など、あらゆる要素が組み合わさって決定されるもの。
とりわけ値決めで重要になってくるのが需要と供給の関係です。
著書では、サンマを例にわかりやすく需要と供給で値段が決まることを説明してくれています。
太ったサンマが100円で、痩せたサンマが300円!
これは100円だったサンマが不漁のために300円になることがある。でも値段が高いからといって、この高いサンマが美味しいかというと決してそうではない。
不漁で採れなくなったサンマは、たいして美味しくもないのに、希少価値があがり値段は高騰。こういった事でも値段はあがる。これが需要と供給の関係です。
お金の勉強として、値段って欲しい人と提供する人のバランスで決まるんだ~ということを子どもが学ぶことができるのも、村上氏の著書ならではですね。
お金は回すもの。銀行に預けてもお金が減る意味
著者は、お金は回すものだとおっしゃっています。日本経済が停滞しているのは日本人はお金をため込んで回せていないのが原因ではないかとおっしゃっています。
特に子ども達の時代は、終身雇用で退職金をたくさんもらえる時代ではありません。今後、子ども達の世代はきっとお金を株などで運用して増やさなければならない。
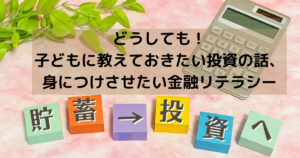
今年から高校の家庭科の授業で投資の勉強がはじまるそうですが、お金を増やす方法を勉強するという事は、そういう意味だと思います。
「株にはリスクが大きいから運用が怖い。。。」古い考え方ならこうですね。
ですが、銀行にお金を預けていても、お金が減ることがあると著者はいいます。
「えっ!、銀行にお金を預けていたら安全ではないの?!」とびっくりするわけですが、
50年前250円で食べられていたラーメンが、今500円になっているとすれば、インフレが起こって、100万円の貯金があったとしてその価値は、その半分の50万円になっているということ。
これが金利がほとんどつかない銀行にお金を預けていてもお金は減るということですが、村上氏ならではの視点で、これを読んだ子どもはきっと衝撃を受けるだろうなと感心しました。
まとめ。お金は汚いものではない事を教える事が大切
子どもの頃は、親に守られている。お金は親が出している。家庭が裕福であればあるほどお金のありがたみがそれほどわからないかもしれません。
加えて漫画やドラマで、お金を持っている人が悪者になっているシーンなんかを見ると、世の中お金が全てではない!とお金の本質を見失ってしまう可能性もあります。
お金の本質を知ることがとても大切だと思います。そしてお金って決して汚いものではないということを僕たちは上手に子ども達に伝えなければいけないなって思いました。
そういう意味で、本書はとてもわかりやすくお金の本質を教えてくれます。
最後に。
著者は、お金に強くなるということは数字に強くなることだともいえるとおっしゃっています。著者は子どもたちを集めて家でよく数字のゲームをされていたそうです。
その数字に強くなるゲームがいくつか紹介されているのですが、「31ゲーム」の話が面白かったです。この話を子どもにすると食いついてきたので最後に紹介しておきます。
二人で1から31までの数字を言い合うのですが、31を言った方が負けという単純なゲームです。ですが、このゲーム、数字に強い人なら絶対に勝てる方法があるんですって!みなさんご存じですか?学校や家でも使えるゲームです。
よかったら、本書を読んで数字に強くなってみてください^^