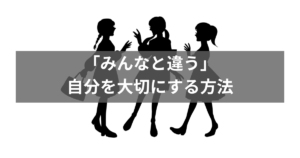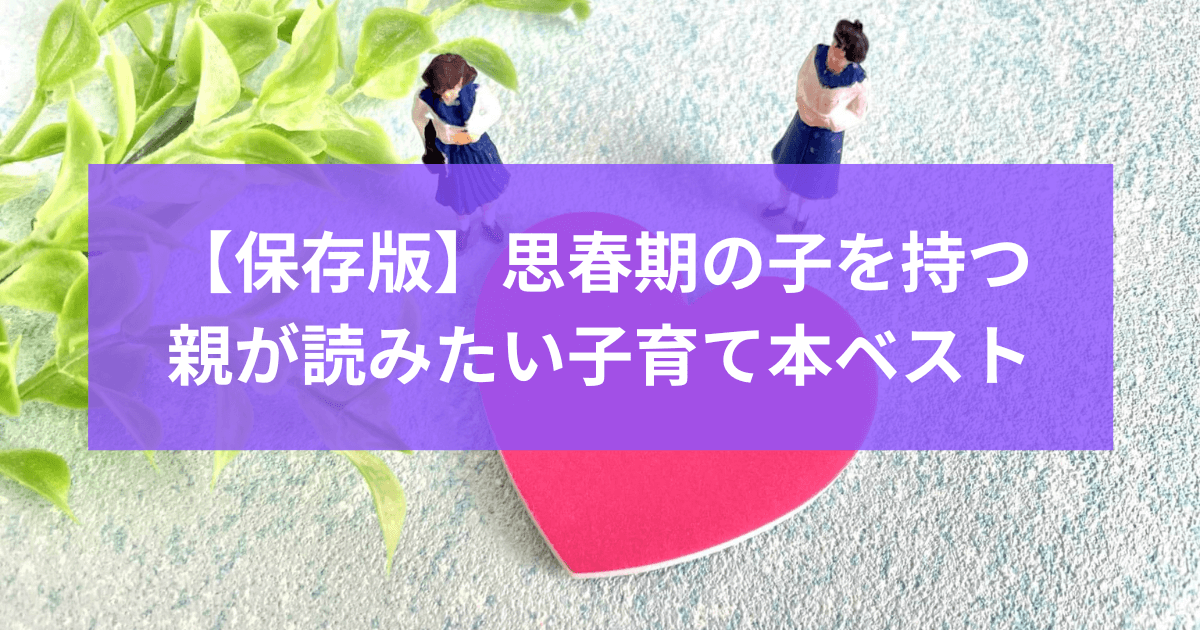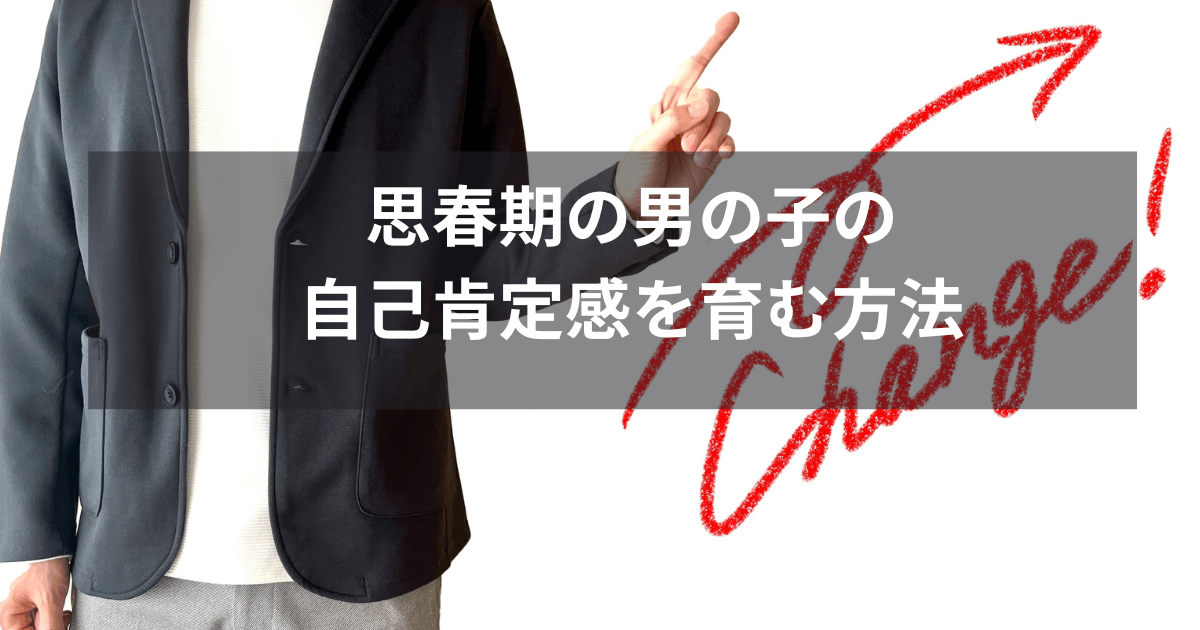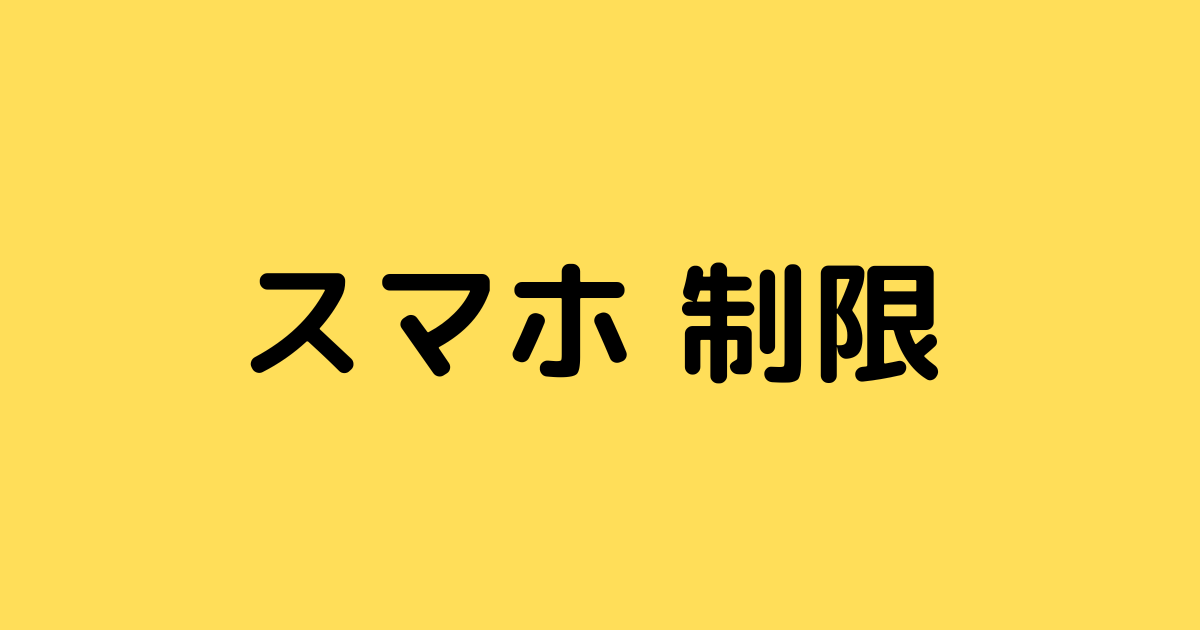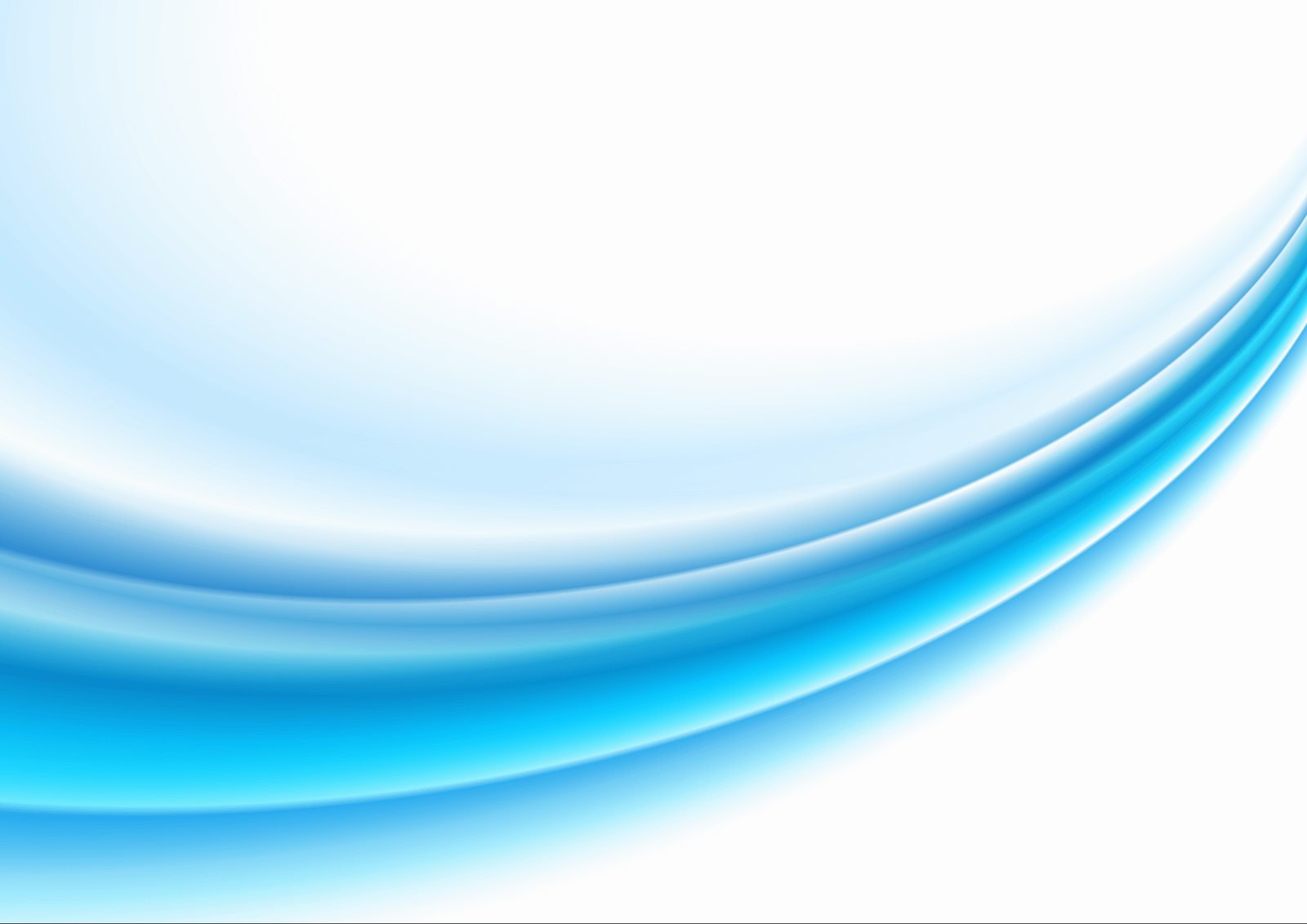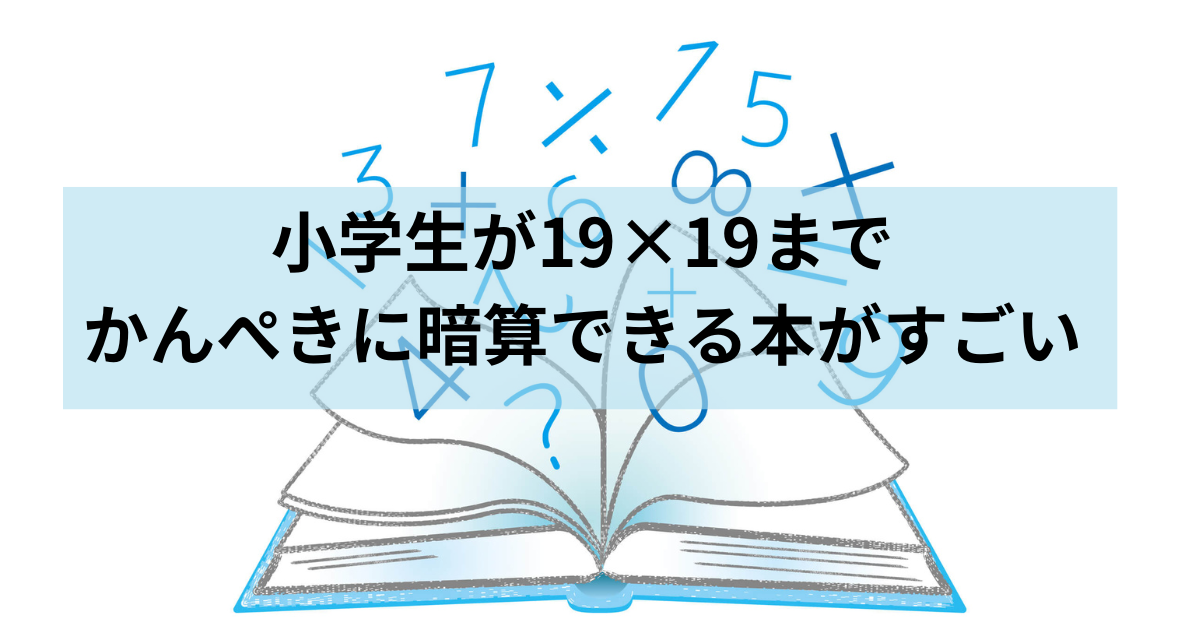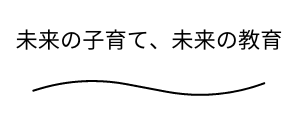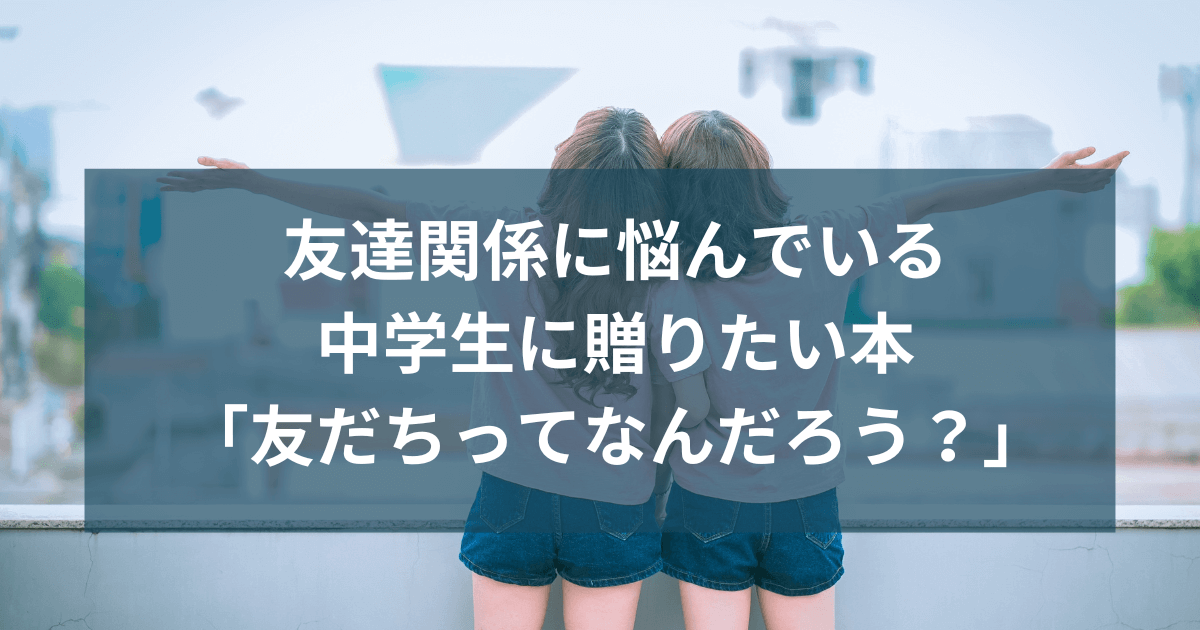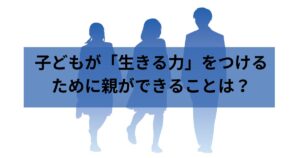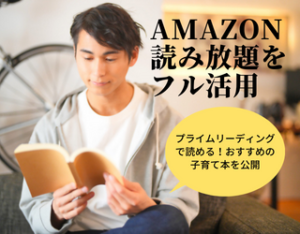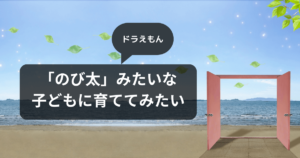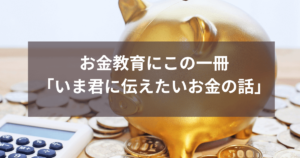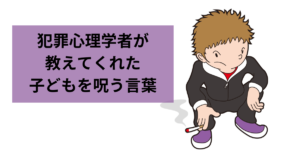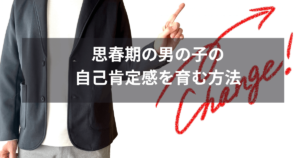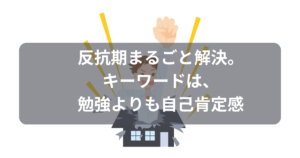僕自身、子どもの友達関係には随分悩んできました。子どもって幼い時はみんな元気で明るいもんだと思っていました。だけど、そうではない子どももいるってことを知りました。みんなが元気で楽しそうに遊んでいる中に、自分の子がなかなか入っていけない。ひとりぼっち。どうしたらいいのか?本当に悩みました。
自分のことなら自分で何とかする。できる。だけど、子どものことは子どもが自分で解決するしかない。そういう意味では、親は無力な存在です。ですが、何か手助けしてやりたい。力になってやりたい。そう思うのが親です。
- 友達関係で悩む子に何かアドバイスをしてやりたい
- ひとりでもいい。いつか友達はできる。無理に友だちを作らなくてもいいんだよと励ましてやりたい
そんな風に悩んでいる親御さんが、もしいらっしゃったら、おすすめしたい本があります。
僕が購読させていただいているはてなブロガーさん、モッピーさんがブログで紹介してくださいました
「友だちってなんだろう?」って本です。

くろちゃんパパ
- 思春期の娘二人(小学生、中学生)のパパ。
- 子育て本、教育本を100冊以上読む。
- 娘が生まれた時からずっと子育てに関わり、娘たちと今も良好な関係を築く。
- 長女の中学受験の勉強に毎日付き合い、中高一貫校の合格を親子で勝ち取る。
- 勉強だけで優劣が決まる今の教育に疑問をもち、未来型の教育に関心を持ち勉強中。
本書と著者のプロフィール
斎藤 孝氏
1960年静岡県生まれ 明治大学文学部教授。東京大学法学部卒。専門は教育学、身体論、コミュニケーション技法。ベストセラー多数。著書発行部数は1000万部を超える。NHK Eテレ「にほんごであそぼ」総合指導(著書発行時)
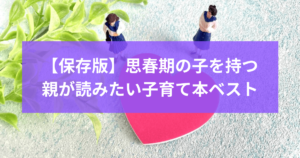
友達とはなにか?本質を考えると人間関係が楽になる
友達付き合いを楽にする、人に頼りきらない関係とは?
友達付き合いを無敵にする3つの力があるといいます。
- 気の合う友達を作る力
- 気に合わない相手ともうまく付き合う力
- ひとりを楽しめる力
二つの対人関係(1と2)に加えて、ひとりを楽しむ力(3)を持つことで、人に頼りきらない関係を築けるようになる。
本書のこの「人に頼りきらない関係」という考え方は、今友達付き合いで悩んでいる子に、きっと勇気を与えてくれると思います。
学校で子どもがひとりぼっちだと悩んでいるお子さんは
「能動的なひとりぼっち」
でしょうか?それとも
「受動的なひとりぼっち」
でしょうか?
自分の意思でひとりになっている状況なのか、それとも人との関係性のなかで、ひとりにさせられてしまっている状況なのか
引用:友だちってなんだろう?
が能動的なひとりぼっちと、受動的なひとりぼっちとの違いです。
「能動的なひとりぼっち」なら、何も悩む必要はありません。子どもが一人の時間を自分で楽しんでいるのですから、その時間はきっと子どもにとって財産になります。
例え今は「受動的なひとりぼっち」であったとしても、何でもいい。好きなことに没頭することができれば、「能動的なひとりぼっち」を楽しむことができるはずです。
本書では、あの「あいみょん」さんも学校でひとりぼっちだった、あの「星野源」さんも人間関係を築くのが苦手であった等、小学生や中学生が共感する事例をあげて、子どもたちにエールを送ってくれます。
こうした有名人の方も、ひとりの時間があったからこそ、自分の好きなことを極められたのだと想像ができますね。そう考えると独りも決して悪くない。
友達とは、自分の好きなもので繋がる
また著者の、友達の作り方や関係性についての考え方も秀逸です。
友達って「好きなもの」で繋がると、共感しやすいので作りやすいのはもちろんですが、「好きなもの」があるから、相手の人格と真っ向から向き合わなくてもよくなり、結果、穏やかな友達関係を築くことができるという考え方は新鮮でした。
逆に、こうした共通した「好きなもの」がなく、なんとなく集まってできたグループは、同じ行動をとらないというだけで人を非難したり、排除したりする可能性があることを指摘し、ただつるむだけの友達ならあえて作らなくてよいと著者はいいます。
なるほど~。友だちってそう考えれば楽になるなって、改めて思いましたね。本書はこのように、友達関係に悩む子に随所で勇気を与えてくれます。
合わない人がいて当たり前。合わない人とどう付き合うか?
一方で
本当に大事なのは「合わない人とうまくつきあう力」
引用:友だちってなんだろう?
だといい、いずれ社会に出ていく子どもたちにあえて厳しいエールも送られています。
厳しいようですが、どこにいっても「合わない人」はいる。それを逃げてばかりでは社会ではやっていくことはできないでしょう。
学校は「人慣れ」の練習場だと著者はいいます。そういう意味では、学校は勉強をしにいくところ以上に、「人に慣れる」練習をしにいく場所なのかもしれません。
ですが、心配は無用です。大人にだって合わない人はいっぱいいます。会社を出れば、会社の人とは一切話しないという人もいっぱいいます。
大人がそうなんだから、子どもがクラスメートが友達だと思えなくても全然いいのです。「友だち幻想」という本があります。ここにもみんな仲良く、みんな友達って考え方はもはや幻想だと書いてあるのですが、多くの人の共感を得ました。
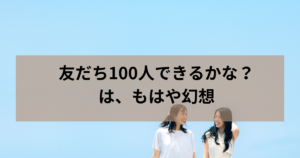
そう、友だち100人できるかな♪、みんな仲良くはもう幻想なんですね。
まとめ 学校で独りでも問題はない。あいみょんさんだって一人だった。
長女に中学受験させた一番の理由は環境を変えてやりたいと思ったから。結果、それが良い方向に向かって、今は中学でいきいきしている娘を頼もしく思っています。
ですが小学生時代は娘は娘なりに考えて人に慣れる練習を一生懸命やっていたのだと思いました。それも財産になるよと言ってやりたいし、これからの未来、もし何か友達関係で悩む事があったなら、この本で勇気やエールを送ってやりたいなと思いました。
それでも学校に友だちがいないと悩んでいる子もいると思うけど、あいみょんさんだって高校では一人だった。ブルーハーツの甲本氏も、「同じ年齢の子が集められただけで、クラスのみんなは別に友達なんかじゃないよ。」とおっしゃっているのだから、きっと大丈夫です!
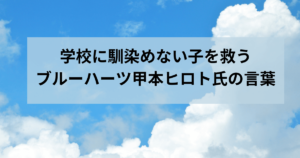
できれば、自分の支えになる何か。夢中になれる何かがあればよいと思います。学校って狭い社会です。さかなクンが著書「一魚一会」でおっしゃっていたように、「広い海」にでれば、友達はきっといつかどこかでできるはずです。
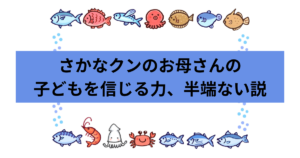
そう信じて前を向いてほしいなって思います。
友だち関係に悩んでいるなら、こちらの本もおすすめです
友だち関係に悩んでいるなら、「みんなと違う」自分を大切にする方法という本も是非一読することをおすすめします。友だち関係がうまくいかない中高生に向けて、書かれた本で、無理やり友だちを作らなくても大丈夫だよという事が書かれていて勇気がもらえます。