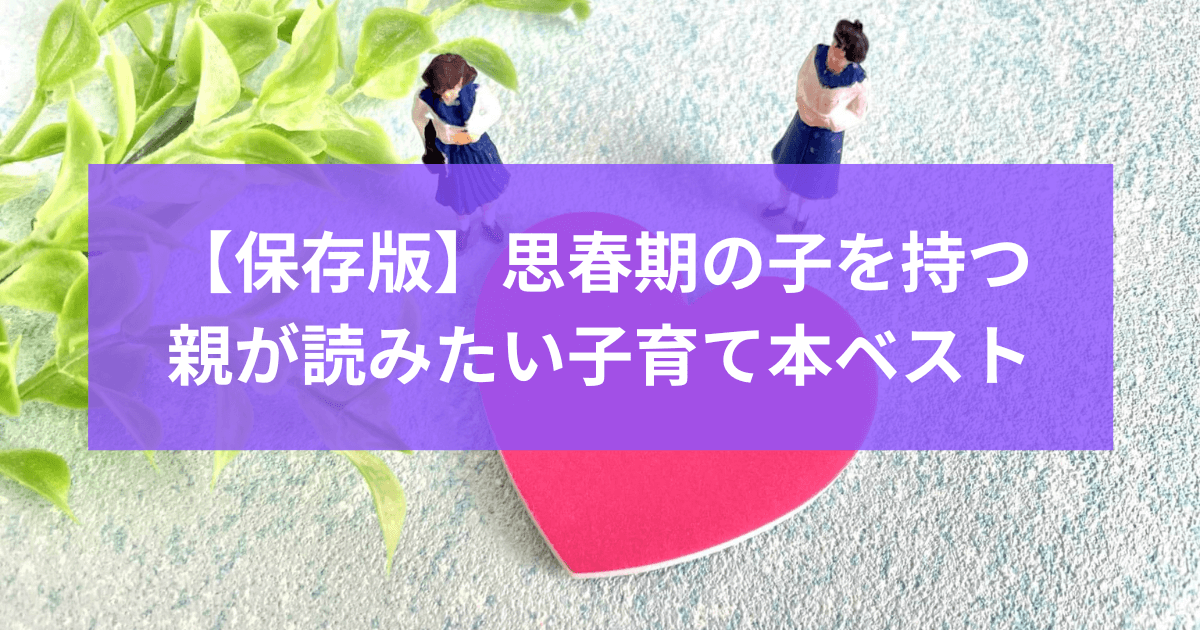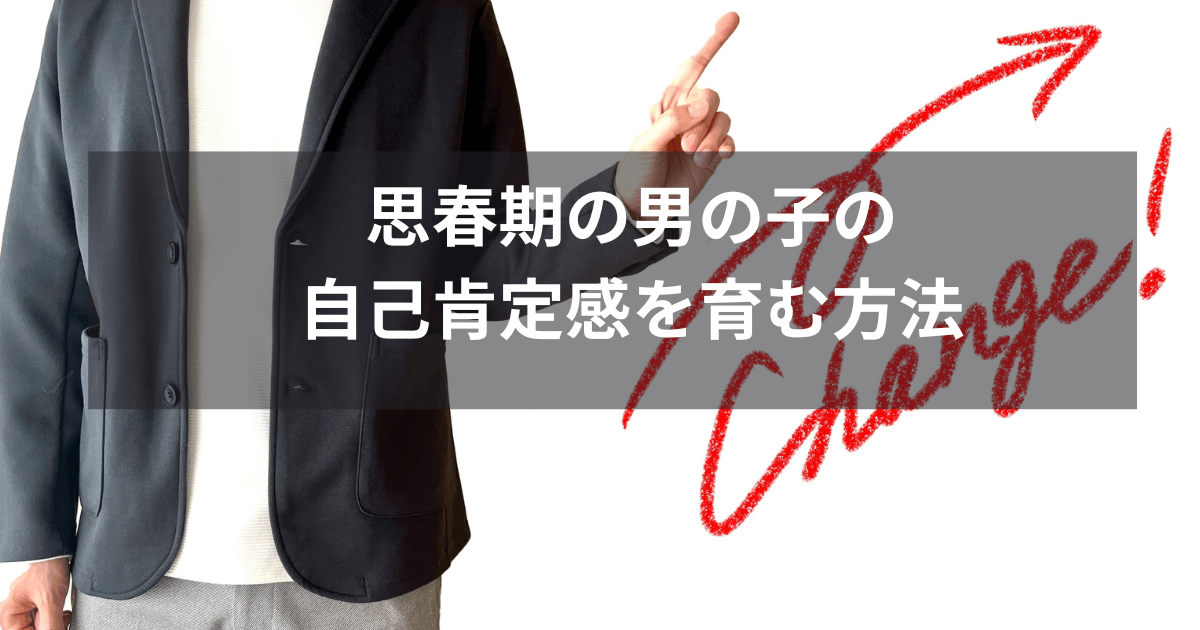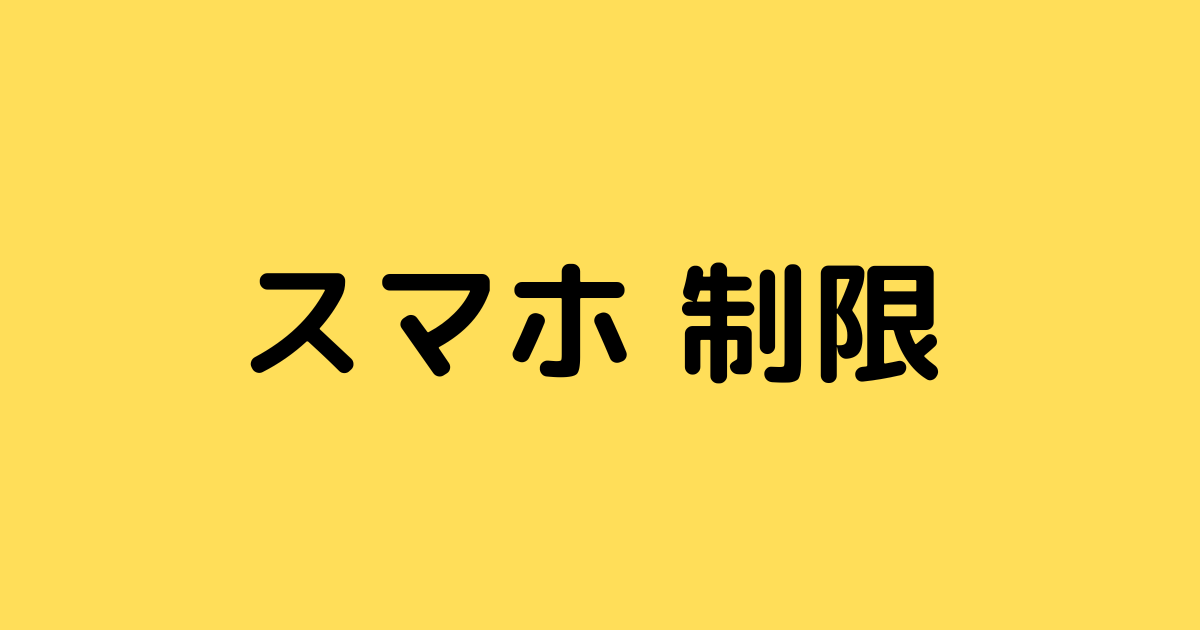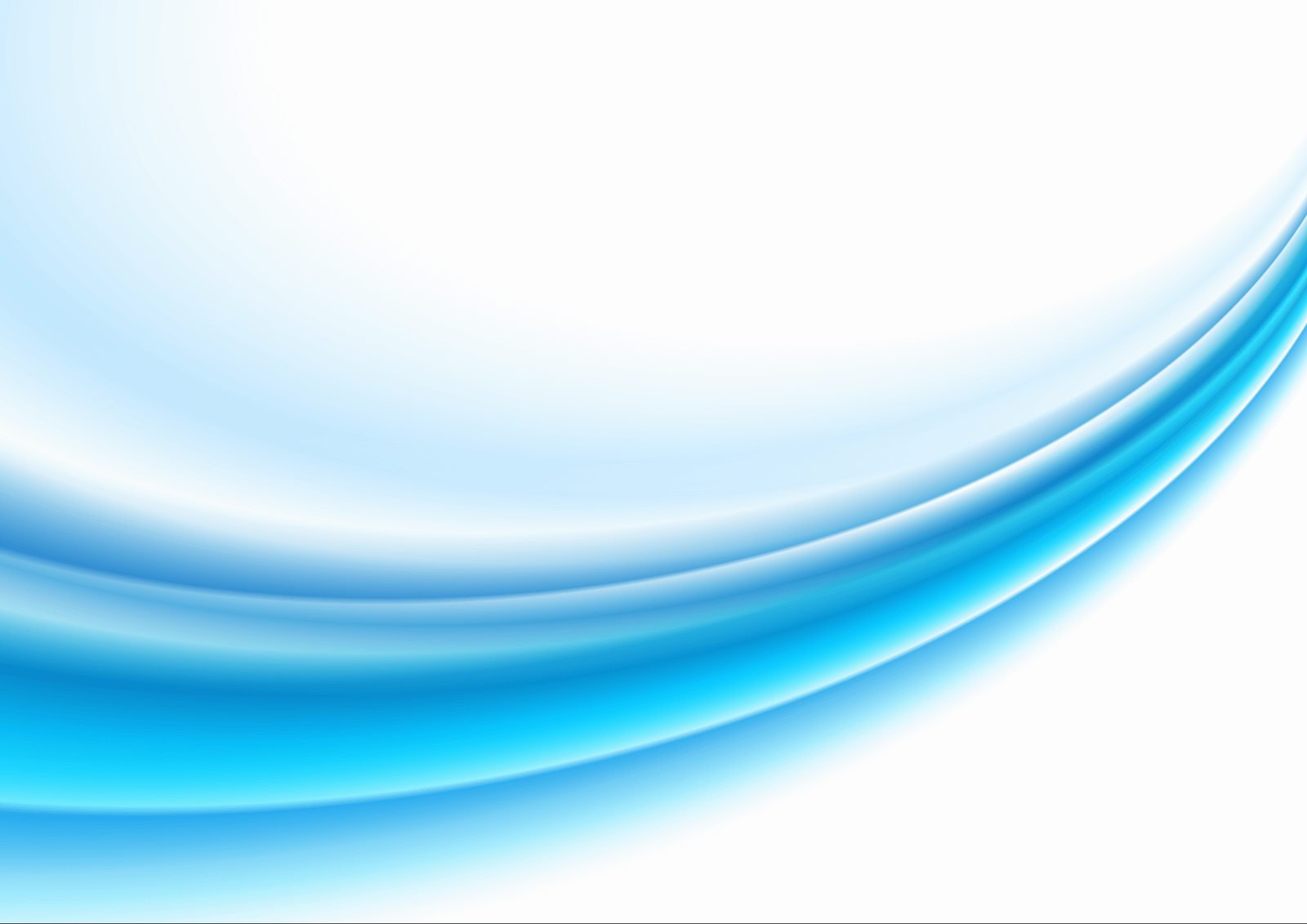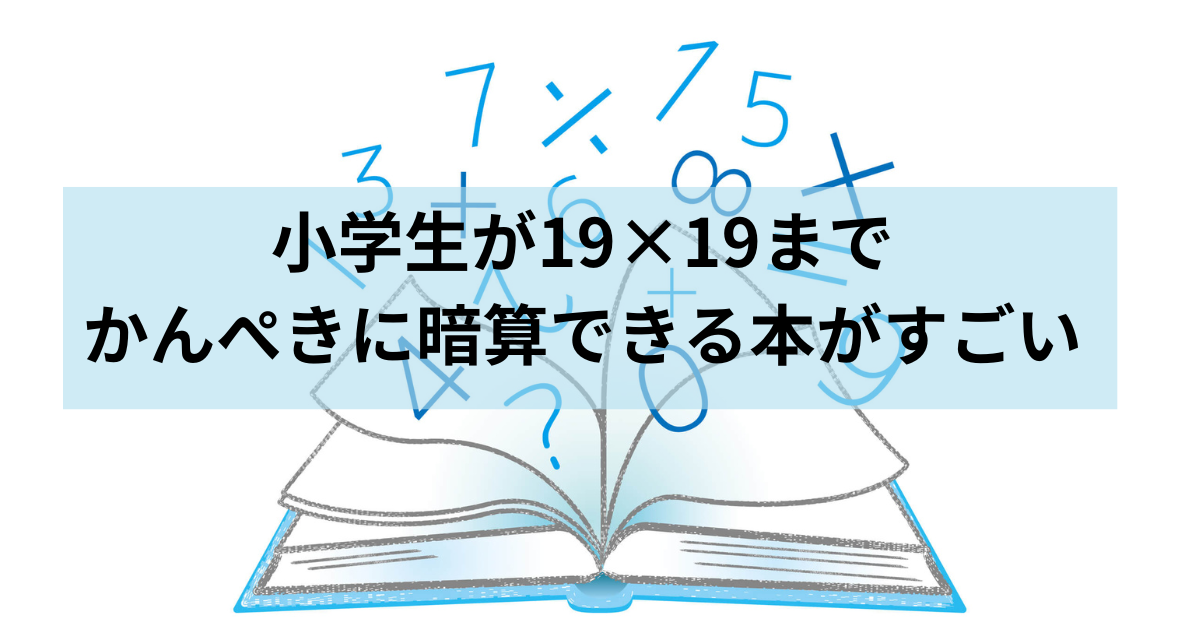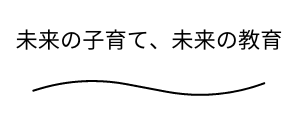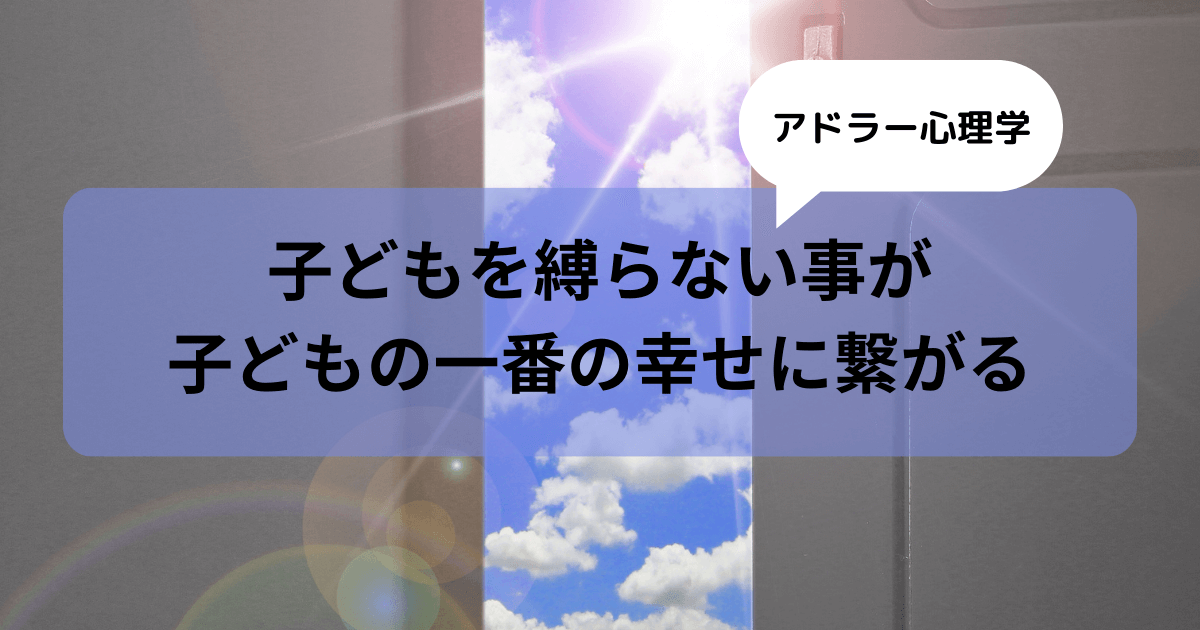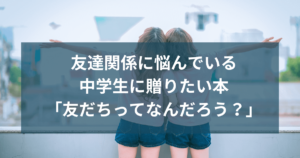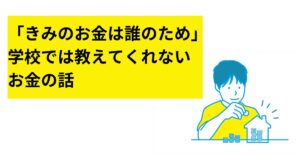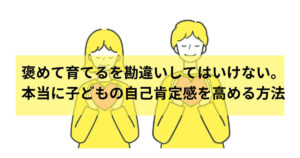思春期の子どもは、大人になる過程で、色々悩みながら成長します。それもいいと思うのですが一方で、子どもの人生に鎖をつけて、頑張れよといっているような気がして悩むときがあります。
また僕には、子どもにはこうあって欲しいという欲があり、それが子どもが思う未来と違う場合、子どもは苦しみ悩むことになる。それって子どもの幸せを本気で考えているのかと自問することがあります。子どもには子どもの進みたい道があるのです。
- 子どもには子どもの人生がある。わかっているけれど、どうしても子どもの進路に口を出してしまう。
- 親が子どもを縛っている事で、子どもの幸せになる権利を妨げているのではないか?
そんな僕のような悩みを持つ方に、ヒントをくれる本を今日は紹介したいと思います。
アドラー心理学をわかりやすく解説したベストセラー本「嫌われる勇気」という本です。

くろちゃんパパ
- 思春期の娘二人(小学生、中学生)のパパ。
- 子育て本、教育本を100冊以上読む。
- 娘が生まれた時からずっと子育てに関わり、娘たちと今も良好な関係を築く。
- 長女の中学受験の勉強に毎日付き合い、中高一貫校の合格を親子で勝ち取る。
- 勉強だけで優劣が決まる今の教育に疑問をもち、未来型の教育に関心を持ち勉強中。
本書の紹介と著者プロフィール
岸見 一郎氏
1956年、京都生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。京都教育大学教育学部、奈良女子大学文学部(哲学・古代ギリシア語)などを歴任。専門の哲学に並行してアドラー心理学を研究、精力的に執筆、講演活動を行っている。(著書発行時)
古賀 史健氏
ライター。株式会社バトンズ代表。1973年福岡県生まれ。1998年、出版社勤務を経て独立。2014年、ビジネス書ライターの地位向上に大きく寄与したとして「ビジネス書大賞・審査員特別賞」受賞。(著書発行時)
アドラー心理学を子育てに活かす考え方(書評)
アドラー心理学とは?
本書は、アドラー心理学の第一人者、岸見一郎氏とライターの古賀氏の共著で、哲学者と青年の対話物語形式にしてアドラー心理学をわかりやすく解説した入門書です。
一人の青年が、アドラー心理学の思想をもつ哲学者・哲人を論破しよう乗り込むのですが、対話の中で、アドラー心理学を深く知っていき、最後には受け入れるというストーリーになっています。
ちなみに心理学の世界では、フロイト、ユング、アドラーが三大巨匠といわれていますが、アドラーは、オーストリア出身の精神科医であり、心理学者アルフレート・アドラー氏1のことをいいます。フロイトと考え方の相違で袂を分け独自のアドラー心理学を確立したといわれています。
アドラー心理学は「勇気の心理学」ともいわれ、本書でもたびたび「勇気」という言葉が出てきます。この勇気というキーワードを心にとめながら本書を読むと、よりアドラー心理学の魅力を感じることができると思います。
ちなみに僕は本書を初めて読んだとき、よい本だな~と感銘は受けたものの、1度本を読んだだけではアドラー心理学を理解することはできませんでした。本書の中で、アドラー心理学を本当に理解して、生き方まで変わるようになるには、「それまで生きてきた年数の半分」が必要とまで書かれています。
アドラー心理学はそれほど奥が深い心理学でありますが、自分の人生観、そして子育てにもおおいに気づきを得ることができると思います。
人間の悩みは、全て対人関係のものである
アドラーは、人間の悩みは、すべて人間関係の悩みであるといいます。
このワンフレーズに僕はすごく惹きこまれました。すごく核心をついているな~と思ったのです。
自分がこれまで悩んできたことを突き詰めて考えてみると、そのほとんどが人間関係に行きつくことに気が付きます。
子育ての悩みだってそうです。子どもが学校でうまくやっていけるか心配するのは、学業の事もあるでしょうけど、大半は人間関係のことを心配しています。
アドラーのいうように、人の悩みというものは、全て人間関係なんだなと思いました。
対人関係に悩むのは、人間関係を縦に考えているからだという著者の指摘もズバリ核心をつかれました。どこかで、人は「この人は僕よりも上」、「僕よりも下」と評価している。
人には承認欲求という、他人に認めてもらいたいという欲求があります。友だちに認めてもらいたい、先生に認めてもらいたい、この承認欲求を得る為に他者を排除する争いが起こっている。これが学校で、いじめや仲間外れに繋がる。これは友だち幻想という本で学んだことですが本書を読んで納得しました。
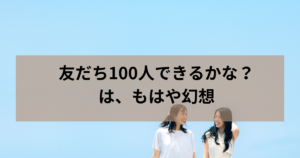
対人関係の中で競争があると、人は、対人関係の悩みから決して逃れることはできない。対人関係から解放されると人は自由になれる。すなわち、自由とは、他者から嫌われる勇気をもつことであるという著者。
この「嫌われる勇気」は本書のタイトルになっていますが、この思想は衝撃的でした。
自分に当てはめてもよくわかる。確かに、人に好かれたい、みんなに好かれたいと思って行動すればするほど、生き方は窮屈になる。人に嫌われてもいいと勇気を持つことができれば、どんなに自由に生きていけるだろうと思う。
子どもの課題に土足で踏み込まない
悩みの全ては人間関係。それは親子関係であってもです。
人間関係のトラブルはなぜ起こるのか?それは、他人の課題に土足で踏み込むことで起こり、また、自分の課題に土足で踏み込まれるから起こる。
これをアドラー心理学では「課題の分離」といって、親子であったとしても、自分の課題と他人の課題を切り離して考えなさいといいます。
例えば勉強は、あきらかに子どもの課題であります。「勉強しなさい」は、子どもの課題に対して親が明らかに土足で踏み込んでいる。だから、子どもは反発する。例え親であっても他人の課題に土足で踏み込まない。これがアドラー心理学流の考え方です。
では、勉強しない子に対して、親はどうすればよいか?勉強は「子どもの課題」であるから、親は立ち入らない。親は見守るしかないのです。
ただ応援することはできます。本書では、
馬を水辺につれていけても水を飲ませることはできない
という英国のことわざ2が何度も登場します。
子どもに環境を用意してやることはできる。けれど、その水を飲むかどうかは、子ども次第だということです。水を無理やり飲ませようと思っても、飲まないって事なんですね。
褒めるのではなく「ありがとう」
子どもへの声かけ、コミニケーション、難しいですよね。アドラー心理学で、もうひとつ面白いなと思ったのは、褒めることも叱ることもしてはいけないという思想です。
叱らない子育てっていうのは聞きますが、褒める事もしないとはあまり聞かないですよね。僕もどちらかというと子育ては褒めて伸ばす事を心がけています。
しかし、アドラー流でいえば、褒めるという行為は、上の立場のものが、下の立場のものを評価している行為であり、賞罰教育で育った子どもは、他人の評価の中で生きてしまうといいます。
「えっ!褒めたらダメなのか?だったらどう声かけするのがいいの?」となりました。
答えは、「ありがとう」とか「助かったよ」あるいは、「嬉しい」という言葉がけをするでした。「ありがとう」といわれると、自分は価値がある人間なんだと実感ができる。
僕は、どうしても子どもを褒めてしまうし、褒めてやりたいと思うのですが、それ以上に「ありがとう」を意識して使いたいと思いました。
自分は価値がある人間なんだという感覚をまず、家で感じさせてやりたい。
60点の子どもを受け入れる
最近の子育て本の主流は、「自己肯定感を高めよう!」です。ですが、子どもにとって自己肯定感を高めるというのは、そう簡単なことではないと僕は思っています。
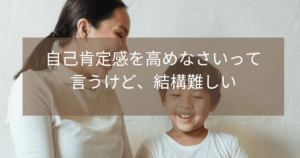
というのも子どもは子どもなりに学校という狭い競争社会に否が応でもさらされ戦っています。アドラーのいう承認欲求を否定せよといわれてもそれはちょっと酷な話です。
それでも、親は子どもが100点でなく、60点であってもそのまま受け入れてあげること。無条件で子どもを愛してあげること、これは子ども自身の自己肯定感に繋がる大事な事なことだと思います。
アドラーの考える自己肯定感は少し変わっています。
自己肯定感とは、できもしないのに自分はできると暗示をかけることだといい、対して、できないままの自分を受け入れることを自己受容といい、自己受容の大切さを説かれています。
どちらにせよ、子どもを無条件に愛してあげることは、子ども自身が自分の存在価値を感じられる大事なことには変わりありません。
自分の居場所を見つけさせよう
嫌われる勇気とは、人との関係を遮断することではありません。アドラー心理学の目標は
行動面
- 自立すること
- 社会と調和して暮らせる事
心理面
- わたしには能力があるという意識
- 人々は私の仲間であるという意識
といいます。しかし、人間関係に悩み、例えば不登校やひきこもりになってしまった場合、社会と調和して暮らせる事、仲間だという意識をもつことは、きっと難しい課題だと思います。
その点について解決するヒントとして、共同体感覚というキーワードを本書で見つけました。共同体感覚とは、他者を仲間だとみなし、そこに自分の居場所があると感じられる感覚のことをいうのだそうです。
仲間を見つけるのは、子ども自身の課題であり、親は決して介入できないのですけど、僕が子どもにいつもいうのが、学校という狭い単位ではなくて、広い世界をみてほしいということです。
本書でも、対人関係の中で困難にぶつかった時には、より大きな共同体の声を聴けといわれています。これっって大事な考え方だなって思う。これを読んで僕はさかなクンの
小さなかごの中でだれかをいじめたり、悩んだりしていても、楽しい思い出は残りません。外にはたのしいことがたくさんあるのにもったいないですよ。広い空の下、広い海へ出てみましょう。
という言葉を思い出しました。
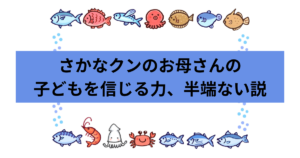
世界は広い。自分の存在が役に立っていると実感できる場所がきっとどこかにある。そう信じて前向きに生きてほしいなって思います。
まとめ 親が子どもを縛らないことが、一番子どもの幸せに繋がる
幸せとは貢献感である。本書の終わりの方に登場するこの言葉もすごく核心をついているなと思いました。人は、誰かに役に立っている、貢献出来ていると感じる事ができると、生きている価値を感じていられる。
自分の居場所を見つけられることが出来たなら、人生はきっと幸せになれる。けれど、居場所を本気で見つけようと思ったら、鎖を断ち切って冒険することが必要だと思います。
子どもが自分の居場所を見つけるために、親は子どもの人生を決して縛ってはいけない
子どもは親に喜んでほしいから、親が思う学校に行き、親が思う企業に就職する。しかし、そこに子どもが考える幸せと思える居場所があるのか?
僕には世間体があります。子どもを私立中高一貫校に行かせた。ならば大学へ行かなければ示しがつかない。どこかでそう葛藤する自分が今もいます。
そう思うと子どもの幸せを一番妨げているのは僕自身(親)なのではないか、そう思う事があります。子どもが、鎖の断ち、自分の居場所を探す旅に出るのを見守っていきたい。本書を読んで改めて強く思ったのでした。