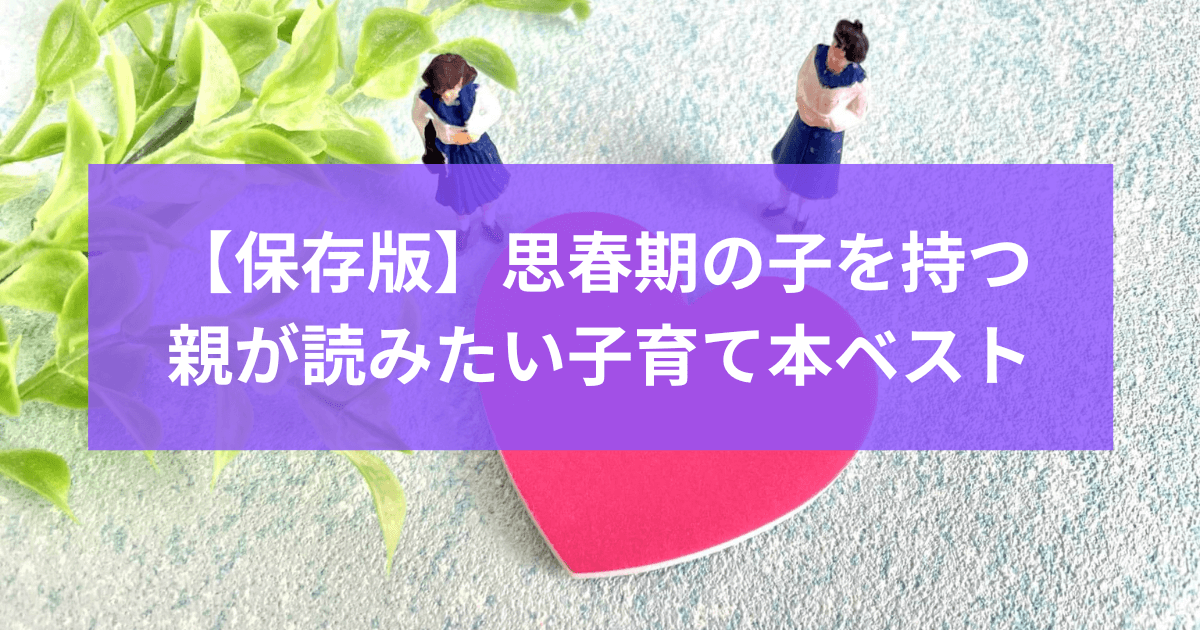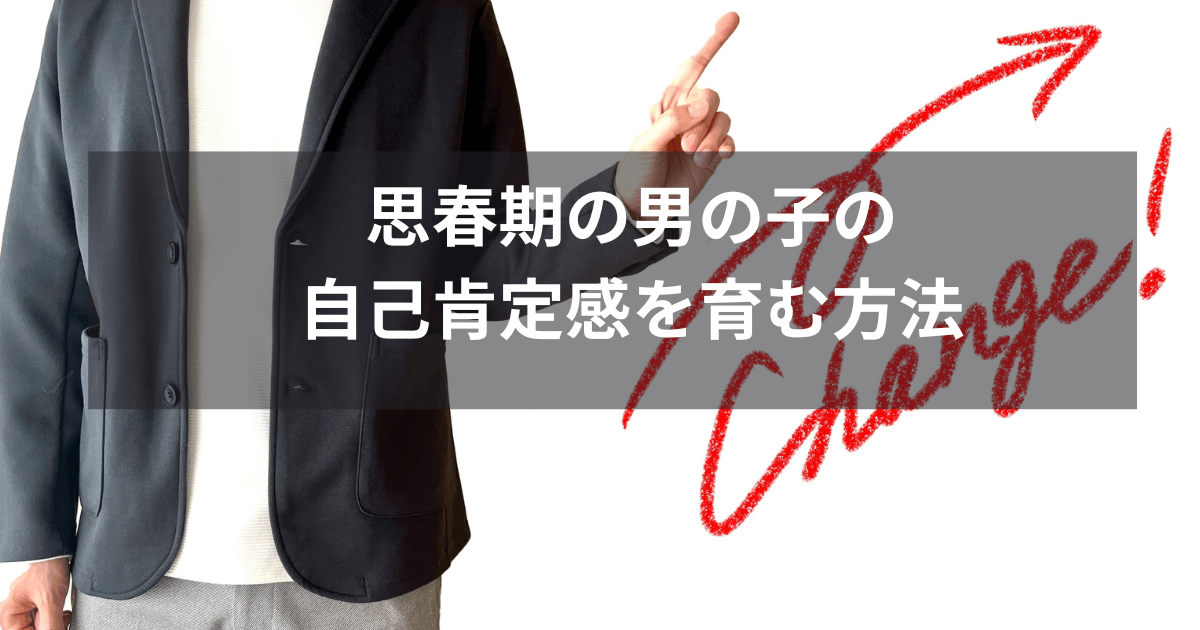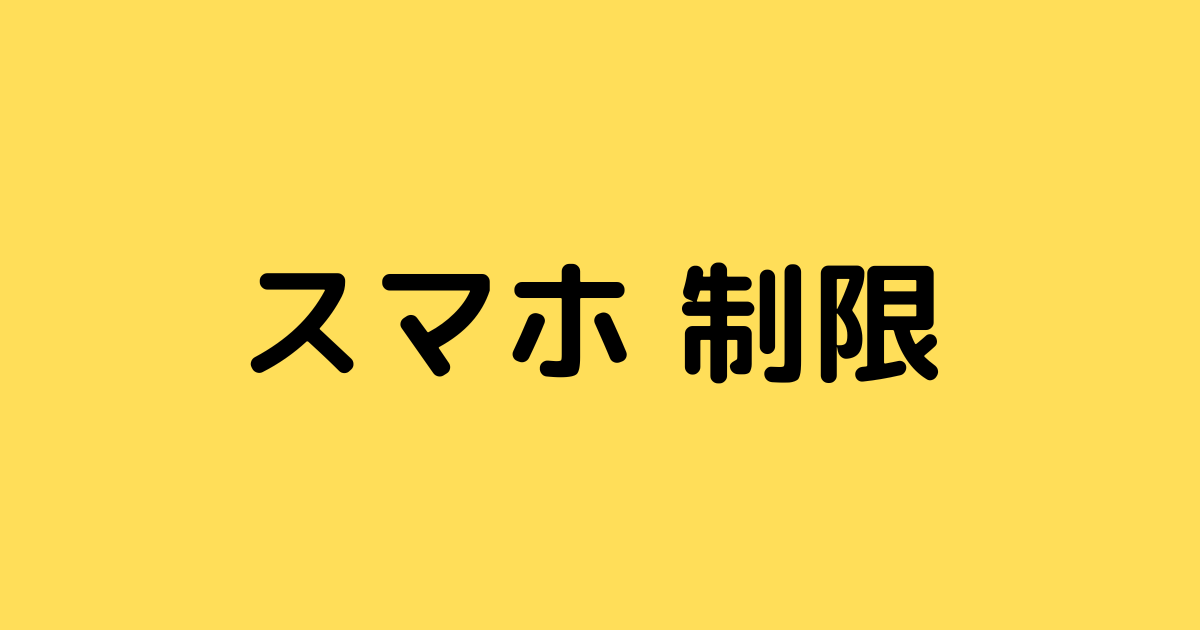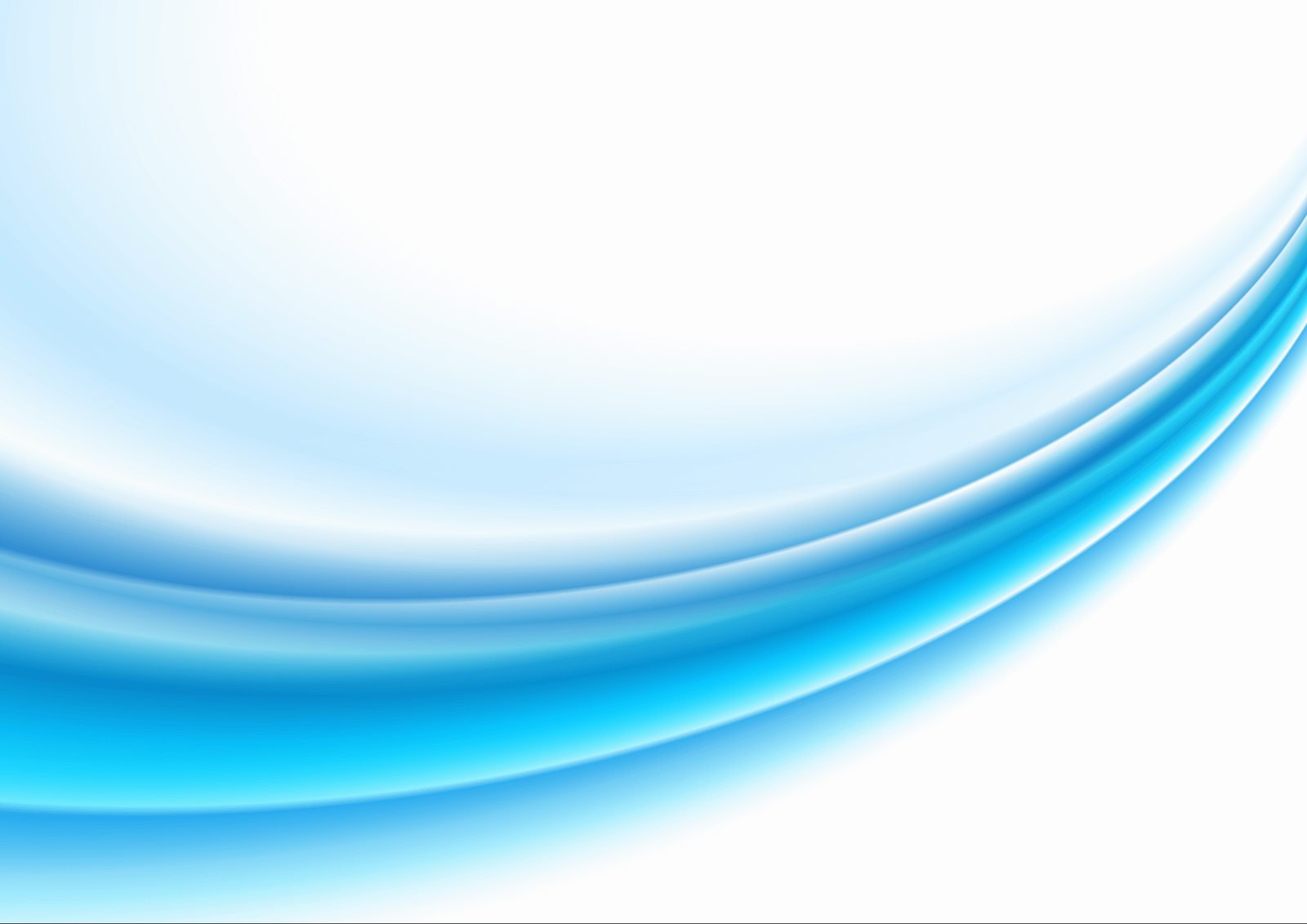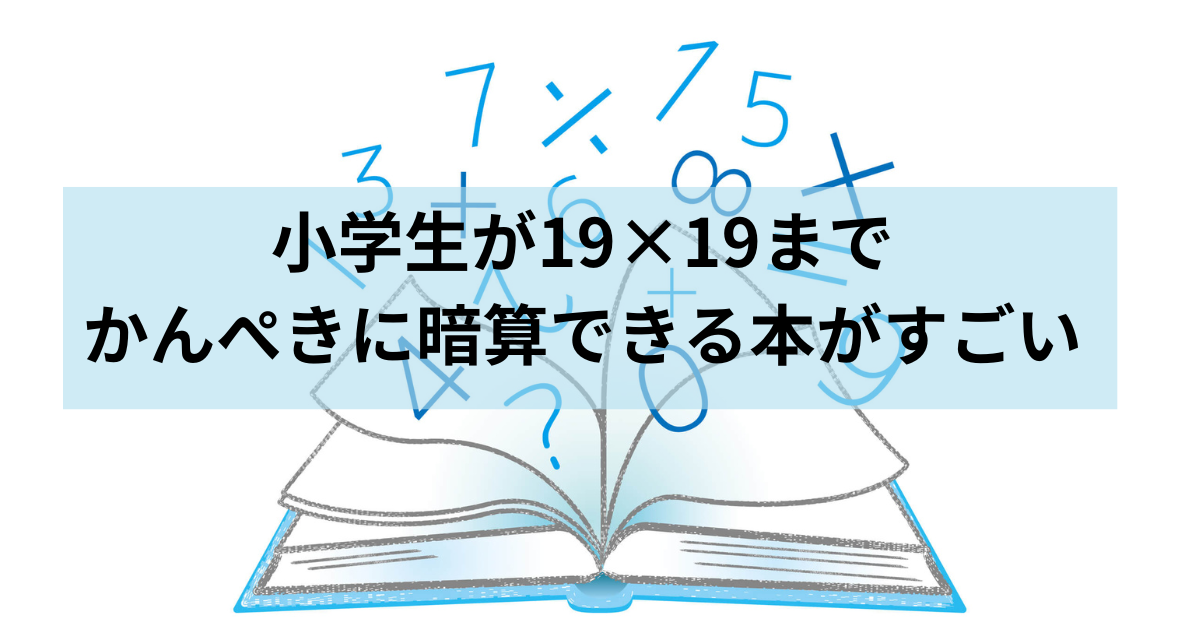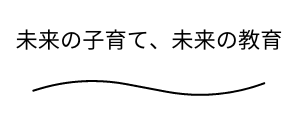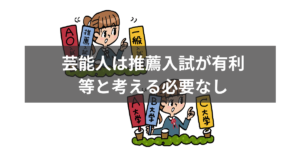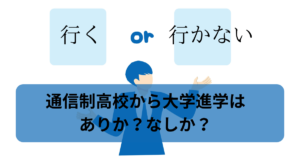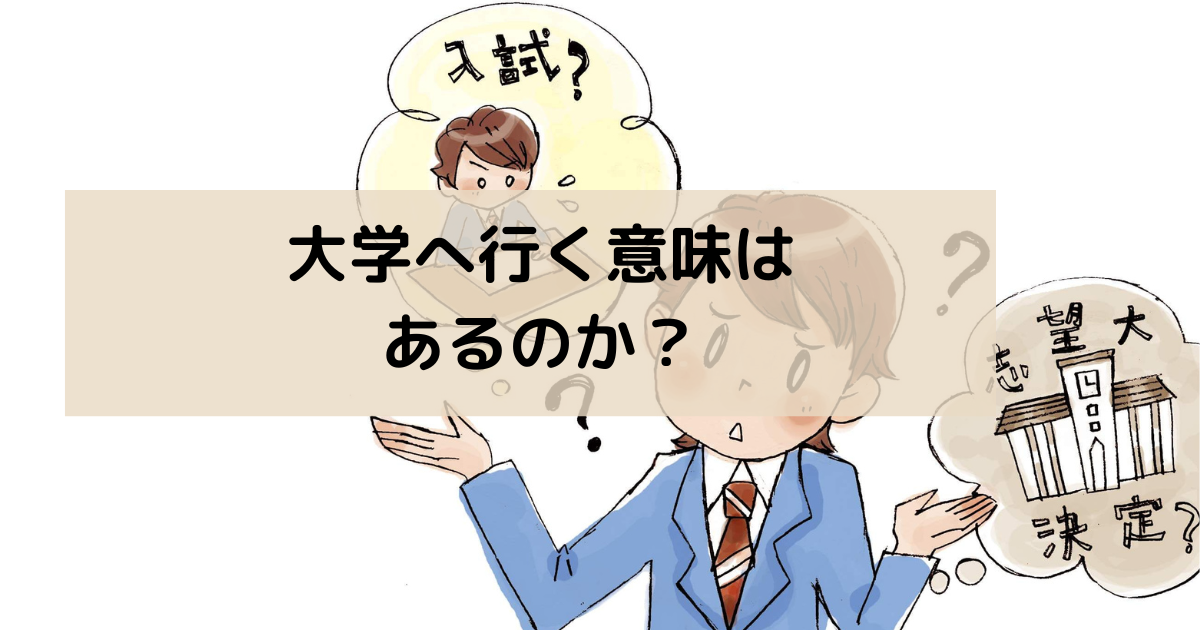
我が家の子ども達は、中学生と小学生。まだ大学を考える時期ではないですけど、今から大学進学の事を考えて、お金も含めて準備しておいても決して遅くないと思っています。
ですが、大学って行く意味って本当にあるのか?少し悩んでいるところもあります。今回は子どもの大学進学について、自分なりの考えを書いてみたいと思います。

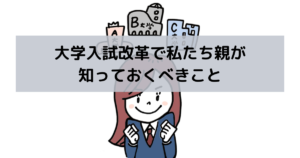
指定校推薦で大学へ行く意味があるのか?
というのも、こちらの記事。
娘さんの大学受験を見守っていらっしゃるお母さんのブログで、よく拝見させていただいているのですが、「指定校推薦組、授業中に寝ている」という記事にショックを受けました。
確かにこうした情報はネットで何度かは見てはいたのですが、リアルな情報でもなかったし、そこまで深刻には思っていなかったのです。ですが、今回記事を拝見させてもらって、今もまだそんな状態?と落胆しました。
僕の指定校推薦の疑問に対して、いただいたコメントがこちらです。
くろちゃんパパさん^^
コメントありがとうございます。
推薦入試組・・・。
本当に、ひどいようです。たとえ授業中寝ていても
授業にでているだけマシみたいです。(;’∀’)欠席・早退する子もいるようです。
体育がだるいとさぼる子まで。内申点を稼ぐために
今まで真面目にやっていたのが
嘘のようです。(;’∀’)指定校推薦が決まっても
共通テストは全員受けなければならない学校なので
模擬試験はかならず受けるように言われているのですが、
それもさぼっているようです。
もちろん、指定校推薦組の全員が全員そうではないですし、また、大学に入ってしまえば、指定校推薦組も、一般入試組も関係なく、一からのスタートです。授業をさぼっていた子でも勉強頑張るかもしれませんし、逆に高校でものすごく勉強してきた子が急に勉強を止めるといった事もあると思います。
ですが、もし推薦が決まった後、勉強しないで大学へ入った場合のハンデは思った以上に大きいと思うのです。
僕の学生時代とはまた時代が違うというのは前置きしますが、大学は受けたい教授の著書を買って授業を受けるスタイルだと思うのですが、このテキストが結構難しいんですよね。僕も学生時代、大苦戦した記憶があります。
果たして何か月も勉強もしないで脳を休めていた子が、教授の分厚い教科書を理解し、大学の授業についていけるだろうか?うちの子も指定校推薦を受ける可能性もありますから、少し考えるところがありました。
それでも大学へ行く意味がある理由
学歴が年収を上げるから
勉強がそれほど好きでもないのに大学に行く意味は果たしてあるのだろうか?それでも大学へ行く意味を考えた時、参考になった記事がこちらです。
少し前の記事ではあるのですが、はてブで見つけた作家・橘玲氏のブログ
ブライアン・カプラン氏の「大学なんか行っても意味はない?教育反対の経済学」の書評でしたが、アメリカの大学事情がよくわかってとても興味深い記事でした。
少し難しい本なので、橘氏の要約をぜひ参考いただければと思うのですが、
僕自身はこの本を読んで、大学生が単位がとれる簡単な授業を選び、試験が終われば学んだことは忘れてしまうというのは、一部のトップクラスの学生を除くと日本もアメリカも変わらないだというのがわかって面白かったです。
僕らが一生懸命勉強する「英語」は、第二外国語です。アメリカの人にとって英語は「国語」なんですよね。で、アメリカの第二外国語は、スペイン語等があったりするそうですが、ほとんどマスターできていないような事が書いてあって、それなら日本人が英語喋れないのと同じじゃない?と思ったものです。
大学卒の資格を得るために大学へ行き、大学の授業はろくに聞いていないという学生がいるのも日本と同じ。
では大金を払ってでも、大学へ行くのはなぜか?
学歴そのものが年収をあげるからです。
私たちの生涯獲得賃金は、大卒と高卒でよく比較されます。大卒であれば高卒よりも生涯賃金が6,000万円も高い。それなら綺麗ごとはいわず、大学進学は目指すべきではないか?ということです。
学歴を取得するために存在する大学。こんな教育にお金を費やす意味があるのか?
カプラン氏は
「ふつうの人は大学へ行くべきではない。もっと言ってしまえば、今のふつうの大学生は大学に行くべきではない」
とまでいいます。
そうなると、大学へ行く人は少なくなりますが、雇用主も大卒ばかりを採ることができなくなるし、もし、大学が「大卒」という称号だけを得るために行っている人が大多数なら、高卒でも十分かもしれないし、早めに社会に出て、職業訓練を受けさせるべきだというカプランの主張も、少し過剰ではありますが、ありかもしれません。
実はこれと似たようなことを言っていらっしゃるのが、林 修氏です。林氏は著書「受験必要論」で、徹底的に大学を整理、見直す必要があるといい、その代わりに、勉強以外の例えば、技術や芸術といった物差しを用意すべきだとおっしゃっています。
カプラン氏や林氏の発想は少し極端かもしれませんが、僕も猫も杓子も大学へ行くのはどうなんだろうか?と不安を持つようになりました。
大学でなりたい自分を発見できるから
大学生が勉強しないというのは、実際、大学教授でいらっしゃった鷲田 小彌太氏の著書「どんな大学に入ってもやる気がでる本」を読めばよくわかりました。

ですが著者は、それでも、大学へは行かないより行ったほうがよいと断言されています。
ひとつは、カプラン氏同様、学歴がものをいう社会である事を指摘されています。
そして、いくら大学生が勉強をしないといっても、大学にも単位というものがあり、卒業するためには単位の取得が必要でテストだってある。高校よりもより専門的な学習を否が応でもし、その知識や技術を得ることができるのも大学であり、価値があるということもおっしゃっている。
最後に、大学には時間的猶予(モラトリアム)があるとおっしゃいます。4年間という時間を使ってなりたい職業を見つけられるとういうケースだってあります。非常に贅沢な時間の使い方でありますが、これも大学へ行く価値があるひとつだといえますね。
さすが元大学教授の視点だなと思いました。理想と現実。現実問題、学生は今も学ばない子が多いのかもしれないけど、大卒の意味はそれなりにあるということです。
著書を読んで、大学へは行けるのなら行った方がいいと思えるようになりました。
ひろゆき氏の大学無償化案が理想
どんな動機であっても、子どもが大学進学したいといえば、応援してやりたいと思うのが親ですね。ただ大学の授業料はとても高い。
すでに子育てを終え、子どもの大学費用を捻出された世代の方には申し訳ないのですが、僕は、近年議論されている大学無償化をぜひ政治の力で実現してほしいと願っています。
しかし、さすがに上記のような、「指定校推薦が決まったら、授業中に寝ている。。。」そんな子に対して、税金を大学無償化に使わせていただくのは申し訳ない。
ひろゆき氏は著書「僕が親ならこう育てるね」で、基本、大学無償化は賛成であるが、共通テストを実施して一定以上の点数を採れた子だけ国が大学費用を払う制度にしたらいいとおっしゃっていますが、まったくもって賛成です。
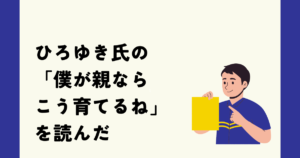
最低限、大学入学共通テストで点数が採ること
僕はもっといえば、大学入学共通テストは、高校卒業レベルの基礎学力を問うテストでよいと思っています。勉強の難度は特別問わずです。
「0才から100才まで学び続けなければならない時代を生きる 学ぶ人と育てる人のための教科書」の著者・落合陽一氏であったり「賢い子はスマホで何をしているのか」の著者・石戸 奈々子氏も、これからは何を学んだかよりも学び続ける力が大事になるとおっしゃっています。
それなら大学入試試験は、高校を卒業するまでコツコツ学び続けていた子が合格するような試験であってほしいと思います。イコール大学入学時に、高校卒業レベルの基礎学力を有している子。
とはいえ、大学の授業についていけるレベルといっても、高校卒業レベルの基礎学力だけで東大の授業が理解できるかというとそうでもないように思いますから、二次試験で入れる大学が絞り込まれるというのも必要かもしれませんし、受験方法も偏るのではなく、多様化しておくのがベストだとは思います。
いずれにせよ最低限、学び続けている子。大学共通テストで点数が採れる子に対して支援をしてあげるべきだと思うのです。
総合型選抜入試はどうか?
今のところですが、総合型選抜入試は学校推薦入試よりもよいと思っています。林先生は、上述の著書「受験必要論」で、総合選抜型入試にしても、その対策塾が出てきて、結果、小論文でも皆同じようなものになると指摘されているので、確かに疑問は残ります。
しかしそれでも、学生が大学で何を勉強したいのかを一定調べて受験する制度なら、多少意味はあるのかなと思います。ですがここでも大学入学共通テストの点数は必須ですね。
まとめ。大人の事情に振り回されず、大学で学べる力を身につけて進学できる子に
指定校推薦は、高校の大学進学実績をあげるため、また大学の学生確保のため、双方がWinWinで作られた制度だと僕は理解しています。大人の事情ですね。
なのでこの指定校推薦の仕組みはそう簡単には変わらないでしょう。だけど、どうしても今のままの仕組みでは、子どもにとってもあまりよい制度とは思えないです。
だから、自分の子のことを思う時、大学へは行ってもいいけど、最低限、大学の教科書が読めるレベル、学力を有していくことを条件に支援したい。
大学のテキストは分厚いし、普段、本を読まない子は苦戦するのは、僕の過去の経験からも明白。なので、僕は学校の勉強に加えて「本が読めたらいいよ」と子どもには常にアドバイスしています。
ひょっとして大学で何をしたいのか見つからずに進学するかもしれない。それでもかまわない。だけど、最低限の学力を有して、大学の授業を理解できる力をもって進学して、大学で勉強して、自分がなりたい職業を見つけてほしいなと思います。
それなら、大学へ行く意味が出てくるのではないか。そう思います。