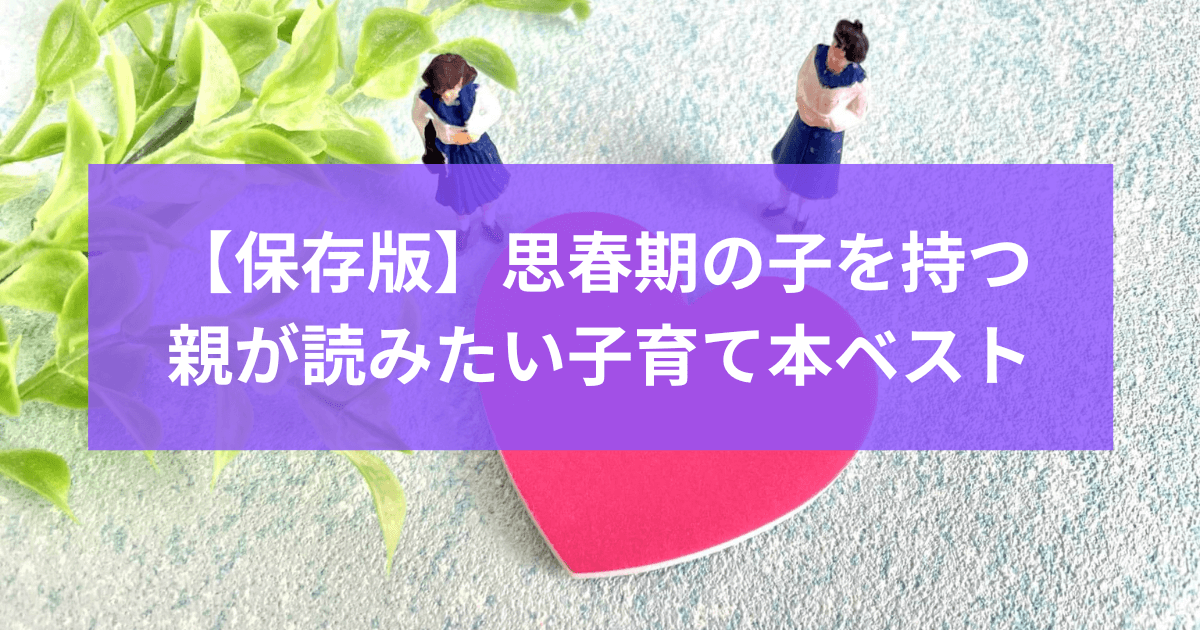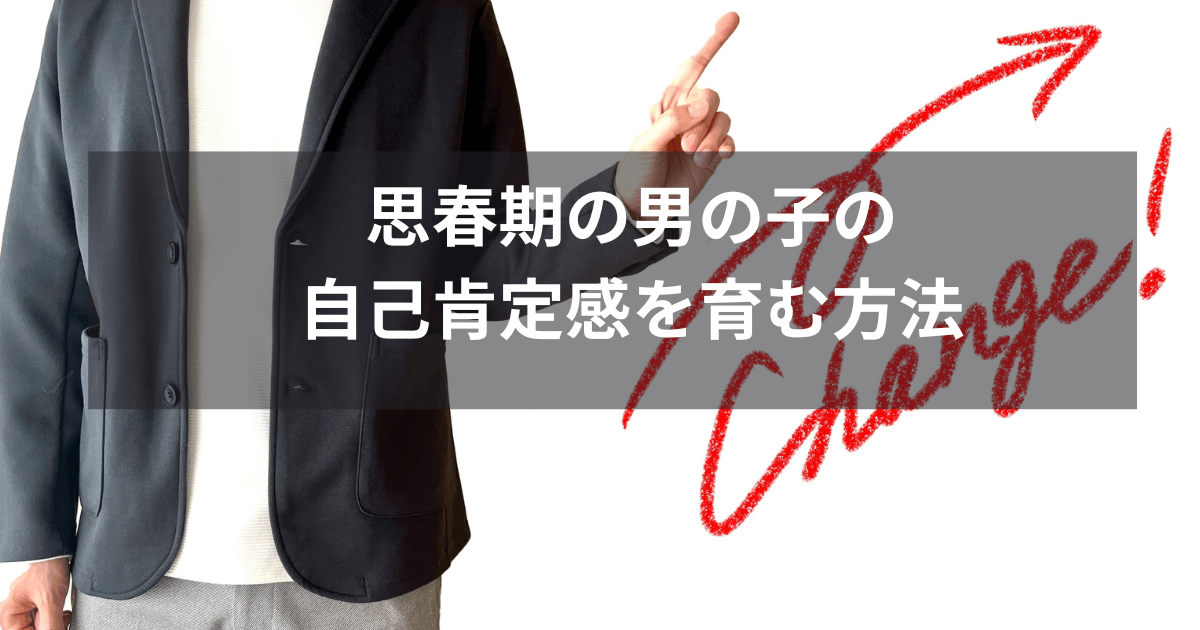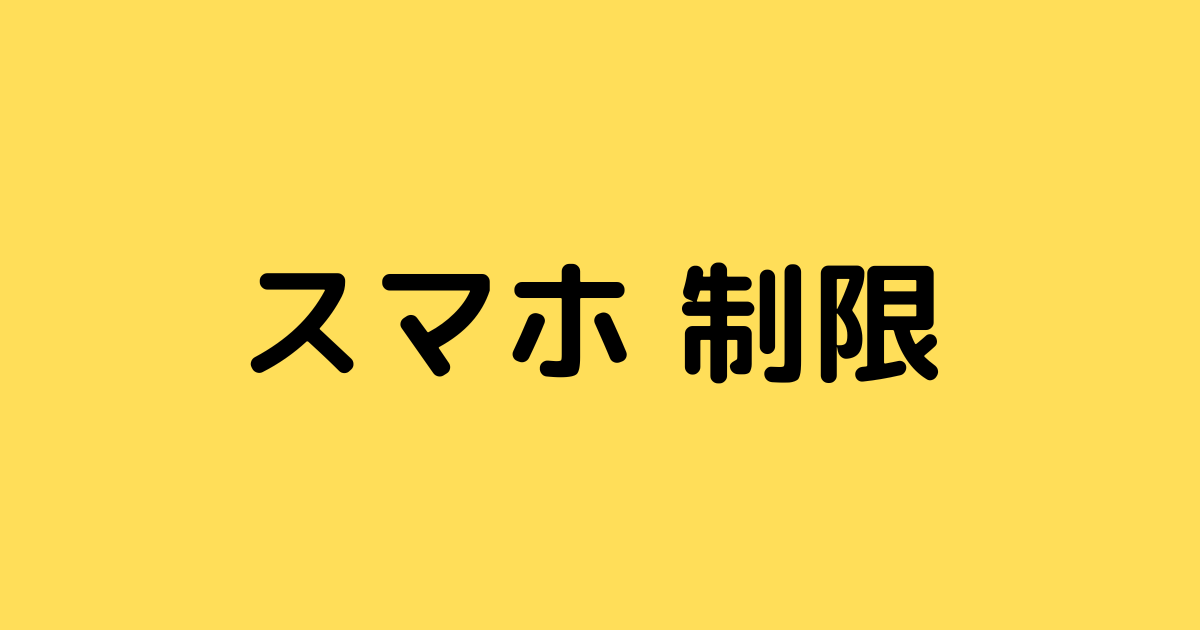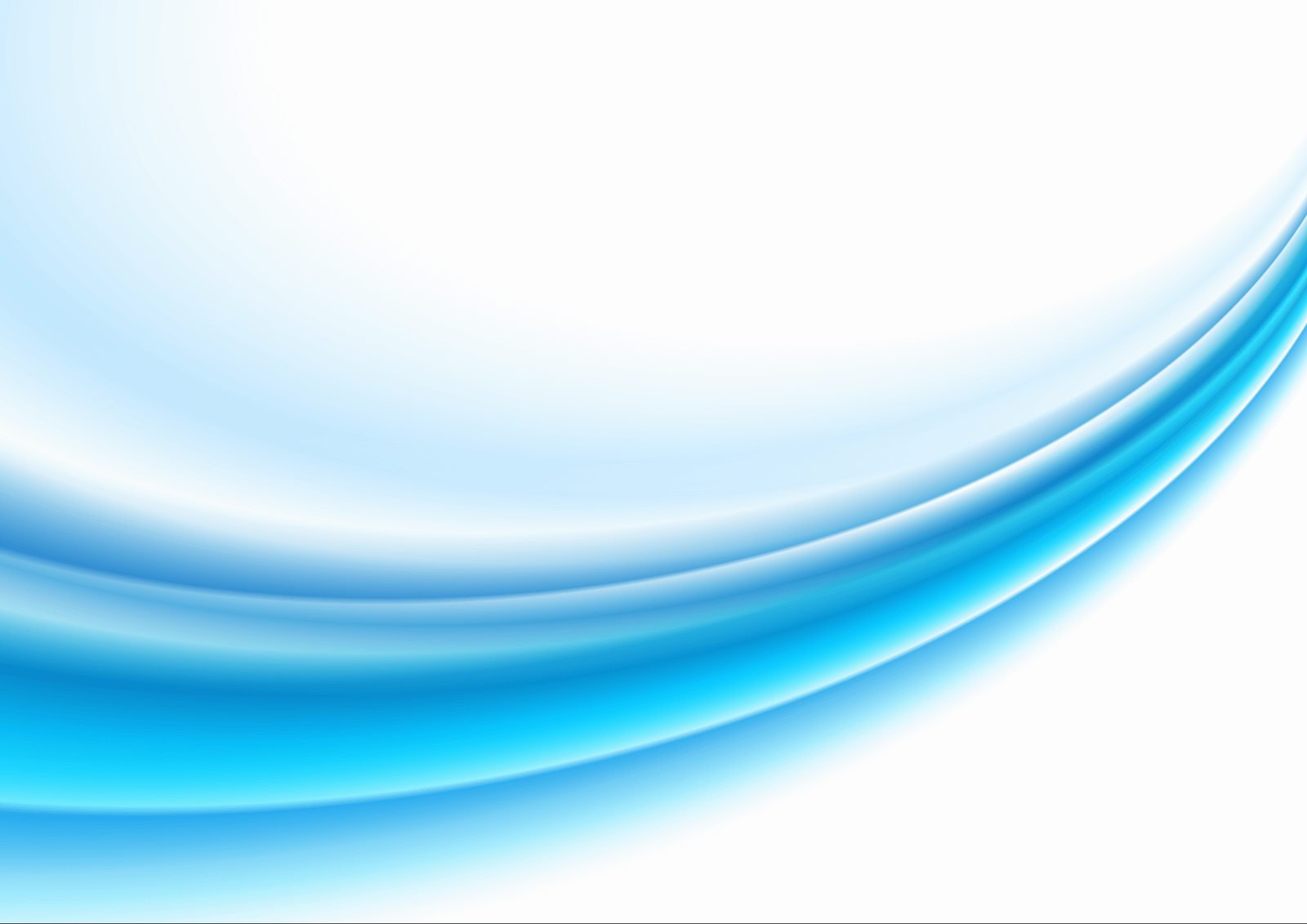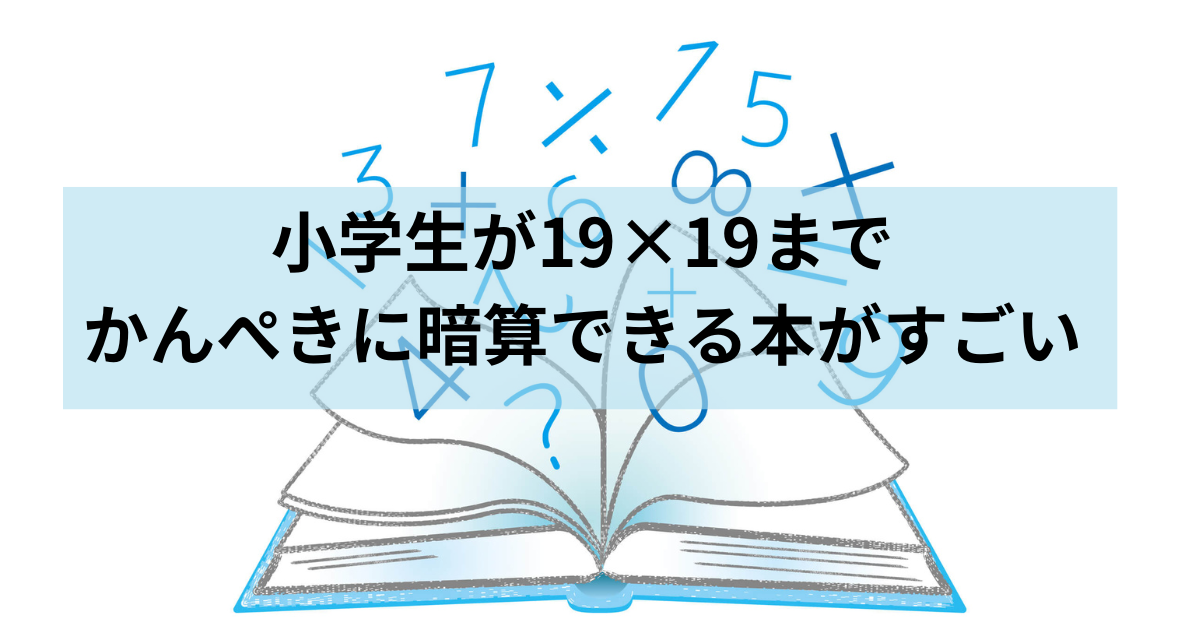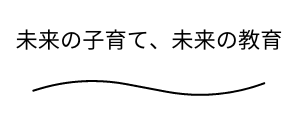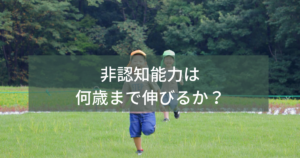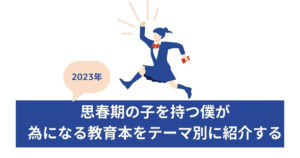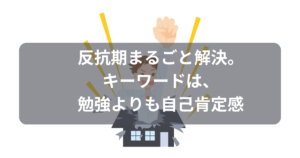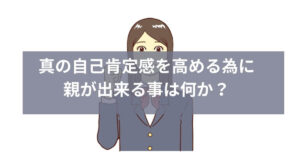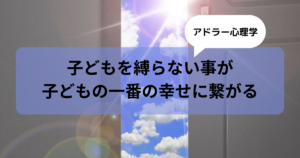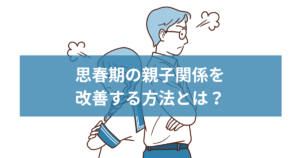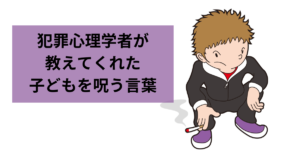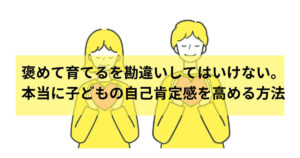二人の娘を立派なレディーに育てたい。二人が考える「幸せ」のお手伝いをしたい。常日頃、そう考えながら子育て本を読んでいます。とはいえ、本を読んだからって、自分の思うようにいかないのが子育ての難しさ。
さて、子育て本を読んでいると、必ず出てくるキーワードがあります。それは、「自己肯定感」です。とにかく子どもの自己肯定感を高めようという事が書いてある本が多いのですが、この自己肯定感を高めるというのも、実はそう簡単にはいかない。
今回は自己肯定感とは何か?という事にスポットを当てて記事を書いてみたいと思います。
自己肯定感とは何か?
「自己肯定感って何か?」ってことですが、書いて字のごとく、ありのままの自分(自己)を好きになるとか、自分を肯定するという意味でいわれます。
ちなみにこの自己肯定感は、勉強といった能力ではない、非認知能力の一つといわれて昨今の子育て本には、よく登場するキーワードです。

子育て本の多くには、
- 「海外と比べて日本は自己肯定感が低い」
- 「海外は子供を褒めて育てるから、自己肯定感が高い」
などと、海外と比べられることが多いのですが、2016年の子ども・若者白書によるアンケートによれば、確かに日本の自己肯定感は低い。特に自分自身に満足しているかどうかのアンケートで、日本人が45.8%なのに対して、アメリカは86.0%と倍近い差がついています。1
ではなぜこの自己肯定感が大事なのでしょうか?
自己肯定感が低いと、自分自身を肯定できないため、失敗することをとにかく恐れるようになります。挑戦を避けるようになる。今までは、言われた仕事をどれだけ早くこなせるかで評価されていた時代ですが、今後は自ら挑戦することが必要な時代です。
自己肯定感が高い子であれば、失敗を恐れずにチャレンジする能力を身につけることができるというわけです。
一方で自己肯定感は、2種類あるといわれています。
- 自らのアイデンティーに目を向けて、自分の長所のみならず、短所も含めて自分自身を受けいれることができること。
- スポーツなどで他人と競争する中で努力し得られる達成感や他人からの評価を経て育まれるもの。
どちらも自己肯定感ですが、1のほうは、他人の評価を気にすることなく、ありのままの自分自身を肯定する自己肯定感のことです。
一方で、2も自己肯定感です。ですが、他人の評価は心変わりすることもあり、自分以上の存在が現れた時には簡単に崩れてしまうものだと言われていて、安定した自己肯定感にはならないとされています。
幼少期にできる子どもの自己肯定感の高め方
子どもが幼いとき、そうですね、小学生の頃までは子どもは親に依存します。ですから、自己肯定感を高めるために、親が愛情をいっぱい注ぐことで、自分は愛されているんだ、ありのままの自分でいいんだという自己肯定感を育むことができます。
とにかく子どもが幼い時は、子どもを褒めて伸ばすのがよいでしょう。
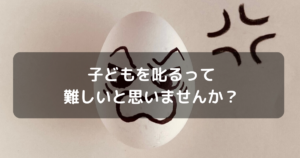
自己肯定感を高めるのは、具体的にどこがよいのかを言ってあげると効果的です。僕も自分の娘には、それぞれの得意なところを具体的に褒めて伸ばすことを常に考えています。
- 長女は音楽をやっていますが、忙しくても毎日必ず楽器の練習をしているところが偉い!
- 次女は、1時間かけて片付けをしなければいけないのを最後まであきらめずに手伝ってくれた。それがすごい!
このように出来るだけ結果ではなくてプロセスを、そして具体的に何が良かったのかを、毎日見つけて伝えています。こうした子どもを具体的に褒める言葉かけは、自己肯定感を高めるベースです。
ですが、子どもは子ども同士のコミュニティーの中で戦っています。こうした親だけの言葉かけだけで自己評価を高め、他人の評価が全く気にならないという悟りに達するのは、そう簡単なことではないでしょう。
実は難しい。思春期の自己肯定感を高め方
他人の評価に振り回されることなく、自分自身を肯定できれば、これは素晴らしいことです。ですが、子どもを伸ばすために他人の評価が全くいらないのかというと、少し疑問があります。
たとえば、僕のこのブログを例に説明します。
このブログをやっててよかったなと思う事ですが、始めた当時(はてなブログでした)、本当にうれしいことに読者登録をたくさんしていただだきました。また、記事を書けばスターや、ブックマークまでいただくこともありました。
これが僕のブログを続けようというモチベーションをあげていたのですが、これは他人から評価を受けていることで、自己肯定感が高まっている状態です。
- 「よし、もっとよい記事を書こう!」
- 「よし、もっとブログのデザインをよくしよう!」
という気持ちも、僕のブログが少なからず評価されていると思うから起こるものです。
これがもし、ブログを書いていても、アクセスがほとんどない状況だとしたらどうでしょう?きっとブログを書くのを止めてしまっていたと思います。
子どもも同じだと思うのです。
子どもが小さいときは親に依存しているからいいでしょう。ですが、思春期になると子どもが評価されたい対象は、親から先生や同級生へと移っていきます。
自分自身を肯定する為にも、客観的評価も少しは必要だということになります。
やっぱりNo1になることで自己肯定感は高まる
小学校時代って、足の速い子とかが、スポーツが出来る子が人気者であったり、生き生きしているのも、
- 「足が速い」
- 「スポーツが出来る」
といった点は、子どもにはわかりやすい他人の評価で、自己肯定感を高めていると考えることもできるなと思うのです。
最近は深刻ないじめ問題もあって、他人と比べない教育をされている学校が多いと思いますが、僕は小さな一番をたくさん作ったらどうかと思っています。
「足が速い」とか、「勉強ができる」
とかは、学生からすればわかりやすい評価ですが、
- 絵がうまい1番
- ピアノがうまい1番
- 字が綺麗な1番
とか、小さい1番もたくさん作ってあげて、学校で発表してあげる。他人の評価だけの自己肯定感はもろいとはいいますが、それでも嬉しいものだと思うし、自信にもなると思うのですね。
元開成中学の校長である柳沢氏も、著書「思春期の男の子の自己肯定感を高める育て方」で、勉強以外の価値観を持たせることの重要性を説いておられる。
勉強では叶わないけど、ピアノではクラスの誰よりも上手い。口に出さなくても自分の中で大きな自信にしたらいいと僕は思うのです。それが自己肯定感を高める。
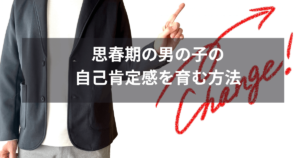
ネットショッピングの楽天市場では、小さな1番をたくさん作ります。例えば、化粧品売り上げ1番をとるのは難しくても、「50代の化粧品売り上げ1番」という小さなカテゴリを作って、そこで小さな一番を作るのです。
小さな1番で子どもを褒め育てる。これで子どもが自信をもってくれて、自己肯定感が高まれば僕はいい事だと思うのですね。
とまぁ、理想論を書いたのですが、現実は、学校がそんなことをしてくれるわけでもなく、親がそれこそ子どもの小さな一番を見つけて、褒めて育てなくてはいけないなと思っています。
まとめ。子どもの選んだ道を応援することで、自己肯定感を高めてやる
小さな一番を見つけて褒める。そしてますます子どもが努力する。全員が全員そう上手くいったらいいのですが、自己肯定感を高めるのはそんなに簡単ではありません。
子どもが大きくなればなるほど、親に依存しないわけですから、他人の評価も気になります。そして他人の評価に流されてしまうことだって多い。これは仕方がないことだと思うのです。
相手関係なくありのままの自分を受け入れることを自己肯定感っていうとありますが、子どもも子どもなりに狭いコミュニティーで戦っているんですから、他人を全く気にしないって結構、難しいと思うのです。
確かに、他人の評価は絶対ではないです。急に梯子を外されることもあるわけです。でも、小さなコミュティーでもいい。客観的に評価されることは、自分自身を愛せるひとつのベースにもなると思うのです。
そのために親は、子どもの小さな1番を探し、それを褒め続ける。時間はかかるかもしれないけど、自己肯定感を高めるために親ができることはやっぱりそれくらい。そして、子どもの自信を加速させるには、少しは客観的評価も必要あるとは思います。
作詞作曲家で、オリコン120曲で1位を獲得、そして今はグローバルに活躍されている岡嶋かな多氏は、著書「夢の叶え方はひとつじゃない」で、自己肯定感が低く、ようやく自己肯定感が高まってきたのが、20代後半だったとおっしゃっています。

ですから、僕は子どもの自己肯定感が今低くても問題ないと思っています。岡嶋かな多氏だって、自己肯定感が高まったのには、多少、他人の評価もあったのだろうと思うし。
そう考えると、親は子どもが選んだ道を応援し、子どもがそれで結果を出すことができた時に、自己肯定感は飛躍的に伸びるのだろう、そう思っています。
そう考えると、本に書いている以上に、自己肯定感を高めるって、結構、難しいとも思うのですが、子どもの自己肯定感を高める努力は親として続けていきたいと思うのです。