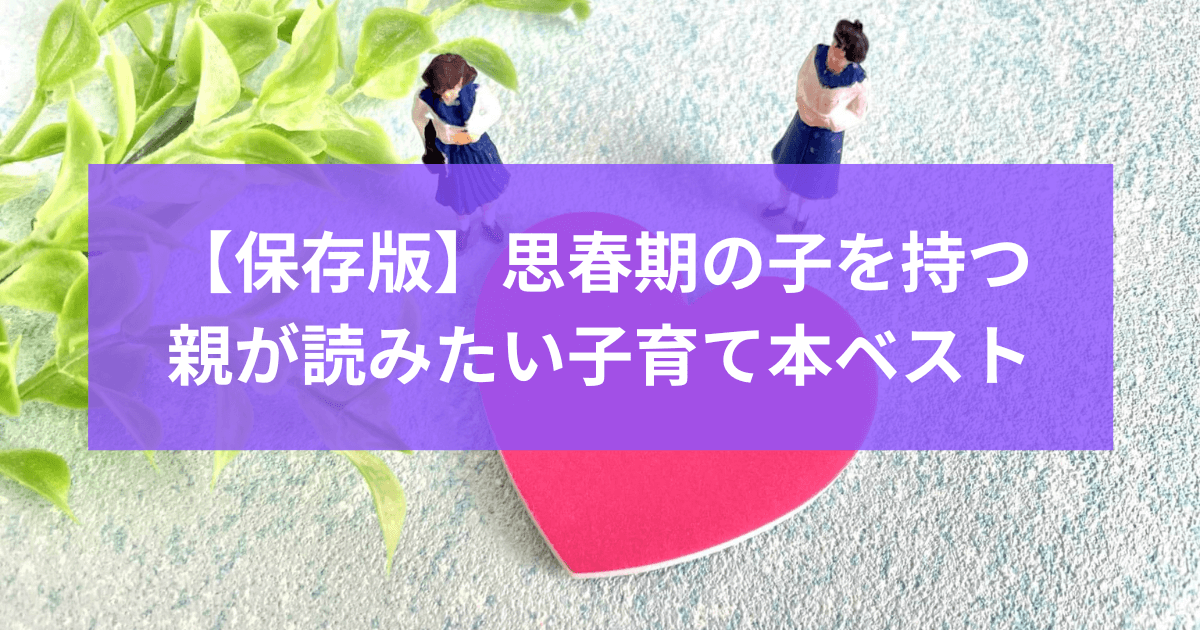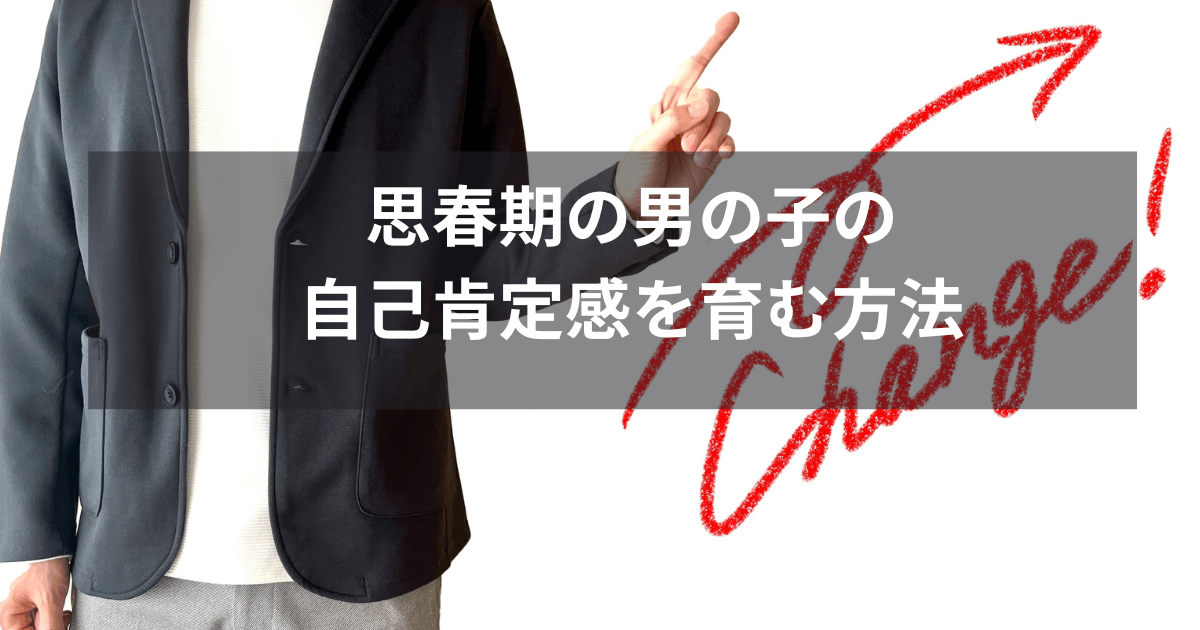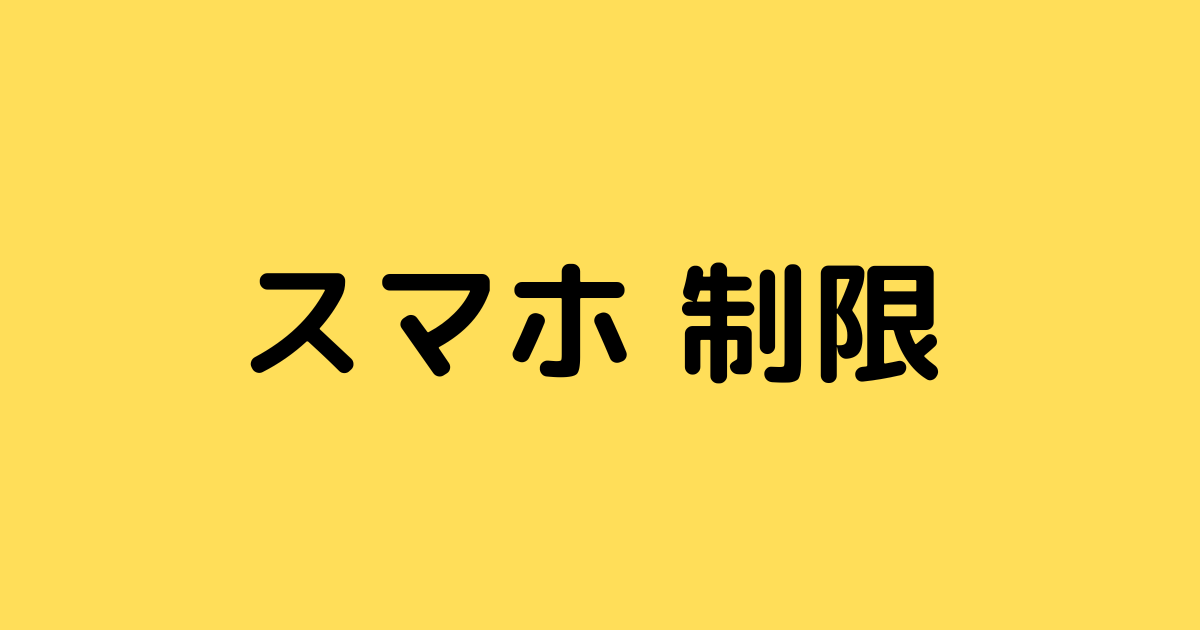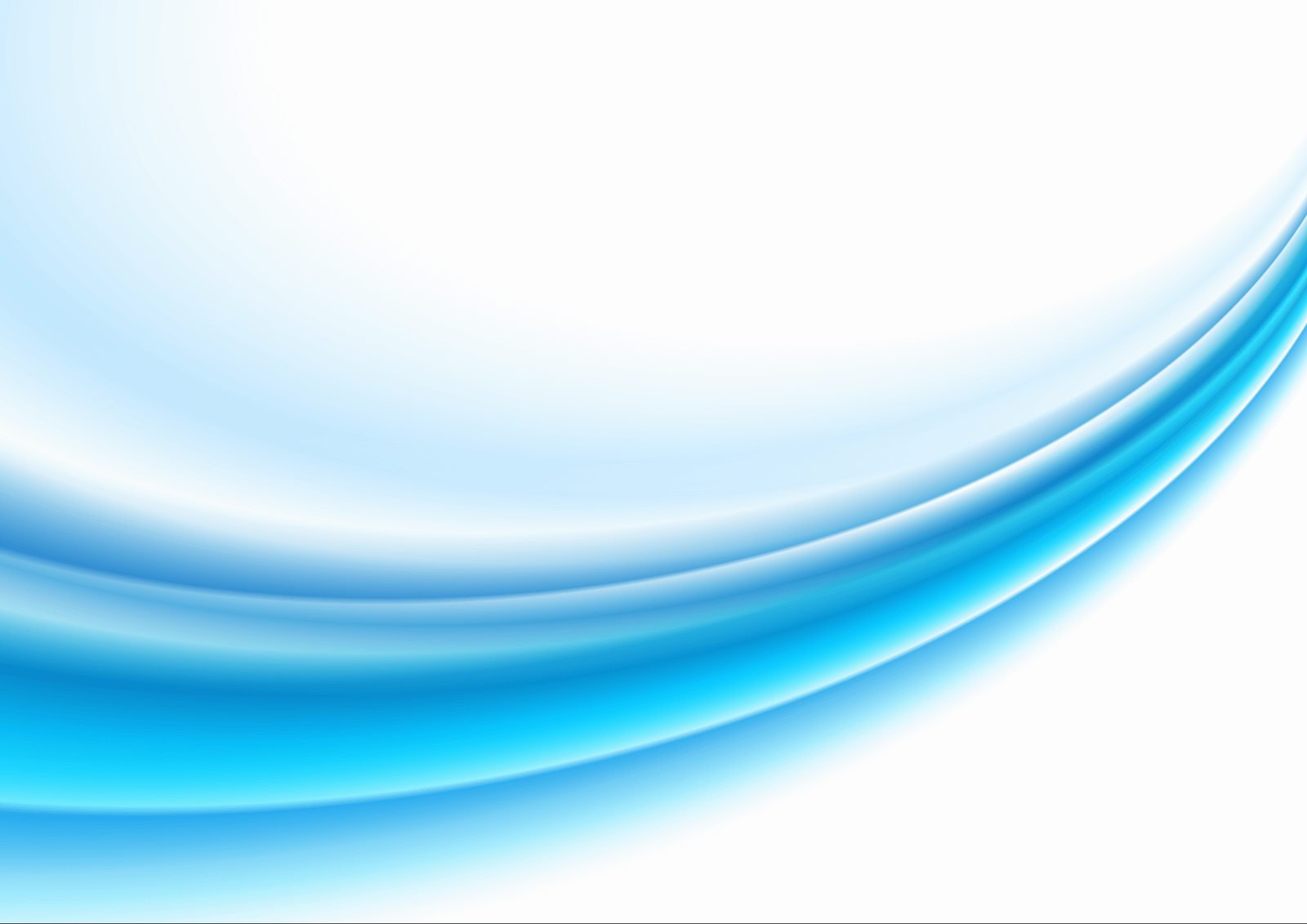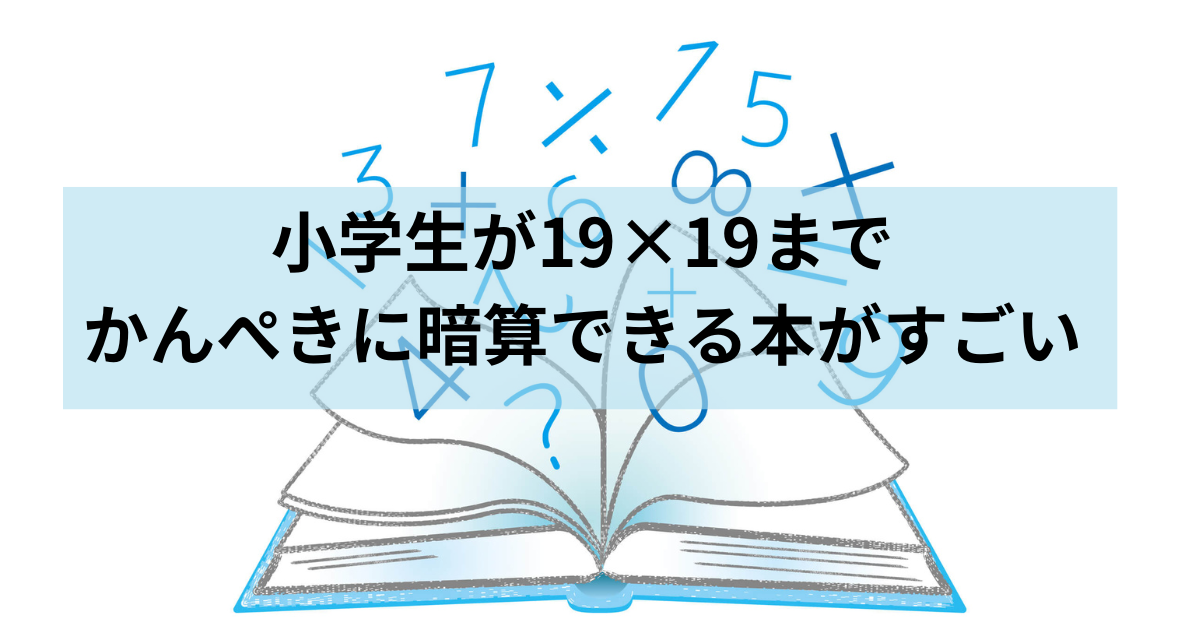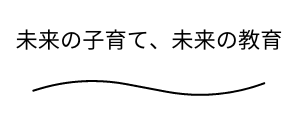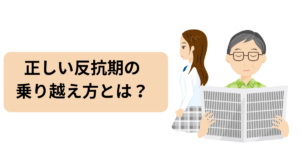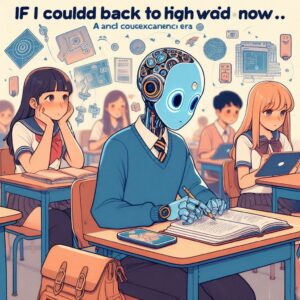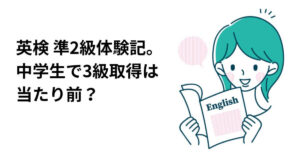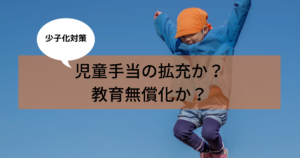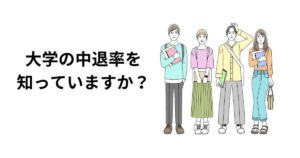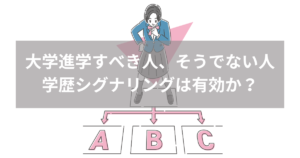以前よりブログで書いていたとおり、僕は今、通信制大学で勉強をしています。〇〇年ぶりの大学です。通学する大学ではなくて、通信制大学ですので、学び方も違うので何ともいえないところもありますが、当時大学生だった僕よりも、俯瞰して大学で学ぶとはどういうことなのか?を見ることができています。
僕自身は学びなおしたいと思った事があったので、大学へ入りなおしましたが、娘はどうでしょう?大学へ行って学ぶべきかどうか悩んでいるようなので、僕が大学生になった今、少しはアドバイスできるかなと思っています。
そしてこのブログでも、大学進学に悩むご本人や、お子さんが本当に大学に行くべきなのか?悩んでいる親御さんに向けて参考になる情報をつづっていけたらいいなと思っています。
この記事を読むにあたっての注意点
まず最初にお断りしておくことがあります。冒頭にも書きましたが、僕が入学したのは通信制大学です。ですので、いわゆる一般的な通学する大学とは異なる点が多々あるだろうことを予めご了承のうえ、読んで欲しいです。
次にこの記事は、大学進学について以下のように悩んでいる
- 特に大学で学びたい事がない
- 勉強は嫌いだし、特別高校時代に勉強を頑張ってきたわけでもない。
- 大学費用が高額で奨学金を受給しながら大学進学を検討している。
方に向けての発信だという事をご了承の上読んでいただきたいです。
高校時代に勉強を頑張ってこられた学生さんは、迷うことなく大学進学でよいと思います。僕も我が子が大学で学びたい事があると、勉強を頑張ってきていたなら、それを全力で応援していたでしょう。
でも、勉強したい事もない、勉強は好きではないと不安に思っている方は不安だと思います。そこで、大学で学ぶということをより大人になった僕が俯瞰的に大学の勉強というものを評価してお伝えしたいと思います。今日はその第1回目です。
大学の学びは社会に出て役立つのかについて考察
さて、ここまで僕が大学で学んできて思った素直な感想をこれから綴っていきたいと思います。大学で学んで、それが社会に役立つのか、将来のキャリアに役立つのかといった視点で書いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1年2年次は教養科目が中心。これは理にかなっているが心配もある
僕は編入学なので、大学3年生から勉強をスタートしています。ですが僕が通う大学の1年2年次は、教養科目の授業を中心にとるのが普通です。この教養科目の多くは、高校の授業の延長のようなものです。
えっ!大学生なのに高校生の延長のような授業をやるの?という疑問は、今財務省と文科省で散々議論しているとニュースにもなっています。
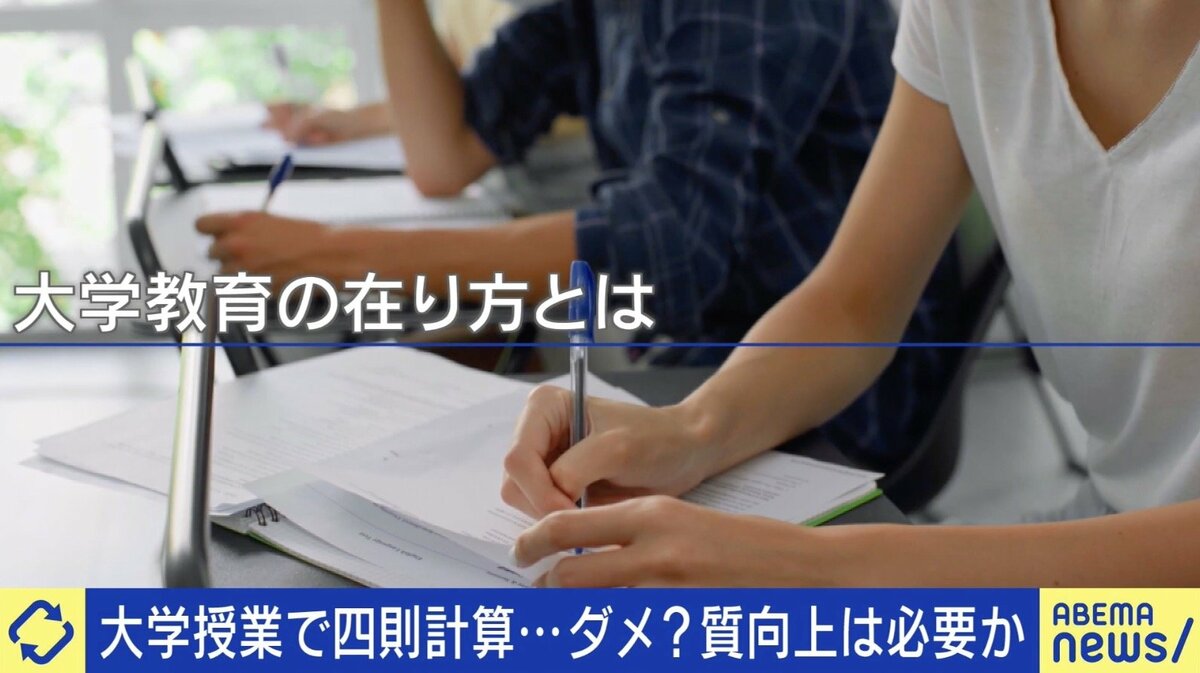
正直、大学で四則演算からやりなおしは、やりすぎです。単位をあげるためにボーナスで授業をやっているようなものですね。
ですが、いきなり大学生になったからといって、専門科目を1年からバリバリ授業するのは難しいだろうなというのも、実際、授業を受けてみての感想です。
なので高校の授業は理解できるというのは前提で、1年2年は、高校より少し難しくなった教養科目からならしていって、徐々に大学の学び方を身につけていく。何事もステップが大事なので、僕はそれは理にかなっていると思います。
ただし、意味のない教養科目もたくさんあります。なので単位が欲しいからといってあまり身にならないような簡単な教養科目をとるという方向性に走ると、せっかく大学で学んでいるのに、無駄な勉強の仕方になるといえるかもしれません。
また、1年2年が一般教養中心であれば、専門科目を学ぶのが3,4年の2年間だけになる。さらに3年から就職活動を前倒ししてすぐに就職が決まったとしたら、以降そんなに大学で勉強しないだろうなと考えると、大学で専門科目を勉強する時間があまりにも短いのでは?と危惧するところはあります。
諸外国で4年卒業(学位)がそんなに評価されないのも、専門科目を学んでいる時間が少ないからではないか?と思うので、博士号までいかないと大学の学びって中途半端に終わる感じもしないでもないです。
単位をとるのに必死になりがち
大学で学問を探求しようと大学へ再入学しましたが、いざ入学すると、学問を探究するというより、単位が欲しい!という勉強になりがちです。
僕が学生時代に「試験、試験」で学校を卒業してきたらその感覚が身に染みているんでしょうね。でもそれって本来の学問を探究したいという意義からは大きく外れます。
原因の一つは、必須科目に勉強したくない授業が結構ある。これはもう単位を取得する為だけに試験勉強をしているようなものです。
必須単位なので採らなくてはならないし、卒業の為には単位取得しなければいけない。大学としたら専門を学ぶためにはこの勉強だけはしておいてね。という必須科目ではあると思うので、我慢して勉強していますが、僕が理想を掲げて入学した、学びたい分野を探究するという趣旨からは大きく外れることになっています。
やっぱり単位は落としたくないし、試験のために勉強しちゃうでしょ?と思います。こういった授業が多いと、大学で身につくことは少なくなると思います。
僕は通信制なので双方向よりも一方通行の授業が多いので、こうした単位を採るための勉強になりがちかもしれません。通学する大学生は双方向の授業が多いのかな?その点がわからないのですが。
専門科目は理解が難しい
とはいえ、大学授業に中身がないかといえば、専門科目はしっかりと中身があり難しいとも感じています。社会人経験をへて入学した僕ですが、新しい分野の学習は、ついていけない科目もあり、必死に復習しなければいけない科目もあります。
ただ思うのは、専門科目は、「社会人を経験しているから意味がわかる」という授業も多いです。社会人を経験していれば刺さる言葉も、高校卒業して一度も社会に出たことがない学生には刺さらないだろうなというのも多々あります。
あぁ~、これ社会人経験してるから理解できるけど、当時学生だった僕ならたぶん理解できていないだろうな
というのがいくつもある。
自分が経験しているから知識として入ってくる、理解できるというのは言い換えれば20歳前後の学生だったら、何を勉強しているのかもわからないという場合も多いのでは?ということ。
もちろん頭のきれる子で、理解できる子もたくさんいるだろうけど、社会経験を積んでから大学で学ぶのも、より大学の学びを理解するうえでは、アドバンテージかなと思います。
まとめ
大学で勉強し始めてから1カ月がたって、おじさんである僕が実際に大学の授業を受けての感想を述べてきました。大学生活ははじまったばかりなので、日が経つにつれて新しい発見が出てきたり、また、ここに書いた事が違うと感じる事も出てくるだろうと思います。
都度、感じた事をブログに書いていければいいなと思っていますのでよろしくお願いします。
今のところの大学の勉強は
- 卒業するためには単位も欲しいから、単位の為に勉強しがち。そのため、学問を探究するという余裕がない
- 1年2年次は教養科目中心なので、ステップバイステップで授業は進行できる。
- ただしさすがに基礎はできていないと授業にはついていくのは大変だろう。
- 専門科目はそれなりに難しい。社会人を経験して理解できることも多いので、3年までに学びたい事を確立しておかないとその後の勉強は辛いかもしれない。(授業を受けていてもさっぱり理解ができない)
という感じです。ではまた勉強の合間にブログ投稿しますね。